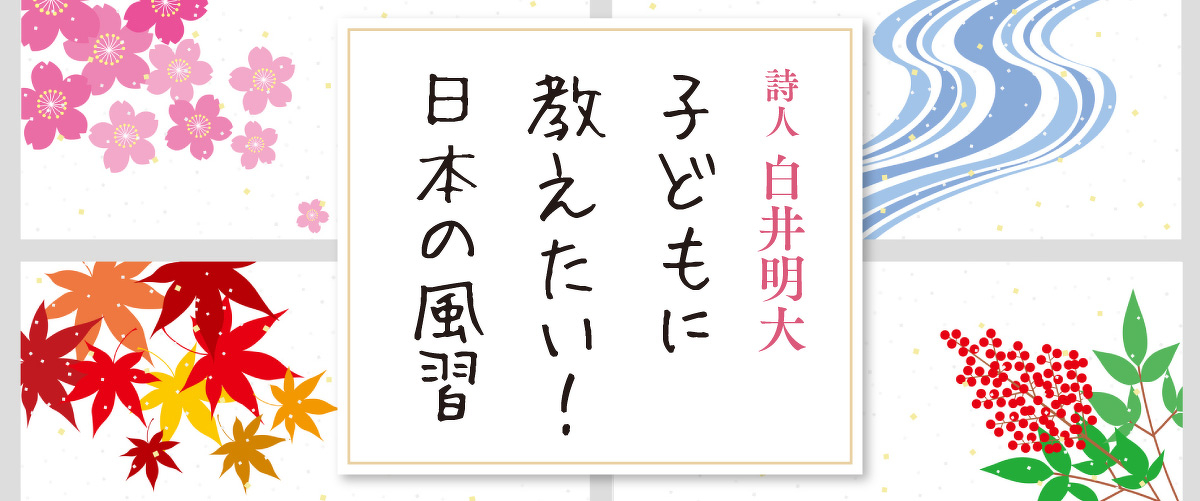

入梅
梅雨《つゆ》というのは気象現象なので、いつ梅雨入りするかは、その年のお天気しだいでまちまちです。昔は天気予報もありませんでしたから、その代わり、いついつ頃から梅雨になりそう、という目印の日が暦に記されていました。
暦の上で梅雨入りを知らせる目印の日を、入梅《にゅうばい》といいます。
入梅の日は年ごとに変わりますが、およそ六月十一日前後です。たとえば今年の入梅は、六月十日に訪れます。
入梅と農事暦《のうじれき》
昔は六月のこの時期に田植えをしていましたので、入梅の日は、苗を植えるタイミングを知る目安になっていました。そのように、農作業をするために役立つ暦のことを、農事暦といいます。入梅は、稲を育てるうえで大切な意味を持っていました。
ちなみに入梅のように、折々の節目の印になっている日を雑節《ざっせつ》といいます。雑節には、ほかにも五節句や彼岸、八十八夜、土用、節分などがあります。

梅雨はどうして梅雨というの?
梅雨のことを梅の雨と書くのは、この時期に梅の実が熟すからだといいます。
そんな梅雨の別名に、麦雨《ばくう》という雨の名前もあるそうです。麦の穂が実る頃に降る雨だから、麦雨(梅雨も、麦雨も、名前のつけ方が似てますね)。
せっかくたわわに実った麦穂が、収穫前に雨にぬれてはたいへんです。穂についたまま、種から芽が出て、せっかく実の中につまった栄養分のデンプンが減ってしまいます。
麦雨(梅雨)が降る前に麦を刈らなくちゃ、ということで、梅雨入りがいつなのかは気になるところ。やっぱり入梅という雑節は、昔の田畑仕事にとって、なくてはならないものだったと思います。

青梅雨《あおつゆ》
梅雨のことを、青梅雨ということもあります。「青」というと色のブルーを思い浮かべますが、昔は明るくも暗くもない漠然とした中間色を「青」といったそうです。しとしと降る雨の情景は、まさにそんな漠然とした「青」がぴったりでした。いまでは青梅雨というと、青葉の茂る頃の梅雨、といったニュアンスでしょうか。同じ言葉でも、時代によって意味が移りかわっていくのですね。
五月晴れ《さつきばれ》
梅雨にまつわる言葉で、時代によって意味が移り変わったものをもうひとつ。五月晴れ、という言葉を聞くと、いまでは初夏のさわやかに晴れた情景を思い浮かべるのではないでしょうか。ですが旧暦の五月は、新暦でいえば六月頃にあたります。もともと五月晴れというのは、久しぶりに青空が顔をのぞかせる、梅雨の晴れ間をいいました。
五月晴れは、もうすっかり初夏の青空としてなじんでいる言葉ですから、いまさら梅雨の晴れ間のことだと言われても、困ってしまいそうです。
さて、五月晴れ。初夏なのか、梅雨なのかによって、意味が大きく変わりますが、いまも昔も、晴れてすがすがしい気持ちに違いはなさそうです。

黒南風《くろはえ》・荒南風《あらはえ》・白南風《しろはえ》
梅雨のさなかのどよんと重たい空の下、南から吹いてくる風が、黒南風です。雨がつづくと、じめじめしてやだな、うっとうしいな、なんて思うこともありますが、そんな気分に、黒南風という言葉はぴったり合っている気がします。 梅雨時に風が強まって、吹き荒れることもありますが、そうなると風の名前が変わって、荒南風と呼ばれます。
黒南風に荒南風というと、いかにも重々しい印象ですが、梅雨の南風は三人兄弟でした。末っ子は、白南風(しらはえ、とも読みます)といいます。黒から白へとイメージが明るくなる白南風というのは、梅雨明けを告げる南風で、本格的な夏を運んでくる熱風といえます。
黒・荒・白の南風三兄弟が、いつ吹いてくるのか。まだかな、もうすぐかな、なんて梅雨の風を楽しんでみてはいかがでしょうか。
嘉祥《かじょう》の梅
六月十六日に採れた梅でつくった梅干しを、旅立ちの日に食べると、旅の危難を避けられるという言いならわしがあります。そんな旅のお守りのような梅を、嘉祥《かじょう》の梅といいます。

この日には、嘉祥喰《かじょうぐい》といって、和菓子や餅をいただくならわしもありました。一説によると、嘉祥元年(八四八年)に仁明《にんみょう》天皇が、無病息災を祈って十六の菓子や餅を供え、元号を嘉祥と改めたエピソードが由来とか。江戸時代には、幕府や宮中で家臣や公卿に菓子がふるまわれたそうです。庶民の間でも、十六文で十六個の餅を買って食べる風習があったそう。
季節の楽しみ
さて、いよいよ梅の実が旬となり、梅干しや梅酒、梅シロップなどを仕込む、梅しごとが楽しみな季節がやってきました。
梅雨のはじまる六月前半は、二十四節気では芒種《ぼうしゅ》(今年は六月五日〜二十日)にあたります。芒種とは、稲など穂の出る植物の種をまく頃という意味。つまりは田植えの季節のことです。
たしかに、昔はこの時期に田んぼに苗を植えていましたが、いまでは五月に田植えをしています。
だったら、いまの時代に、芒種ってどんな意味があるんだろう? というと、何か夢や目標、ひいては未来のために、あるいはちょっとした日々の喜びのために、自分に種をまく季節と考えてみてはどうでしょう。
その点、梅しごとが、まさにそうだと思うのです。がんばったおかげで、漬けておいた梅干しや梅シロップが完成すると、毎日の食卓に幸せが並ぶようになります。これもやっぱり自分への種まきではないでしょうか。
七十二候では六月半ばに、梅子黄なり《うめのみきなり》という季節がめぐってきます。まさに梅の実が熟して色づく頃。梅酒や梅シロップには、まだ熟す前の青梅を。梅干しや梅酢づくりには、熟してきた梅の実を。そしてとろりと甘く完熟した梅は、砂糖といっしょにことこと煮ると、おいしい梅ジャムができあがります。
参考文献:白井明大『日本の七十二候を楽しむ ─旧暦のある暮らし─ 増補新装版』(絵・有賀一広、KADOKAWA)、同『暮らしのならわし十二か月』(絵・有賀一広、飛鳥新社)、同『一日の言葉、一生の言葉 旧暦でめぐる美しい日本語』(草思社)
【プロフィール】
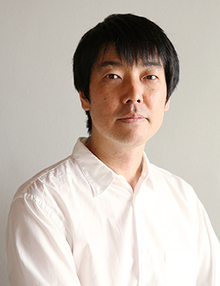
白井明大(しらい・あけひろ)
詩人。1970年生まれ。詩集に『心を縫う』(詩学社)、『生きようと生きるほうへ』(思潮社、第25回丸山豊記念現代詩賞)など。『日本の七十二候を楽しむ』(増補新装版、絵・有賀一広、KADOKAWA)が静かな旧暦ブームを呼んでベストセラーに。季節のうたを綴った絵本『えほん七十二候 はるなつあきふゆ めぐるぐる』(絵・くぼあやこ、講談社)や、春夏秋冬の童謡をたどる『歌声は贈りもの』(絵・辻恵子、歌・村松稔之、福音館書店)、詩画集『いまきみがきみであることを』(画・カシワイ、書肆侃々房)など著書多数。近著に、憲法の前文などを詩訳した『日本の憲法 最初の話』(KADOKAWA)、絵本『わたしは きめた 日本の憲法 最初の話』(絵・阿部海太、ほるぷ出版)




















