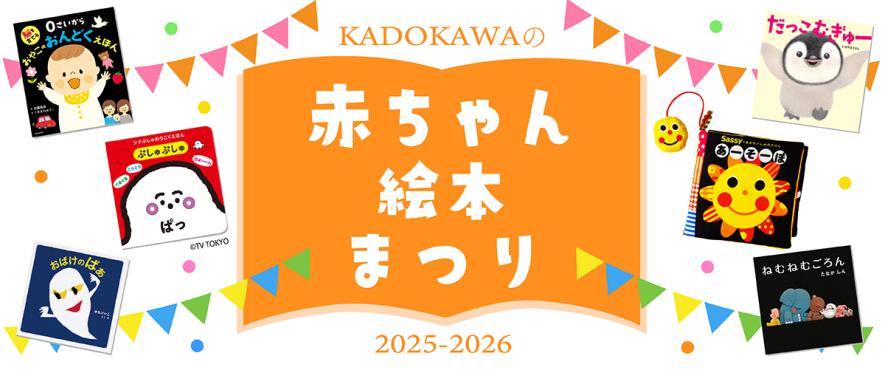これまで多数の脳科学や音読に関する本を手掛けてきた医師・脳科学者である加藤俊徳先生が、構想2年をかけた0歳向けの音読絵本が登場! 「言葉の発達に絶大な効果を発揮する」という、これまでなかった赤ちゃん向け音読絵本の制作秘話や活用法について、お話を伺いました。
- 【定価】
- 1,650円(本体1,500円+税)
- 【発売日】
- 【サイズ】
- B5変形判
- 【ISBN】
- 9784041164389
構想2年! 言葉の発達を改善できる0歳からの音読絵本
――今回なぜこの絵本をつくろうと考えたのでしょうか?
これまでも数多くの音読に関する本をつくってきましたが、以前から「0歳向け」をつくりたいと思っていました。なぜなら、僕自身が高校まで音読ができない「ひらがな音読困難症」だったからです。家族が多かったこともあって、絵本は買ってもらっていましたが、めくって眺めていただけで内容は全くわかっておらず、童話もほとんど知らずに育ちました。そんな僕が「どんな絵本だったら自分がひらがな音読困難症にならずに、本がスムーズに読めたのか」を想像してつくったのがこの『脳を育てる 0さいから おやこのおんどくえほん』です。
「絵本でありながら言葉が発達しないといけない」「勉強のための音読とは違う絵本とは」「親が赤ちゃんにできる役割とは」など、多方面から考慮し、構想は2年かかりました。その結果、小児科医として長年未熟児や言葉が遅れた子を数多く見てきた経験から、「赤ちゃんの言葉の発達の遅れを改善したり、言葉の発達が遅れないようにしたりするのに有効な音読の絵本」となりました。
僕自身は20歳の頃に独学で音読のトレーニングをして克服したのですが、幼少期にこの本があったらなと思っています。
――この絵本の特長を教えてください。
この本は、左ページは大人が読み、右ページは赤ちゃんといっしょに声を出すようにつくりました。左ページでは、大人の発する言葉を聴くことで聴く力、絵を見ることで見る力が鍛えられ、右ページでは口を動かす力、声を出す力が鍛えられます。また、この本を活用することで親子のコミュニケーションが豊かになり、感性を育みます。そして、成長に伴ってこの本を繰り返し使うことで、記憶力や理解力、思考力も鍛えられると考えています。言葉が話せるようになったら、左ページも子ども自身が音読することで長く使えますよ。


音読は脳の集音機能を高め、海馬を刺激する効果がある
――音読が脳に与える効果を教えてください。
音読が脳に与える一番の効果は、聴音能力を高めて、海馬を刺激することです。言葉を習得するためにまず必要なのは「言葉を聞くこと」ですが、赤ちゃんは聴音能力が低いので、耳元で話してもらわないと言葉がよく聞きとれません。文字が読めない赤ちゃんは、面白そうな言葉が耳元で繰り返されることで、聴音能力を高めることができるのです。音は目に見えませんが、親御さんが乳児期にどれだけ顔を近づけて耳元で声をかけたかで、後の言語習得力や情緒の安定、愛着関係にも影響するのではと考えています。
――言葉の遅れが音読で改善できるって本当ですか?
これは本当です。脳に問題がなくても、言葉が遅い子は左の海馬の発達が遅れていることが多いのですが、そういう子は聴音能力が低いのです。聴音能力が育っていないと、小学生になってもすらすらと文字を読めないことがあります。ところが、私のクリニックで言葉が遅い子たちに音読を実践してもらうと、1~2ヶ月で驚くほど言葉が出てきたという例を毎日のように見てきました。この方法は、革命だと思います。
――なぜ音読で海馬(音の記憶)が刺激されるのでしょうか?
脳の構造的には、0~3歳までは語彙力はそれほど増えない時期だとされています。なぜなら脳の側頭葉の内側は、音を聞く(上側頭葉・1歳頃)→言葉を理解する(中側頭葉・2歳頃)→言葉を記憶する(下側頭葉・3歳頃)と、それぞれの部分が順番に連携しながら発達していくためです。
加えて、赤ちゃんは1歳前後から歩きだしますが、まだしゃべれないのは、立って歩くという身体の発達が話すことよりも先だからです。人間の体は、体幹→手→口という順番で発達しやすいので、言葉を話すには、泣いて腹筋を鍛え、ハイハイやよちよち歩きで運動機能を発達させることが必要になってきます。
つまり、何が言いたいかと言うと、脳の構造的に、言葉の習得には、0~3歳までは音読や遊びで運動しながら、親子が接して楽しい状況をつくることが何よりも大事だということ。一般的にボキャブラリーが増えていくのは4歳を過ぎてからだということも覚えておくとよいでしょう。
ゆっくり話すお母さんの子は賢い子が多い!? 赤ちゃんとの音読で注意したい4つのポイント
――具体的に、どのように音読すればいいか、ポイントを教えてください。
その1 助詞を区別して読む
日本では小学校で助詞を習いますが、言語の習得の面で言うと、それでは遅いのです。なぜなら、日本語は助詞を正しく使えないと、「私とあなた」「私はあなたに」のように意味が変わってしまう言語だからです。反対に音として助詞の区別できるようになっていれば、ほとんどの会話が理解でき、言葉が伝わる話し方になるのです。ですから、「いぬ『が』あるいているよ」「おはな『が』さいているね」など、助詞を強調した音読を心がけ、助詞が区別できる脳の仕組みを0歳からつくり上げていきましょう。自分で助詞を強調して音読できるようになると、小学生以降、どんどん本を読めるようになります。
その2 ゆっくり読む
歴代のアメリカ大統領や天皇の演説を思い出してみてください。言葉を区切ってゆっくり話しますよね。そうすることで、脳の海馬の番地をより刺激し、聴く方も理解しながら記憶する時間が長く与えられるのです。よく、「ゆっくり話すお母さんの子は賢い子が多い」と言われるのも同じ理由です。ぜひ「くるまが~、はしっているよ~、ぶ~~~ぶ~~」と、ゆっくり読んでみましょう。
その3 明るいところで見る
生まれて間もない赤ちゃんはまだ目が見えていませんが、泣くことで目に光がさし、ドーパミンやセロトニンの数値が上がってきて、絵本を「見える」から「見たい」という意欲につながります。音読は明るいところでするのをおすすめします。
その4 お腹の中にいるときから始めてOK
私は小児科医歴38年で長年未熟児医療にも携わってきましたが、「お腹にいるときから0歳」という考え方を推奨しています。なぜなら、生まれる1ヶ月前から脳幹の音を感知する部位が働き、さらに大脳の聴覚の枝が伸びてくるので、音としては聞こえはじめている状態だからです。親御さんが生まれる1~2ヵ月前からこの本を音読しておくと、生まれた赤ちゃんにも親近感が増しますし、親御さんにとっても音読や赤ちゃんとのコミュニケーションの練習になるはずです。お母さんだけでなく、ぜひお父さんにも、親になる準備運動としてこの本を活用してもらえたら嬉しいです。
音読は大人の脳トレにも効果的!
――音読は赤ちゃん以外にも効果があるのでしょうか?
音読が与える影響は子どもだけではありません。年をとるにつれ耳が遠くなるのは、人に話す機会が減って、だんだん自分の声が小さくなっていくからです。ゆっくりと声に出して音読することで、衰えがちな口腔筋が鍛えられ、誤嚥も防ぐことができます。さらに、最近の研究で「大人は聴覚が弱くなると認知症を発症する可能性がおよそ7%も増える」ということもわかってきました。音読は口の筋トレはもちろん脳トレにも効果がありますから、おじいちゃんおばあちゃんにこの本を使ってお孫さんに音読をしてもらうのもおすすめです。
取材・文 加藤朋美
著者情報
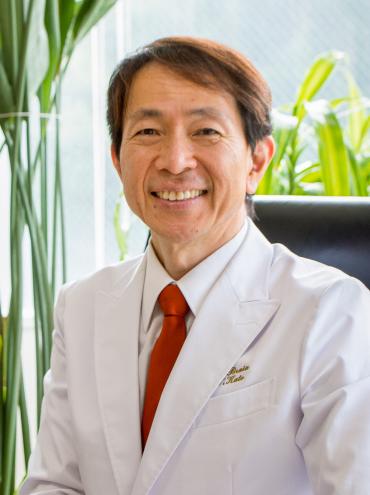
加藤俊徳
脳内科医、小児科専門医、医学博士。加藤プラチナクリニック院長。株式会社脳の学校代表。昭和医科大学客員教授。脳科学・MRI脳画像診断の専門家。脳番地トレーニング、助詞強調おんどく法の提唱者。加藤プラチナクリニックにて、独自開発した加藤式MRI脳画像診断法による脳個性診断を行っている。小児から超高齢者まで1万人以上を診断·治療。
『頭がよくなる! 寝るまえ1分おんどく366日』『頭がよくなる! はじめての寝るまえ1分おんどく』(ともに西東社)、「1話5分 おんどく伝記&名作」シリーズ(世界文化社)など音読本のベストセラー多数。
書籍情報
- 【定価】
- 1,650円(本体1,500円+税)
- 【発売日】
- 【サイズ】
- B5変形判
- 【ISBN】
- 9784041164389
\注目の赤ちゃん絵本を紹介中!/