
100年以上前に発表された作品から、近年刊行されたばかりの新刊まで。5月28日に発売された『けんごの小説紹介 読書の沼に引きずり込む88冊』は「新しい物語との出会い」を求める方に向けて、小説紹介クリエイターとして活躍中のけんごさんが、国内外の多種多様な88冊の小説を紹介するという、画期的な一冊です。同書を書き下ろしたけんごさんは、読書とは無縁の少年時代を過ごしてきたからこそ、ご自身と同じ立場の若者たちに読書の素晴らしさを伝えたいと、さまざまな活動を続けています。そんなけんごさんに、子どもの頃の話などを聞いてみました。
【プロフィール】
けんご
小説紹介クリエイター。SNSで小説の紹介動画を投稿。短尺で的確に小説の魅力を伝える紹介動画は、幅広い年齢層から絶大な支持を得る。紹介動画の投稿後に、たちまち重版した書籍は多数。SNSの総フォロワー数は90万人以上。大の猫好きで、現在は妻と猫2匹の4人暮らし。
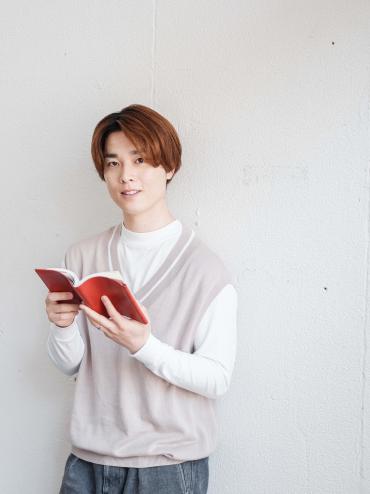
子ども時代から大学生までは、野球漬けの日々
我が家は、いわゆる野球一家で、小さい頃からずっと野球をしていました。小学3年生の時に本格的に始めてから、大学4年生まで、ずっと野球に打ちこんでいましたね。僕には歳の離れた兄が二人いて、長男は10歳、次男は8歳年上で、次男は今も社会人野球の選手として活躍しているのですが、その次男の背中をずっと見ながら野球をしていました。「お兄ちゃんと同じフィールドで野球がしたい」という夢を叶えるため、社会人野球でプレーできるよう頑張ろう、と小さな頃からずっと思っていました。

※写真はイメージです
僕自身は記憶にないのですが、野球を始める前の3、4歳の頃は、電車に夢中になっていたようです。祖母の家の近くに鉄道の線路があって、僕がほぼ一日中、外で電車をみていて、祖母がそれにつきあってくれていた、といったことがあったそうです。また、これもまったく覚えていないのですが、ものすごい数の鉄道路線の名前を空で言えたらしく、両親は「当時の様子を動画に収めておけば、『天才少年』としてメディアで注目を集めたんじゃないか」と今でも言っていたりしますね(笑)。
目立つことが大好きだった中学時代
小学生の頃は地元の少年野球チーム、中学時代はクラブチーム、高校は野球部と、野球が中心の日々をずっと過ごしていました。高校では、テストで赤点を取ると部活に参加できないというルールがあったので、結構真面目に勉強していましたが、小・中学生の頃は、本当に一切勉強していなかったですね。なので、読書は、学校での朝読書の時間以外には、まったくしていませんでしたし、読んでいたとしても、兄たちが集めているマンガ本くらいでした。きっと、小・中学校でお世話になった先生方が、今、僕が小説紹介クリエイターとして、本に携わる仕事をしていると知ったら、すごく驚かれると思います。
小学生時代に所属していた地域の少年野球チームは、強豪とは言い難いチームでした。ですが、僕が小学6年生でキャプテンを務めた年は、いろいろな大会に出場して、銅メダルを獲得することができたのですが、その時は本当にうれしかったですね。
目立つことが好きだった僕は、九州地区最大級のマンモス校と呼ばれる中学校に通っていた頃、積極的に人前に立っていました。体育祭でブロック長を務めたりと、何かとみんなの前に立って、いろいろな人と仲良くしていた記憶があります。率先して大勢の前で意見を言ったりということは、かなり積極的にやっていたので、宿題もしないし成績もあまり良くない生徒でしたが、先生方には可愛がっていただいた印象がありますね。
「コスパのいい趣味」として選んだ読書が運命を変えた
野球推薦で大学進学が決まり、福岡から上京しました。高校時代にくらべ、野球の練習時間に余裕ができたので、「お金を使わずにできる趣味が欲しい」と思い立ちました。釣りなども考えましたが、釣り具を用意する金銭的な余裕もない。そんな中で、書店へと足を運びました。僕が最初に手にしたのは、東野圭吾さんの小説『白夜行』で、手に取った理由は表紙のインパクトもありますが、シンプルに分厚くて。「この厚さだったら、長い時間つぶせそう」という単純なものでした。その後、一ヶ月くらいかけてじっくりと読み終えた後は、こういった長編小説をちゃんと読み切ったという感動が大きかった記憶がありますね。その後、読書の楽しさを知り、いろいろな本を読むうちに、映像制作の仕事の延長線上で、小説紹介クリエイターとして活動を始めました。
今、振り返っても、その日、書店を訪れて『白夜行』を手にしたことは運命だったと思います。その日、「本を読もう」と思って、実際に行動していなければ現在の僕はないと思っています。

※写真はイメージです
紹介した88冊を通して、読書の楽しさを伝えたい
5月に発売となった『けんごの小説紹介 読書の沼に引きずり込む88冊』は、初めて読書する子どもたちや読書体験があまりない子どもたちに向けて、小説を選びました。この本で紹介した物語をきっかけに、さまざまなジャンルの作品を楽しんで欲しいな、という思いがあったので。たとえば、ホラー小説と一言でいっても、心霊体験がテーマのホラーがあれば、人間の恐ろしさを描いた作品や、「イヤミス」と表現される、後味の悪さが特徴のミステリーもあったりするので、ジャンルでひとくくりにせず、たくさんの種類の小説を紹介しました。
子どもの頃は、まったくといって良いほど本を読まなかった僕ですが、今では小説紹介クリエイターとしての仕事をしながら、毎月20冊ほどの本を読んでいます。僕が大学生になってから読書を始められた理由は、確実に読書に対してのトラウマがなかったからとは思っています。もし、僕が幼少期から両親にものすごく読書を強要されたりしていたら、きっとそれはトラウマとなって、趣味を作りたいって思った時に読書という選択肢が生まれなかったんじゃないかなと思うんですけど、幸いなことに僕の両親は、読書を強要することは一切なかったので、それは大きかったかなと思います。僕が将来、親となり、子供に本を読んでもらいたいなと思った時は、「読書しなさい」と押しつけるのではなく、一緒に楽しんだり、僕が本を読んでいる姿を見せてあげることが、すごく大切になるんじゃないかなとは思っていますね。
自分のペースで自分が好きな時間に、自分が好きな場所でできる。それが、読書という趣味の一番の魅力かなと思っています。 何千年も前に書かれた物語でも、本は読まれるのを待っていてくれますからね。そして、これから読書感想文を書かなければいけない小中学生には、森絵都さんの『カラフル』や湯本香樹実さんの『夏の庭―The Friends』をおすすめしたいです。


























