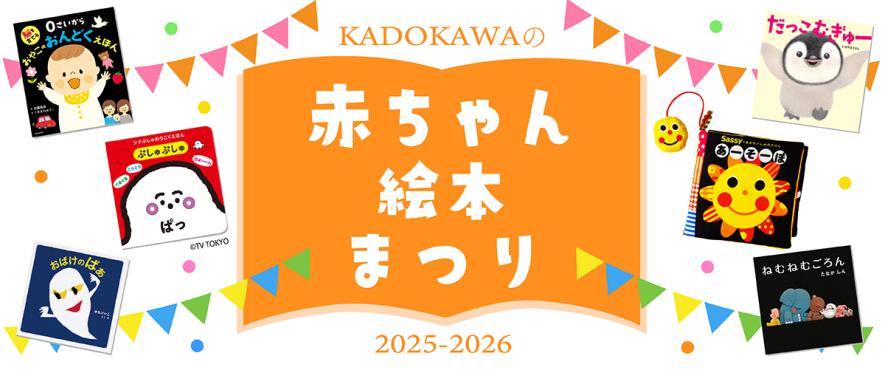【あそびえほん】どうやってあそぶの? 最新の発達認知科学研究から生まれた年齢別絵本監修者8名による特別インタビュー【第2回・鹿子木康弘先生】

赤ちゃんは生まれながらにして「数」や「コミュニケーション」に関する知識をもっています。
発達認知科学から生まれた、「あそび」を通じて赤ちゃんが生まれもつ知識を伸ばす絵本——それが年齢別の「あそびえほん」シリーズです。
発達認知科学研究者8名が、最先端の研究成果を結集して作り上げた本シリーズ。
今回は、「赤ちゃんの他者理解、道徳性」について研究されている鹿子木康弘先生に、「赤ちゃんが生まれながらに持っている道徳性・正義感」や、絵本の制作についてお聞きしました。

―鹿子木先生は、乳幼児の発達認知科学の研究者でいらっしゃいますが、どのようなご研究をされているのでしょうか?
簡単に言うと、「赤ちゃんがどのようなことを考えることができるのか」を、科学的な方法を用いて研究しています。
具体的な方法としては、アニメーションや映像を見ているときの、赤ちゃんの注視行動(どこを見つめているか)や実際の行動を計測したり、親子のやり取りにおける視線や行動を計測したりしています。
僕は、赤ちゃんが生まれながらにして“正義感”や“道徳性”、“向社会性(他者に利益をもたらす自発的な行動)”を備えているのではないか、と考えています。
2022年には8か月の赤ちゃんを対象にして、赤ちゃんが「悪いものを罰するかどうか」の検証を行いました。
▼「8ヵ月の乳児も“悪者”を罰する 前言語期乳児の道徳的行動を解明」
https://resou.osaka-u.ac.jp/ja/research/2022/20220610_1
※外部サイトへ移動します。
―「あそびえほん」シリーズでは、0さい「やさしいね」、1さい「どうしたの?」、2さい 「ありがとう」の内容選定・監修を担当されました。研究者の目線でこだわった部分や、具体的なポイントは?

「ふーっ」と息を吹きかけてあげることで助ける
赤ちゃんは、生後6か月くらいで善悪の判断ができ、「他者を邪魔する悪い者より、他者を助ける善い者を好む」ことが研究からわかっています。「やさしいね」の項目では、0歳の子も理解しやすい「風船が葉っぱに引っかかって通れない」という状況を場面として設定し、読者が「ふーっ」と息を吹きかけてあげることで助けるという、思いやり行動を引き出す内容にしました。

0歳は手足の動きが十分に発達していないので、他者を助けるために自ら動くことはまだ難しいです。そこで、赤ちゃんでも行いやすい「息を吹きかける」という行動を採用しました。絵本を読む際には、保護者が「ふーっ」と息を吹きかけて風船を助ける行動を示し、子どもがそれを真似することで子ども自身の思いやり行動を引き出すことができるのではないかと思います。
「ボタンを押す」形で助ける
1歳になると、他人が困っているときに助けてあげるような、簡単な援助行動を示すようになります。「どうしたの?」の項目は、バスのボタンに手が届かず困っているネズミさんを、読者の子どもが「ボタンを押す」形で絵本の中で助ける、という内容になっています。「ボタンを押す」という行動は10か月くらいからできるようになるので、そうした発達段階を考慮し、場面を設定しました。
生まれながらにして「人を助けたい」という気持ちを持っていても、0歳児では行動に移すことが難しいですが、1歳児は体の発達とともにいろいろな行動ができるようになります。絵本を通じて、その思いやり行動をさらに発展させていってほしいと思います。

「他者が落としたものを拾う」という形で助ける
2歳「ありがとう」は、1歳よりも明確な援助行動として、「他者が落としたものを拾う」という形でダイレクトに相手を助けるお話にしました。
助けることで感謝される、ハイタッチをする。そういった「助けるもの・助けられるもの」の相互の関係性が理解できるようになることも重要です。この項目には、そうしたエッセンスも散りばめました。
もちろん、「感謝されるために、向社会的行動(他者に利益や恩恵を与える行動)をとる」というわけではありません。やはり、他者を助けたいという気持ち・能力がもともと備わっていると考える方が正しいです。

成長とともに「向社会行動」も変化していく
ただ、だんだん子どもが大きくなっていくと、人を助けるという行動がより選択的になっていきます。
例えば、発達初期の1-2歳は意地悪な人でも困っていれば助けてあげます。でも、子どもは認知能力が発達する中で、「この人はちょっと近寄りがたいな、いじわるだな」と思うと向社会的行動を示さなくなります。大人でもそうですよね。3歳くらいになるとだんだんとそうした認識ができて、行動が戦略的になっていきます。そして、「悪いことをしている人は助けないけれど、いい人は助けてあげる」というように、選択的な行動が見られるようになります。助ける対象の道徳的な特性が向社会的行動に影響し、援助行動の示し方がより複雑になっていきます。
正義感に関連することとして、悪いものを罰したい、という気持ちは0歳児からあります。自分がやられたからやり返すというのではなく、「第三者罰」という自分が危害を加えられていなくとも、なお悪いものを罰しようとする正義の行動です。これは人間特有の行動で、チンパンジーだと自分がやられたからやり返すことはしますが、自分に危害が加えられていなければ干渉しないんです。
―「赤ちゃんは生まれながらに正義感を持つ」という研究は非常に興味深いのですが、そうした情報を保護者が知っていることには、どんなメリットがありますか?
例えば、「自分の子どもが正義感などの善性・良い特性をもともと持っている」と考えながら教育する場合と、「赤ちゃんは身勝手で言うことをきかない、何もわからず非道徳的である」と考えて教育する場合では、子どもに対する接し方は変わってきますよね。
ですから、赤ちゃんが生まれながらに持っているコアな部分を知ることは、保護者の接し方においてポジティブに働くのではないかと思います。
そして、子どもが生まれながらにして持っている善性をさらに伸ばしていくためには、後天的な学習も不可欠です。この絵本シリーズを通し、さまざまな状況における適切な援助方法を身に着けていってほしいです。
―この絵本シリーズで「赤ちゃんが夢中になる」ポイントや、子育てでどう使ってほしいかを教えてください。
夢中になるポイントというと、やはり赤ちゃん自身が「参加できる」ところだと思います。子どもが参加しやすい、没入しやすいシチュエーションを意識して作っているので、集中しやすいのではないかと思います。
この絵本シリーズを読むときは、親自身の感情をこめて文章を読み上げつつ、お子さんの顔を見ながら「どういう感情状態にあるか」を観察してみてください。こうした読み方をすることで、子どもの感情理解が促進されて他者の気持ちの理解につながっていく、ということが科学的にも実証されています。
「うれしい、楽しい、悲しい」のような心の状態に関する言葉をよく使う親の子どもは、他者への理解が深まるということも言われています。書かれたテキストを読み上げるだけでなく、「サンタさん、こまっちゃったみたいだね」などと呼びかけてみてください。
子どもの発達認知にもとづいた絵本は、これまであまりなかったと思います。この「あそびえほん」シリーズをきっかけに、赤ちゃんは受け身の存在ではなく、外界に自ら働きかけ、能動的にいろいろなものを学習していく存在であることを、保護者の皆さんに知ってもらえたらいいなと思います。
また、繰り返しになりますが、「子どもは向社会的な存在として生まれ、人に対して優しくする傾向があり、道徳的特性を持っている存在なのだ」ということを伝えたいですね。
―最後に、鹿子木先生ご自身も子育てをされていらっしゃいますが、そうした中で思ったことや、それをもとに、保護者の方へメッセージがありましたら教えてください。
僕は専門家なので、「この月齢だと大体こんなことができる」という知識があります。ですので、自分が子どもを育てる際に、子どもが通常の発達曲線のどこにいるのかがすごく気になりました。しかし、子育てをする中で、発達段階にマッチしない部分があっても、意外とそれは気にしなくていい、という結論に至りました。
なぜかというと、研究でわかっている子どもの発達の知見というのは、実験など特殊な状況下で得られた結果だからです。普段の生活では研究結果に沿った発達状況が見られないことの方が当たり前なので、過度に心配する必要はないと思います。
赤ちゃんは自制もできないし、身勝手な行動をとる側面もあります。必ずしも子どもは善性100パーセントでできているわけではないですが、いろんな側面があるなかで、向社会的な面もある、ということを保護者の皆さんにはお伝えしたいです。
これまでは「道徳的な考えや行動は、後天的に、教育でゼロから教えるもの」という考えが主流でしたが、子どもたちには生まれながらに持っている道徳性があり、教育でもそこに着目して伸ばしていくことが求められると思います。
子どもの感情状態をしっかりと観察しながら、お子さんの優しい側面に着目して、この絵本を読んでいってほしいと思います。
プロフィール
鹿子木 康弘(かなこぎ やすひろ)
1977年大阪府生まれ。大阪大学大学院人間科学研究科教授。乳幼児の認知・社会性の発達をテーマに、実証的な研究に従事している。著書に『社会性の発達心理学』(ナカニシヤ出版,分担執筆)や『社会的認知の発達科学』(新曜社,分担執筆)など多数。