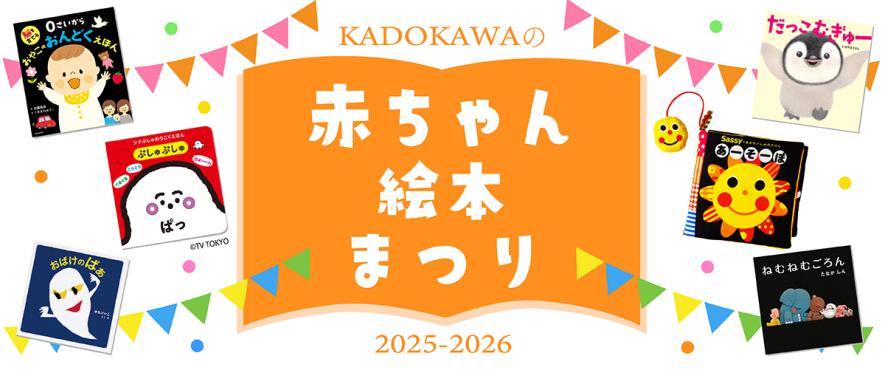【あそびえほん】どうやってあそぶの? 最新の発達認知科学研究から生まれた年齢別絵本監修者8名による特別インタビュー【第1回・開一夫先生】

赤ちゃんは生まれながらにして「数」や「コミュニケーション」に関する知識をもっています。
発達認知科学から生まれた、「あそび」を通じて赤ちゃんが生まれもつ知識を伸ばす絵本——それが年齢別の「あそびえほん」シリーズです。
発達認知科学研究者8名が、最先端の研究成果を結集して作り上げた本シリーズ。
そのこだわり、楽しみ方、込められた想いを、
総監修を務めた赤ちゃんラボ5.0の開一夫先生にお聞きしました。
■ 発達認知科学からうまれた子どもの知識を伸ばす絵本

―「あそびえほん」シリーズの総監修として、開先生が特にこだわった部分を教えてください。
私は発達認知科学の研究者として、赤ちゃんの研究を続けています。実は、子どもたちには生まれながらにして持っている「知識」があるんです。息をしたり、ご飯を食べたりという生存の基本だけでなく、世界を理解し、かかわっていくための基礎となる知識です。発達認知科学では、これを"コアナレッジ"と呼んでいます。
具体的には、たとえば「数」に関する知識、周りの人々とコミュニケーションをとるために必要な知識、さらに物理的な世界で生きていくうえで必須となる、「空間」や「物体」に関する知識などです。赤ちゃんは、これらの知識を持って生まれてくるんですね。
こうした知識が成長とともにどう変化していくか——それを解明することが発達認知科学の中心的な研究課題です。乳幼児期にこれらの知識がどう変わっていくかを考えて作りました。"生まれながらの知識"のうち特に興味深い5つの分野「いきもの」「もの」「かず・かたち」「コミュニケーション」「空間」を意識して章立てを行ったのがこだわりです。

"発達科学の研究者たちが作った"ということも強みだと思っています。このシリーズには、発達科学の最先端にいる8名の研究者が参加しています。赤ちゃん研究の中でも、社会的認知の専門家や言語発達の専門家など、多様な研究者が集まっています。私自身は「数の認知」の立場でこのシリーズにかかわっています。
面白いのは、みなさん子育てや子どもと関わる立場でもあること。もちろん実験と実際の子育てはずいぶん違った部分があると思いますが(笑)。子育てや子どもに関心を持っている研究者たちが作った——それが強みです。
■ 子どもが気づいてくれる 遊び心をしのばせる
―絵本の細部やデザインへのこだわりは?
たとえば、このシリーズにはオリジナルキャラクター「うーにー」がいるんですが、実は全ページの隅っこに小さく隠れていて、パラパラめくるとアニメーションのように動いて見えるんですよ。大人は気づかないくらい小さいんですが、子どもが「あれ?」って気づいてくれるとうれしいですよね。

さまざまなジャンルの内容が数ページずつ入った構成なので、物語絵本のような流れは作りにくい。でも、全体に統一感は持たせたかったんです。
こういう遊び心、大事だと思うんです。赤ちゃん本人が持ってめくれる大きさにもなっていますし、どのように見せたら赤ちゃんがじっと見てくれて、楽しいか——そういったことを考えながら作りました。
■「赤ちゃんにも分かっていることがある」からこそできる、楽しい体験
―開先生が直接監修された「かず・かたち」について、詳しく教えてください。
このシリーズでは0歳から「かず・かたち」のジャンルを扱っているのが特徴的だと思います。ほかの本で、0歳向けの数の本はあまり見たことがないでしょう。

▲0さい「りんごは なんこ?」より抜粋
赤ちゃんを対象としたこれまでの研究で、0歳でも「数」に関して生まれ持ったナレッジ(知見)があることがわかっています。ちょっと考えれば当然で、「数」について小学生になって学校で習ったら突然わかる、というわけではないですよね。生まれ持っての知識があって、時間をかけて大人と同じような「数」の概念が獲得されていくわけです。
一緒に読むお母さん・お父さんには、「赤ちゃんにも分かっていることがある」ということを念頭において読んでほしいですね。「数なんてうちの子にはまだ早い」なんて思わないで、数に触れていってもらえたら嬉しいです。
また、私のパートでは、0歳児にかたちの名前を覚えさせようとはしていません。しかし、「まる」「さんかく」「しかく」と指差しながら読むことで、赤ちゃんは「かたち」に対応する「音」があることを自然に理解していきます。
工夫したのは、しかけです。エルヴェ・テュレさんの絵本『まるまるまるのほん』に大きく触発されました。「読み手の行為が、ページをめくると結果として現れる」——このしかけを、私なりに数とかたち、音の学習に応用したのです。自分がやったことの結果が目の前に現れる。赤ちゃんにとっては、とても楽しい体験です。
■ 読み聞かせとは、親子で同じ経験をシェアすること

―読み聞かせのコツはありますか?
そうですね。たとえば、保護者の方がまず、数を声に出して数えてあげること。絵の中の数と言葉の数詞が関連する点で理想的ですね。そうやって耳と目と行為から総合的に情報を得るのも大切な経験だと思います。
シリーズ全体の読み聞かせに関しても、耳から聞くだけじゃなくて目で文字を見ることも学びになりますね。絵本を開いて、「お母さんはこれ(文字)を見て読んでいるな。そうか、これは音に関連するものなんだ」と、赤ちゃんは自然に気づきます。
読み聞かせで文字を学習させる必要はありません。「文字というものがある」ことを、なんとなく感じてもらえればいい。0歳からの読み聞かせには、そこに大きな意味があるんです。
―「赤ちゃんがじっと見る絵本」というコンセプトについて教えてください。
赤ちゃんの「じっと見る」は、最高の反応なんです。興味がなければ一瞬で視線をそらしますが、気に入ったものは見続ける。赤ちゃんに「じっと見てもらう」ことは、実際にやろうと思ってできることではありません。そう簡単ではないですよね。ただ、そういう絵本を目指すか目指さないかでは結構大きな違いがあると思います。
親子で絵本を見ることで、同じものを同時に見て、同じ体験を共有できます。それに向かって何かを語り掛けることで、赤ちゃんが反応する機会が生まれます。そのうち「あ、このページが好きなんだ」「ここで必ず笑うな」という発見が出てきます。親子で同じ経験をシェアする——それが子どもの知識を育てるうえで、とても重要なのだと思います。
1、2歳になれば笑ったり、自分でめくったり、反応がわかりやすくなりますが、0歳でも楽しいものにはちゃんと反応します。「0歳児に絵本を見せても意味がない」と思う人もいるかもしれません。ですが、0歳児でも興味のあるものは、やはり視線がそちらにいくし、6、7か月になると、本当によく見ますよ。
いろんな絵本を試して、お子さんが特に反応するページを見つける——それ自体が、素敵な親子のコミュニケーションです。
■ データの蓄積で 育児にプラスの循環を
―「赤ちゃんラボ5.0」について聞かせてください。どのような取り組みをされているんですか?
赤ちゃんラボ5.0では、新しい考え方で、赤ちゃんに関するさまざまな研究を進めています。
従来、研究データは研究者のものでした。でも私たちは、データの主役は赤ちゃんとご家族だと考えているんです。だから、研究で得られた情報を、参加してくださったご家族にお返しする仕組みを作っています。
絵本についても同じです。「この絵本が好きな子は、次にこの絵本も気に入る可能性が高い」といったデータを出版界全体で共有できれば、もっと良い絵本が生まれ、育児がもっと楽しくなる。
このラボで蓄積したデータをユーザー主体にすることで、さまざまな垣根をとりはらっていきたいのです。そうして、社会全体の育児をレベルアップさせたい。それがお父さんお母さんの安心感につながる——そんな循環を目指しています。
―この絵本への想いを聞かせてください。
「こんな楽しみ方を見つけました!」「こうやって読んだらこんないいことがあった!」——そんな声が聞けたら、本当にうれしいです。
以前作った『もいもい』という絵本では、カリフォルニアの研究者から「息子がきみの本をずっと持ち歩いている」と動画が添付されたメールをもらいました。とってもうれしかったですよ。
そんな風に、子どもたちの毎日に寄り添う絵本になってほしい。親子の大切な時間を、もっと豊かにする絵本になってほしい。それが私たちの願いです。
● 赤ちゃんラボ5.0の詳細はこちら → https://aka-lab.jp/
プロフィール
開一夫(ひらき かずお)
1963年富山県生まれ。東京大学大学院総合文化研究科広域システム科学系教授。乳幼児の心理や行動、脳の発達過程について科学的にアプローチに基づく「赤ちゃん学」を専門とし、赤ちゃんラボ5.0を運営。著書に、『赤ちゃんの不思議』、『日曜ピアジェ:赤ちゃん学のすすめ』(岩波書店)、絵本に『もいもい』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)など多数。乳幼児向けTV番組の監修として「シナぷしゅ」など、多方面で活動。