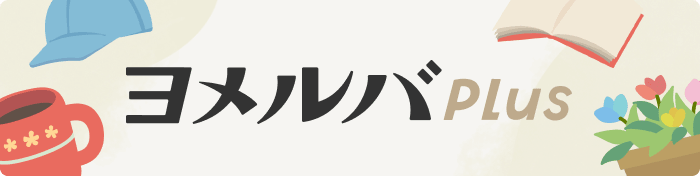4
「柿沼のやろう、とうとうこなかったじゃんか」
安永は、英治にはっきりと非難の眼差しを向けた。まるで、おまえ責任取れよと言っているみたいなので、つい、目をそらしてしまった。
「あいつは、裏切るような奴じゃないんだけどな」
知らずに声が小さくなる。柿沼直樹の家は産婦人科の病院をやっている。英治はそこで生まれたのだが、同じ日に直樹も生まれた。
誕生日がいっしょだというせいもあって、直樹とは幼稚園以来の親友である。将来医者になることを運命づけられている直樹は、小さいときから塾や家庭教師で勉強したので、成績は英治よりはるかにいい。
解放区には、おそらく参加しないと思ったのに、一も二もなく賛成した。あんまり張り切り過ぎるので、英治の方が心配になってきたくらいだ。その柿沼が……。
「じゃ、どうしてこねえんだ?」
「それは……」
そんなこと、英治にも答えようがない。
「もしかしてあいつ、親たちにチクっていねえかな」
「それは絶対にない。信じてくれよ」
英治は、必死になって柿沼をかばった。みんなの顔がろうそくの炎に揺れて、なんだか別人になったみたいに意地わるく見える。
「まあいいさ。こない奴はしかたねえ。それより、もうそろそろ八時半だろう。橋口純子から連絡がある時間だ。屋上に上がろうぜ」
相原が助け船を出してくれたので、英治はやれやれと思った。
相原はろうそくの火を三本とも吹き消した。部屋の中が真っ暗になって、何も見えなくなった。一分、二分。目が闇になれてくると、みんなの姿がぼんやりと見えはじめた。しかし、顔はわからないので、なんだか変な気持ちだ。
「足もとに気をつけて、ゆっくり歩け」
相原の声がしたかと思うと、肩に大型のスポーツバッグをひっかけて、そこだけ切り取ったように明るい、窓に向かって歩き出した。英治はすぐあとにつづいた。
「懐中電灯をつかえばいいじゃんか?」
だれかが言った。
「だめだ。闇(やみ)になれるんだよ。懐中電灯をつかうのは、どうしても必要なときだけだ」
窓際まで行った相原は、手さぐりでドアーをあけた。
「ここは非常口だ。ここから非常階段で屋上まで上るけれど、急だから一人ずつゆっくりこいよ」
英治は、相原につづいて外へ出た。外の方が生暖かい。このビルは四階で、いまいる事務室は二階にあるので、下へ降りる非常階段は傾斜(けいしゃ)が急になっている。
空は街の明かりを反映してか意外に明るい。非常階段に足を乗せると、きしんだ音を立てた。
「痛えッ」
うしろでだれかの悲鳴がした。
「どうした?」
相原が聞いた。
「椅子をひっかけてころんじゃったんだよ」
「だから気をつけろと言っただろう。これからは、何があっても大きい声を出すなよ。外に聞こえるとヤバいからな」
相原は、早いスピードで上って行く。みる間に三階の踊り場を通りすぎた。四階の踊り場までやってくると、立ち止まって下を見おろした。英治もそれにならった。
みんな黙々として上ってくる。まるで樹(き)の幹を登る蟻(あり)の列のようだ。
屋上は、バレーボールができそうな広さだった。周囲は高さが一メートルくらいの鉄柵になっている。
両隣は工場で、東側にK駅があり、繁華街になっている。ここからだと、一キロ以上あるはずなのに、光の海がすぐ近くに見える。
南側は隅田川があるはずなのだが、隣の工場の屋根が、すっかりおおいかくしてしまっている。
西側も工場が立ち並んでいるが、その建物の間から、隅田川の川面がわずかに光っている。
北側にまわった。ここからは荒川の河川敷が一望に見おろせる。すぐ右下に見えるのがN橋。車のライトが、いつ途切れるともなくつらなっている。
「おい、合図してるぞ」
英治が指さす方をみんなが見た。河川敷にあるグランドの中央あたりで、ライトが明滅している。
相原は、持ってきたスポーツバッグからトランシーバーを出すと、アンテナを伸ばし耳にあてた。
「こちらナンバー1、どうぞ」
『了解。こちらナンバー33。解放区放送よく聞こえました。どうぞ』
ナンバー1というのは相原の番号で、33は橋口純子である。純子の声は、ボリュームをいっぱいに上げても聞きとりにくい。英治は、トランシーバーに顔を寄せた。
「そちらの反響を聞かせてください。どうぞ」
『その前に聞きますが、柿沼君そっちにいますか? どうぞ』
「いません、どうぞ」
『やっぱり……』
純子の声が途切れた。
「もしもし、柿沼がどうしたんですか? どうぞ」
『柿沼君は誘拐されたんです』
「柿沼が誘拐された……?」
相原が大きい声を出したので、みんながいっせいに注目した。
「ほんとか? どうぞ」
『ほんとよ。うちのママが柿沼君ちへ入院してるでしょう。いま大騒ぎよ』
「なんだ、また子どもが生まれるのか?」
『そうよ』
「何人目だ?」
『七人目』
「うへぇ」
『おどろくでしょう。うちのパパとママは神さま信じてるから、できた子どもは絶対おろさないのよ』
「じゃ、まだ生むつもりなのか?」
『うん。兄弟で野球チームをつくるんだっていうから参っちゃうんだ』
橋口純子の家は、来々軒(らいらいけん)という中華料理屋である。中華料理といっても、できるのはラーメン、チャーハン、ギョーザくらいのものである。
兄弟の多い純子は、普通の家みたいに正月や誕生日におこづかいはもらえない。おこづかいが欲しければ労働をしなければならない。
長女の純子は、学校から帰るとすぐ店に出て働く。出前にも行くし、赤ん坊のおむつも替える。掃除や洗濯はお手のものだ。
働くことが何より好きな純子は、高校へは進学せずに家を手伝うのだそうだ。いつも勉強に追い立てられ、偏差値が頭から離れない英治を、かわいそうだと言ってくれる。純子と話していると、気持ちがのんびりして明るくなる。だから彼女が好きだ。
英治は相原の脇腹(わきばら)をつついた。
「柿沼が誘拐されたことがどうしてわかったんだ? どうぞ」
『身代金を寄こせっていう電話がかかってきたんだって』
「いくらだ? どうぞ」
『千七百万円』
「ずいぶんはんぱだな」
『払わなければ殺すってさ』
「殺す?」
相原の顔がこわばった。英治も首筋に鳥肌が立ってきた。
『そうよ。ひどいでしょう』
「警察には言ったのか? どうぞ」
『まだみたい』
「どうして?」
『あなたたち男子生徒全員がいなくなったでしょう。だからみんなで騒いでたのよ、そこへ誘拐だっていうんで、全員が誘拐されたと思ってるようよ』
「おれたち全員が誘拐されたって? 笑わしちゃいけねえぜ」
みんなが、肩をたたきながら笑いころげている。
『みんな笑ってるみたいね。だけど、こっちは笑いごとじゃないのよ。どうする?』
「どうするって、いまさら中止するわけにはいかねえよ。解放区に立てこもったばかりだから。あしたの放送で、おれたちは関係ないことを言やいいんだろう?」
『そうだけど、柿沼君どうする?』
「どうするって言われてもなあ」
『このまま、ほうっておくつもりなの? どうぞ』
純子の声が険しくなった。
相原が言いよどんでいると、「助けてやろうぜ」という声がした。とたんにみんなが、「そうだ、そうだ」と口ぐちに言い出した。
「どうするか、これから方法をみんなで相談するよ」
『いいわよ。柿沼君のことはあたしたちにまかせて』
「あたしたちにって、女子にか?」
『そうよ。あたしたちだって、柿沼君が殺されるかもしれないのに、みすみす指くわえて見てられないよ』
「言ってくれるぜ。おれ、見なおしたぜ」
『女子だって、やるときはやるんだからね』
「わかったよ。じゃ、あしたの朝八時に連絡してくれないか。どうぞ」
『了解。菊地君に替わって』
「OK、おい菊地、彼女からだ」
相原は、トランシーバーを英治にわたした。
「もしもし」
『英ちゃん、元気?』
「元気さ」
『頑張ってね』
「うん」
『じゃあ、バイバイ』
純子の明るい声が消えた。もっと話したかったのに、どうしてこんなに早く切ってしまったのだ。
「菊地はいいなあ。心配してくれる彼女がいて」
日比野がうらやましそうに言った。
「彼女がほしかったら、もっと減量しろよ」
安永が言うと、みんながどっと笑った。
「笑ってる場合じゃねえだろう。柿沼は誘拐されたんだぜ」
相原は、きびしい顔で言うと、橋口純子との会話の内容をみんなに説明した。
「おとなってのは、だから信用できねえんだよな。子どもを誘拐して金を奪おうなんて、やり方がきたねえよ」
安永が、唇をとがらせて言った。
「女子だけにまかしとくのはヤバイと思うぜ」
英治は、しゃべりながらも不安が次第にふくれあがってきた。
「警察に言うのかな?」
「わかんねえ」
「ポリ公が動いたらもっとヤバイぜ。テレビで見たけど、そういうとき犯人は、大抵警察に言ったら命はないって言うんだろう」
日比野の顔もこわばっている。
「おれたちで、何かやれねえかな?」
「こんなときに誘拐されるなんて、やつもついてねえよ。おれたちはここから出るわけにいかねえんだもんな」
「おれたちの解放区。一時中止にしたら……」
宇野秀明が、口の中でつぶやくように言った。宇野は、家に帰りたくなったのかもしれない。
「お前、帰りたければ帰れよ」
相原が言った。
「そういう意味で言ったんじゃないんだ」
宇野は、慌てて首を左右に振った。
「助ける方法はないことはないさ」
中尾和人(なかおかずと)が、落ち着いた声でぽつりと言った。みんなが中尾の方に視線を向けた。
眼鏡をかけて小柄な中尾は、英治と同じサッカー部である。練習は熱心なのだが、もって生まれた運動神経のにぶさのためか、いっこうに上達せず、ドジばかりやっている。
しかし成績の方は、別に塾に行くわけでもないのにトップであった。英治はだから、相原とは別の意味で、ひそかに中尾を尊敬している。
「あすの朝八時、橋口と連絡するだろう。そのときこう言えばいいんだ」
相原は、食い入るように中尾の口もとを見つめている。
「誘拐犯人に金をわたす前に、柿沼が無事でいることをたしかめたい。そのために柿沼の手紙をほしい。そう言えば、犯人だってきっと柿沼に手紙くらい書かせてくれると思うんだ」
「手紙に何か書こうとしたって、犯人もちゃんと調べるだろう」
「そりゃもちろんさ。だけど柿沼のことだから、手紙をよこせと言えば、犯人にはわからない暗号で書いてくるはずだ」
「そうか、そういえば柿沼は暗号の天才だった」
英治は思わず手をたたいた。
「ほかに、だれかいい案があるか?」
相原は、みんなの顔を見わたした。
「中尾の案でやってみようぜ」
英治が言うと、みんながそれに賛成した。
「じゃ、そうしよう」
「みんな、空を見てみろ。星がきれいだぜ」
立石剛(たていしつよし)がだしぬけにそう言うと、仰向けにひっくりかえった。つられて英治も、仰向けになって空を仰いだ。英治は、このところ星なんて見たこともない。天の川が見えた。首が痛くなったので、立石と並んで寝た。
それがきっかけになったのか、まるでドミノみたいに、みんなつぎつぎとひっくりかえった。
「まず北の空を見ろよ。あそこにあるのが北極星(ほっきょくせい)だ。これはだれでも知ってるだろう」
立石の家は三代つづく花火屋で、立石も小学校のときから、父親の花火の打ち上げについて行かされたのだそうだ。
星に強くなったのは、そうやっていつも夜空を見上げていたからで、クラスでは星の王子さまというあだながついている。
「こぐま座はわかるな。それに北斗七星(ほくとしちせい)も」
「わかるさ」
あちこちで声がした。
「では南を見よう。銀河の中を見てくれ。真上に近いところでよく光っている星があるだろう?」
「あった」
英治は思わず大きな声を出した。
「あれがはくちょう座のデネブだ。そこから右の方を見ると、やはり光っている星がある。これがこと座のベガだ。わかるか?」
「わかる」という声と、「わかんねえよ」という声が交錯した。
「この二つの星を底辺にして二等辺三角をつくるんだ。光ってる星があるだろう。それがわし座のアルタイルだ」
「わかった。あれだろう?」
英治は手を伸ばして、指さした。
「そうだよ。あの三つの星をつないで、夏の大三角っていうんだ。ほら、七夕(たなばた)で牽牛(けんぎゅう)と織女(おりひめ)ってのがあるだろう?」
「七月七日の夜、二人が一年に一度だけ会えるってあれだろう?」
「その牽牛がアルタイルで、織女がベガさ」
「そうか、あれがそうか……」
星を眺めていると、解放区のことも誘拐のことも、みんな消しゴムで消したみたいに、きれいになくなってゆく。
「やがて、おれたちみんながいなくなっても、星はああやって輝いているんだぜ」
立石が言うと、みんなしんとしてしまった。
背中に触れるコンクリートの温かさが気持ちよかった。