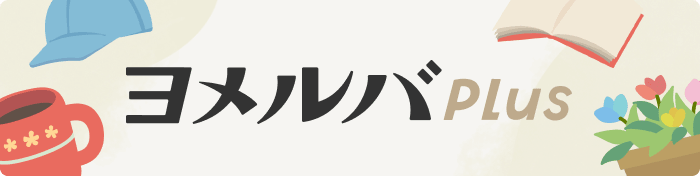3
相原徹は、送信機のスイッチを切って、
「どうだった?」
とみんなの顔を見た。
「ちょっと、固くなってたみたいだったぜ」
英治は、固くなっているのは、自分だって同じだと思いながら言った。
「とうとうやったぜ」
宇野秀明(うのひであき)が、うわずった声で言った。
「シマリスちゃん、おっかねえのか?」
安永宏(やすながひろし)が挑発するように宇野の顔をのぞきこんだ。シマリスというのは、小さくて臆病で、いつもちょこまかと動く宇野のあだなである。
「おっかねえもんか」
一四五センチの宇野は、一七〇センチの安永を、見上げるようにしてにらんだ。
部屋は、もと事務室だったらしく、スチールデスクが二十ほど、ほこりをかぶって並んでいる。その上にろうそくが三本立っているだけだから、顔はほとんど影になって見えない。
「無理すんなよ。声がふるえてるぜ」
みんな、火がついたように笑い出した。
「からかうなよな」
日比野(ひびの)が言った。日比野は一六〇センチ、七〇キロ、宇野の体重の倍はある。いつもおとなしくて、カバというあだなの日比野が、副番の安永に、こんな口の利き方をしたことに、みんな一瞬しんとなって成り行きを見守った。
「なんだカバ。おれにインネンつけようってのか?」
安永は、すごんでみせた。
「インネンつけるわけじゃないさ、こわいのはみんな同じなんだ」
日比野は、ゆっくりとした口調で言った。
「おもしれえ、受けて立つぜ」
安永は、ボクシングのファイティングポーズをとると、日比野にこいと手招きした。それが、ろうそくの炎で、壁に大きな影を映した。英治は息をつめた。
「デスマッチ、一本勝負。時間無制限」
天野(あまの)が、リングアナウンサーみたいな大声を出した。将来スポーツアナウンサーを目指している天野は、特にプロレスの実況中継が得意である。
「二人とも、どうかしてんじゃねえのか」
相原が二人の間に入った。
「おれたちがけんかする相手は、おとなだってことを忘れちゃ困るぜ」
「そうか……。そうだったよな」
安永は、照れくさそうに、ファイティングポーズをやめた。
安永のことだから、このままではすまないと思っていたのに、意外にあっさりと引き下がったことで、英治は肩の力が脱けた。
「二人とも握手(あくしゅ)しろよ」
相原が言うと、安永は素直に手を差しだした。
「わるかった。かんべんしてくれよな」
日比野は、その手をおずおずとにぎりながら、
「おれも、ちょっと変だったよ」
「ちえッ。世紀の決戦の実況放送をやってやろうと思ってたのに」
天野は、いかにも残念そうな顔をした。
その一言で、それまでの緊張がとけたのか、みんなはじけたように笑いだした。
「いいかみんな。ここはおれたちの解放区。子どもだけの世界だ。楽しくやろうぜ」
相原が言うと、全員が「おーう」と叫びながら、拳を突き上げた。
英治は、なんだかしらないけれど胸が熱くなった。
六月の初めのことだった。クラブ活動のサッカーを終えた帰り道、並んで歩いている相原が英治にぽつりと言った。
「おれたちの解放区をつくろうと思うんだけど、おまえ、参加しねえか」
「解放区?」
英治は、自分より五、六センチ上背のある相原を、ちょっと見上げるようにした。
「解放区ってのはだな……」
夕陽に向けた相原の顔が、燃えるように赤い。
「おれたちがまだ生まれる前、大学生たちが権力と闘うために、バリケードで築いた地域のことさ」
「おまえ、どうしてそんなこと知ってんだ?」
「おれのおやじとおふくろは、大学時代に機動隊と闘(たたか)ったんだ。おまえんちのおやじだって、やったかもしれねえぜ」
「おれ、聞いたことねえな」
「じゃあ、ノンポリだったんだ」
「ノンポリ?」
「おまえんちのおやじみたいに、学生運動には無関心だった連中さ。だから、いい会社に入れたんだよ。おれんちなんか学生運動やったおかげで、就職するとこねえから塾をはじめたんだ」
「損したな」
「そうでもねえみたい。でも、本心はどうなのかな、やせ我慢かもしれねえよ」
「権力ってなんだ?」
英治は、相原にばかにされそうな気がしたが、思い切って聞いてみた。
「政府とか警察とか学校とか、要するにおとなたちさ」
「あんまり、よくわかんねえな。それで結局どうなったんだ?」
「そりゃ負けたさ」
「なんだ負けたのか」
英治はがっかりした。
「負けたっていいのさ。やりたいと思ったことをやれば」
相原の顔は、いっそう赤く見えた。
「どうしてだ?」
「おまえ、センこうとか親とか、おとなたちのやることに満足してるのか? 言いたいことはねえのか?」
「言いたいことはいっぱいあるさ。でも……」
「でも、なんだ?」
「しかたねえだろう」
「しかたねえとあきらめるのか?」
「だって、おれたちゃ子どもじゃんか」
「子どもは、なんでもおとなの言うことを聞かなくちゃなんねえのか?」
相原に、こういうふうにたたみかけられると、英治は、なんと答えていいかわからなくなる。
「おれたちだって、力を合わせればおとなと闘えるさ」
「そうかなあ」
英治には、とてもそんな自信はない。
「そうさ。解放区はおれたちの城さ」
「そこで何をやるんだ?」
「子どもたちだけの世界をつくるんだ」
「そんなことして、おとなたちが黙ってるかな?」
「黙ってねえさ、攻めてくるだろう。そうすりゃ追っぱらえばいいじゃんか」
「ヤバくねえか?」
「ヤバイさ。だからおもしろいんだ」
相原の目が、きらきらと輝いている。
「やるか?」
英治は、夕陽に目を向けた。眩しくてすぐ目を閉じた。まぶたの裏で火花が散った。
なんだか、すばらしいことが起こりそうな予感がする。しかし、同時にヤバイことも起きそうで不安だ。
「びびってんのか?」
「ちがう。考えてんだ。中学に入ってから、おもしろいことねえもんな」
「これからだってねえさ。だんだん、わるくなるばっかりだ」
「やるのは、いまでなくちゃいけねえのか?」
「いましかねえ」
「ほかに、だれがやるんだ?」
「おまえがはじめてさ。おまえがいやだって言えば、この計画はパーだ」
「おれのほかに、だれをさそうつもりなんだ?」
「一年二組の男子全員さ」
「それは無理だよ」
「どうして?」
「そんなことやってたら、絶対偏差値が下がっちゃうじゃんか。やるやつは、どうみたって半分だな」
「半分じゃだめだ、全員でなくちゃ」
「やるのはいつだ?」
「一学期が終わったらすぐだ」
「夏休みか……」
「何か予定があるのか」
英治は、母親の詩乃の顔を思い出した。このあいだ、夏休みになったら家族三人で、軽井沢へテニスをしに行こうと言われたばかりだ。すっぽかしたらなんと言うだろう。
「こっちの方が絶対おもしろいぜ」
相原に見つめられて、英治は反射的にうなずいた。
「よし、じゃあ決まった。あとは二人で手分けして、みんなを仲間にさそおうぜ」
相原の顔がすっかり明るくなった。
「解放区の場所はどこなんだ?」
「ほら、荒川の河川敷に区営グランドがあるだろう。あそこから見える荒川工機(こうき)って会社さ」
「会社なら社員がいるじゃんか」
「それが、だれもいねえんだよ」
相原は、にやっとわらった。
「どうして?」
「一か月前につぶれたんだ。この間、塀を乗りこえて中にもぐりこんで調べてみたのさ。あそこなら、すげえ砦(とりで)になるぜ」
──砦。
インディアンに取り囲まれた砦、その猛攻の前に、味方はばたばたと倒れてゆく。もうだめかと思ったとき、はるか地平線の彼方から姿をあらわす援軍の騎兵隊(きへいたい)。
西部劇でよく見るシーンだが、こんどの場合、はたして援軍はやってくるのだろうか。
「いつまで立てこもるんだ?」
「一週間はもつと思うぜ」
「食糧はどうするんだ?」
「それまでに、こっそり運びこんでおくのさ。あそこは、電気はつかえねえけど水は出るから、携帯用のガスコンロを持って行けば、ちゃんと暮らせるさ」
「電気がないっていうと、夜は真っ暗か?」
「キャンプに行ったと思えばいいだろう」
「おもしろくなりそうだな」
「おれたちだけで暮らしてるのがどんなに楽しいか。それを、毎日解放区放送で流してやるのさ。みんな、うらやましがるぜ」
「解放区放送?」
「ほら、FMのミニ放送局があるだろう。あれさ。あれなら、別に電気はなくても放送できるじゃんか」
「センこうやおとなたちの悪口も言おうぜ」
「もちろんさ」
英治は、胸がわくわくしてきた。
決行日の一週間前、七月十三日午後七時半。
曇っているせいか、月も星もない夜だった。
荒川河川敷の区営グランドに集まった男子生徒は、何度数え直しても二十二人全員であった。
「信じられねえなぁ」
英治は、相原と顔を見合わせた。相原は、大きくうなずいたまま何も言わない。きっと、感動のあまり、声が出ないにちがいない。
相原と英治が、手分けしてみんなをさそったとき、いやだと言う者はいなかった。しかし、そうは言っても実際にくる者はきっと減るだろうと思っていた。
それが全員集まるとは。
「みんな、ちょっと聞いてくれ」
相原が、黒い影のようなかたまりに向かって話しかける。
「この中に無理して参加してるのがいたら、やめてもらってもいいんだぜ。それだからって、おれたちは仲間はずれには絶対しねえから」
「無理なんかしてねえよ。やりてえからやるんだ」
黒いかたまりのあちこちで、そんな声がした。
「勉強がおくれるかもしれねえぜ」
英治が言った。
「いいって、いいって」
すかさず、だれかが言った。
「センこうににらまれるぜ」
「センこうなんてメじゃねえよ」
「おふくろが泣くぜ」
「勝手に泣きゃいいだろう」
「よし。じゃあこれから一週間の間に、籠城(ろうじょう)に必要なものを運びこむことにする」
相原は、ズボンのポケットから手帳を取りだすと、水銀灯(すいぎんとう)の明かりにかざした。
「まず第一に食糧品だけど、これは各自が一週間分持ってくること」
「そこ、冷蔵庫あるのか?」
日比野が言った。
「あるわけねえだろう。電気もつかねえんだから、持ってくるのは米と乾(かん)パン。それに缶詰(かんづめ)だ」
「缶詰なら、おれんちにいっぱいあるぜ」
柿沼が言った。
「そうか。おまえんちは医者だから、みんなが持ってくるんだな」
「そうさ。段ボール箱の二つや三つなら、持ちだしてもわかんねえよ」
「よし、そいつはいただきだ。ほかにも、家にあまってるものがあったら持ってきてくれ。食糧品のほかに、やかん、なべ、皿、携帯コンロ、しょうゆ、砂糖、塩なんかもいる」
「風呂はもちろんねえだろうな」
「風呂はねえけどシャワーはある」
「えッ? ほんとか?」
「ただし、水だ」
「なあんだ」
「そうだ。せっけんも持って行こう」
「運びこむのはどうするんだ?」
「ほら、あそこに塀が見えるだろう?」
相原は、堤防に並ぶ工場の一つを指さした。
「あれが、おれたちの解放区だ。あの塀から入れるんだ。ただし、これはセンこうにもおとなにも秘密だからな。気づかれないように行動してくれよ。もし、持ちだすのがばれても、解放区のことは絶対に言うな」
「わかってるって。だけど、女子は知ってるぜ」
日比野が言った。
「女子には話した。それはこういうことなんだ」
相原は、額の汗を腕でこすった。
三日前のことである。相原と英治がサッカーの練習を終えて帰りかけたとき、水泳部の中山ひとみがやってきて、
「男子だけで何かしようとしてるでしょう? おしえなさいよ」
と言った。
「なんにもしねえよ。なあ」
相原は、英治の顔を見て言った。
「あなたたちがこそこそ動いてること、あたしたちにはちゃんとわかってるんだからね」
「それは、夏休みに遊ぶ計画さ」
「じゃ、あたしたちも仲間に入れてよ」
いつの間にやってきたのか、堀場久美子(ほりばくみこ)がうしろにいた。久美子はスケ番である。
「女たちは入れられねえよ」
「どうして? 入れない理由を言いなよ」
「それはちょっと……」
「言えないんならいいよ。そのかわりあたしたちは、男子生徒がおかしなことやろうとしてるって、センこうにチクるからね」
「密告(みっこく)はきたねえぜ」
「じゃ、言いなよ」
相原は、空を見上げてから大きく息を吸いこんだ。
「言ってもいいけど、絶対秘密を守ってくれるか?」
「あったりまえじゃん。裏切ったら髪を切ってもいいよ」
久美子は髪を切り落とすまねをした。
「じゃ言うぞ」
相原は、覚悟を決めたように、解放区計画を話した。二人は息をつめるようにして聞いていたが、
「楽しそうじゃん。あたしたちも仲間に入れて」
「だめだよ。男と女がいっしょに立てこもったら、おとなたちはなんて言うと思う?」
「不純異性交遊(ふじゅんいせいこうゆう)?」
「それだけで、文句なしにパクられちまうぜ」
「それはそうかもしれないけど、あたしたちをシカトするなんて許せないよ」
シカトとは無視することである。
「シカトはしねえさ。女子にもやってもらいたいことがあるんだ」
「何よ」
「おれたちが中に立てこもるだろう。すると外の様子がわからねえ。それをおしえてもらいたいのさ」
「どうやっておしえるの?」
「それは、あとで考えるよ」
二人は、それで納得して帰って行った。
「女たちにしゃべって、秘密がもれねえか」
と安永が心配そうに言った。
「だいじょうぶさ。あいつらは信用できる」
「そりゃ、中山と堀場は信用できるけど、女ってのはいい子ちゃんが多いからな。チクるかもしれねえぜ」
「それはおれも考えたさ。だから話すのは、橋口純子(はしぐちじゅんこ)だけにしといてくれと言っといた。といっても、秘密にしておくのは、おれたちが解放区に立てこもるまでの間だ」
「入っちまえば、秘密もくそもねえか」
「そうさ」
相原はうなずいてから、
「谷本、おまえは外にいてくんねえか?」
と言った。
「どうして?」
谷本は、眼鏡を押し上げるようにして言った。
「おまえは、まだからだが治っちゃいねえじゃんか」
「もうだいじょうぶさ。ほら」
谷本は、松葉杖(まつばづえ)を脇に置いたまま、ふらふらと立ち上がった。
「わかった。おまえに外にいてもらいたいのは、からだのことだけじゃねえ。ほかにもやってもらいたいことがあるんだ」
相原は、谷本を座らせた。
「なんだ?」
「おまえはエレクトロニクスの天才だ」
「天才はオーバーだよ」
谷本は、照れくさそうにぼそぼそと言った。
「謙遜(けんそん)するなよ。おまえはパソコンのソフトだってできるんだろう?」
「それはそうだけど、やさしいやつさ」
「やさしくたってすげえよ。なあ」
相原が言うと、みんなうなずいた。谷本が一週間に二回は秋葉原(あきはばら)に通って、パソコンをいじっていることはみんな知っている。谷本の勉強部屋ときたら、電気製品で埋まっている。だから、彼のあだなはエレキングという。
将来はコンピューターを研究したいと言っているが、もしかすると、ノーベル賞くらい取れるかもしれない。
「おれたちは、おまえがつくってくれたFM発信機で、あそこから解放区放送をやる」
「電気もないのに、放送できんのか?」
日比野が聞いた。
「あんなものは電池でできるさ。ただし、一〇〇メートルしか届かない」
谷本は、まるで技師みたいな口の利き方をする。
「それは聞いたよ。だから、一〇〇メートルの間隔で、その放送を受けて、もう一度発信すれば、大きなネットができるんだろう?」
「そういうことになる」
「どうやってやるんだ?」
安永が聞いた。
「女子にやってもらうのさ。といっても、彼女たちはどうやっていいかわかんねえと思うんだ。そこでエレキングが必要なんだよ」
相原がそこまで考えていたとは、英治にとって驚異であった。とてもかなわないと思った。
「わかった。だけど、それだけじゃかったるいな」
谷本は、不満そうな顔をして見せた。
「もちろん、やってもらいたいことはまだあるさ。おとなたちの様子をさぐって、こっちへ報告してもらいたいんだ」
「そんなことは簡単だ」
「さぐるって、盗聴(とうちょう)するんだぜ」
「ああ、わけないよ」
谷本は、いとも簡単に言った。
「よし。これでおれたちは安心して籠城(ろうじょう)できるってもんだ。じゃあ、たのんだぜ」
「ああ、まかしとけ」
相原は、谷本とがっちり握手した。