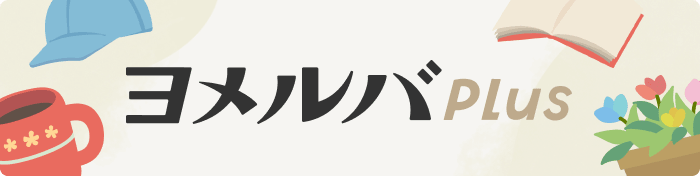二日 説得工作(せっとくこうさく)
1
英治は、窓の明るさで目がさめた。周囲の様子がいつもと変わっている。おやっと思った。
──そうか。ここは家ではなかったのだ。
もとは会議室だったのだろうか。三階にあるこの部屋には、長テーブルと折りたたみ椅子がいくつもあった。それを全部廊下に運びだし、床にビニールの防水シートを敷いて、そのうえで全員がごろ寝したのだ。
英治にとっても、おそらくみんなにとっても、こういう経験ははじめてである。最初のうちは、背中が痛くてなかなか寝つけなかった。もちろん、はじめて解放区に立てこもった夜ということで興奮もしていた。
解放区より、ブラックホールの方がいいと言ったのは立石だ。プロレス狂の天野は、ワンダーランドの方がいいと言った。安永は荒川城(あらかわじょう)にしろよと言った。
みんなで、夜おそくまでしゃべり合い、そのうち疲れて眠ってしまった。横を見ると、宇野秀明が背中を丸めて、おだやかな寝顔を見せていた。
宇野の過保護ママはクラスでも有名である。みんなにさびしくないかとひやかされて、ついに泣きだしてしまった。あれは少しかわいそうだった。
不安なのはみんな同じだった。だから宇野をからかって、自分の気持ちをまぎらわそうとしたのだ。
英治は、そっと起き上がって部屋を出た。廊下は薄暗く静まりかえっている。階段を降りる自分の足音がぺたぺたと頼りなく、汚れたコンクリートの壁にひびく。まるで監獄(かんごく)みたいだ。
外へ出ると明るさが目にしみる。わずかな空地を隔てて工場がある。この空地がこれからみんなの広場なのだ。
ビルの脇に消火栓があって、そこから水がちょろちょろともれて、広場のアスファルトにしみをつくっている。
これは防火用の消火栓(しょうかせん)で、ホースのつなぎ方もわかった。これがあるおかげで、体も洗えるし、炊事もできる。トイレには、バケツに一杯水を入れて持って行くことにした。
英治は、水を両手で受けると顔を洗い、口をゆすいだ。タオルを持ってくるのを忘れたので、顔をふくことができない。このまま乾かそうと思って、空に顔を向けた。
雲ひとつない空。朝が早いせいか、色はまだ淡いブルーだ。深呼吸をした。だれかが走ってくる足音がした。ふり向くと相原だった。
「もう起きてたのか?」
「目がさめちゃったんで、中をひとまわりしてきたんだ」
相原が、英治に解放区をつくろうと言い出したとき、なんとなくおもしろそうだというので賛成した。仲間をもっとふやそうと声をかけてみたが、集まるのはせいぜい五、六人だろうと思っていたのに、中尾や小黒(おぐろ)みたいに、勉強しか興味がないと思っている連中まで、仲間に入れてくれと言いだした。
そしてとうとう、クラスの男子生徒全員が立てこもるという大袈裟(おおげさ)なものになってしまった。
なぜだろう? みんな英治と同じように、何かやりたかったのだ。
それがいまはっきりとわかって、みんなは立ち上がったのだ。
──そうさ。子どもはおとなのミニチュアじゃないんだ。自分たちの思いどおりになると思っていたら大まちがいだ。それを、はっきりと思い知らせてやるぜ。
相原の顔は、心なしか蒼ざめて見える。いくら朝でも、この広い工場の中を、一人で歩くのは薄気味わるかったのかもしれない。
「おまえ、よく一人で歩けるな。勇気あるよ」
「それがだよ」
相原は、目を大きく見開いて英治を見た。
「どうしたんだ?」
「おれたち、きのうみんなでこの中を見てまわったよな」
「うん」
「そのとき、どこにもだれもいなかったよな」
相原は念を押した。
「いなかった」
「ところが、いたんだよ。人間が……」
相原の頰(ほお)が、緊張のためかぴくりと痙攣(けいれん)した。英治は、顔から血が引いてゆくのが自分でもわかった。
「おどかすなよ」
「おどかしてなんかいねえよ。ほんとなんだ」
相原がこんな真剣な表情をするのははじめてだ。
「うそだと思うなら、いっしょに行ってみるか?」
「いいよ。おまえがそう言うなら信じるよ」
英治は、とても見に行く気にはなれない。
「行ってみようぜ。おれもちょっと見ただけで、びっくりして逃げてきちゃっただろう。生きてるか死んでるかもわかんねえんだ」
「死んでる?」
声が勝手にふるえ出した。
「行こうぜ」
相原はそう言うと、先に立って歩きだした。ここで逃げたら、相原に軽蔑(けいべつ)されることは目に見えている。英治はあとにつづいた。
相原は、英治が出てきたビルに入って行く。一階は車庫と、製品の積み出しをしていたのであろうか、いまは何もないがらんどうである。前方の入口には、鉄のシャッターがおりているので中は薄暗い。
入口の近くに小部屋があった。もとは守衛(しゅえい)の詰所(つめしょ)か、それとも宿直室(しゅくちょくしつ)なのか。
「あそこだよ」
と相原は指さした。相原の歩き方が忍び足になった。英治も、音を立てないようにそのあとにつづく。
部屋にはガラス窓があった。相原は顔をつけてのぞきこむと、後ろから近づく英治の頭をかかえるようにして、ガラス窓に押しつけた。英治には、ちょっと高さが足りないので、中が見えない。近くから木ぎれを拾ってきてその上に乗った。
「な、いるだろう」
相原の押し殺した声が耳のはたでした。たしかに男が一人寝ている。
「生きてると思うか、死んでると思うか?」
部屋の中は、外よりいっそう暗く、男の表情も見えない。
「わかんねえ。だけど、きのうここはたしかに見たぜ」
「たしかにいなかったよな」
「そうすると、おれたちが寝てる間に入ってきたんだから生きてるさ」
こんなあたりまえのことが、相原はどうしてわからないのだ。
「それはそうだけど、奴はどこから入ってきたんだ? おまえだってわかってるだろう。おれたちがここへ入るときは、なわばしごを堤防(ていぼう)側の塀(ほり)にかけて乗り越えてきたんだ」
「ほかに入口があるんじゃねえのか」
「絶対ない。おれは徹底的(てっていてき)に調べたんだ」
「おかしいな。じゃお化けか?」
英治は相原の顔を見た。そのとき、乗っていた木ぎれから足がはずれて、派手な音を立てて床に転げた。
「痛えッ」
思わず悲鳴をあげた。相原が指を唇にあてたがもうおそい。
「起きたぞ。生きてる」
「どうする?」
英治は逃げ腰になった。
「会おう」
「みんなを呼んできてからの方がいいんじゃねえのか?」
「だいじょうぶさ」
相原が言ったとき、ドアーがあいて男が顔を出した。薄汚れてしわだらけの顔。髪は白いのだろうが、いまは灰色になっている。どう見ても浮浪者(ふろうしゃ)といった風体だ。
「おまえたち、どこからやってきた?」
意外におだやかな声だ。
「それより、おじいさんこそ、どこからやってきたんだ?」
相原は胸をそらすようにして、逆に聞きかえした。英治の方は、足が勝手にふるえ出して、止まらなくなってしまった。
「おじいさんだと? おまえたちいくつだ?」
「中一だよ」
「中一か。わしにもそのくらいの孫がいる」
「おじいさん、この工場の人?」
「ちがう。関係ない」
「じゃ、どうして泊まってるんだい?」
「泊まりたいから泊まっているんだ」
「家はないの?」
「あるさ、ずっと遠くに」
「どうしてそこに住まないの?」
「息子とけんかして出てきたんだ」
「それからずっとここに住んでるの?」
「そうだ」
老人は、ちょっとさびしそうに目をふせた。英治にも静岡(しずおか)におじいさんとおばあさんがいる。それを思い出して、なんだかかわいそうになってきた。
「だけど、きのうおれたちがやってきたときにはいなかったじゃん」
「きのうは、夜おそく帰ってきたんだ」
「どこから入ってきたの?」
「おまえたちこそ、どこから入ってきた?」
「おれたちは、塀を乗り越えたのさ」
「二人でか?」
「ちがう、二十人だよ」
英治は、二十人というところを、ことさらはっきりと言った。
「二十人だと……?」
老人は、口を半ばあけたまま、二人の顔を見つめた。
「おまえたち、ここで何をするつもりなんだ?」
「おれたちの解放区をつくるためさ」
「解放区?」
老人は目をしばたたかせた。
「おとなにじゃまされない、子どもたちだけの城さ」
「そんなこと、おとなが許すわけないだろう。ばかなことを考えるな」
「許さなかったら、戦うだけさ」
「戦うだと……? 勝てると思っとるのか?」
「負けるつもりで戦うやつはいねえよ」
「あきれた連中だな」
警戒的(けいかいてき)だった老人の目が、すっかり柔和になった。
「おじいさん、どうやって入ってきたのかおしえてくんないか」
相原が食いさがった。
「ついてこい」
老人は先に立って歩き出すと、ビルの外へ出た。そのまま真っ直ぐ広場のすみまで行って、マンホールのふたを指さした。
「ここだ」
「ここから入ってきたの?」
「そうだ」
「だって、この下は下水道なんだろう?」
英治が聞いた。
「そのとおり」
「下水道を歩いてくることができるの?」
「できるさ。ここをおりてしばらく行くと本管に出る。そこは立って歩けるほどの大きさだ」
「下水道って、どぶねずみがいるんじゃないのかな」
「そりゃいるさ。猫ぐらいの大きさのやつが」
英治は、もう少しで、声をあげるところだった。
「下水道を通ってどこへ行くの?」
「南へ三〇〇メートルほど歩いて上へあがると、中学の近くにある児童公園の、ブランコの下に出られる」
「ええッ。あのブランコなら乗ったことあるぜ。そういえばマンホールがあった」
「へえ。そんなところへ出られるのか」
相原は、首を振って感心した。
「おじいさん、どうしてそのことを知ってるの?」
「わしは、二十年前までこの会社で働いていたからさ」
「その秘密の抜け穴のこと、おじいさんのほかに知ってる人いる?」
「おらん。あの当時でも知っとるのはわし一人だった。ましていまなんか、だれ一人知るわけないさ」
「そうか。いいことを聞いちゃったぞ」
相原は、両手をにぎりしめてガッツポーズをとった。