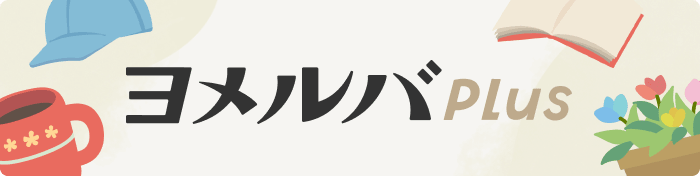一日 宣戦布告(せんせんふこく)
1
掛(かけ)時計の長針と短針が重なった。
正午。
さっきからそれを見つめていた菊地詩乃(きくちしの)は、あらためて大きなためいきをついた。
予定の帰宅時間から一時間もおくれている。最初のいらだちが、いつの間にか不安にすり変わっていた。何かあったのだろうか?
──交通事故?
まさか。学校からの帰り道に交通事故なんて、起きると考える方がどうかしている。
成績がわるくて、学校に残されたのだろうか?
一人息子の英治(えいじ)は中学一年。きょうは一学期の終業式である。いくらおそくても、十一時には帰れるはずだ。
そうしたら、十一時半に英治をアウディ80に乗せて家を出発。十二時十分に、池袋(いけぶくろ)のサンシャインビルの前で夫の英介(えいすけ)を拾う。
英介の会社はサンシャインビルにあるのだが、きょうの午後から休みをとり、日曜日までの三日間、軽井沢(かるいざわ)で親子三人テニスをやったり、高原のドライブをしたりしようという計画である。
計画を立てたのは詩乃で五月のことである。夫の英介はさほど乗り気ではなかったが、英治がすごく行きたがっているからと言って、しかたなしに承知させたものである。
けさ英治が学校へ出かけるとき、詩乃は、道草をせずに早く家に帰ってくるよう、しつこいくらい言った。そんなことを言わなくても、英治は聞きわけのいい子なのだが、なんとなく虫が知らせたのかもしれない。
──それにしてもおかしい。
時間は容赦(ようしゃ)なく過ぎてゆく。詩乃は窓から表を眺めた。梅雨明けの青空がひろがって、道路は強い陽光を受けて、こうこうと光っている。英治が帰ってくるとすれば、向こうの曲がり角から姿をあらわさなければならないのだが、人っ子一人見えず、森閑(しんかん)としている。
突然電話が鳴って、思わず、椅子から腰を浮かした。悪い報せかもしれない。そうだ。きっとそうにちがいない。激しい動悸がして、胸苦しくなってきた。電話は鳴りつづける。意を決して受話器に手を伸ばした。
「いつまで、何をぐずぐずしているんだ?」
いきなり、夫の英介のどなり声である。
「英治が……」
「英治がどうかしたのか?」
「帰ってこないのよ」
「どこかで遊んでるんだろう。早く帰ってくるよう、ちゃんと言ったのか?」
「言ったわよ。口がすっぱくなるくらい」
「おかしいじゃないか」
「おかしいのよ」
詩乃は英介(えいすけ)の言葉を反復した。
「学校へ行ってみたのか?」
「いいえ、まだ」
「どうして行かないんだ?」
英介は声を荒げた。そう言われてみれば、まったくそのとおりだ。
「いまから行って見てくるわ。十五分したら、もう一度電話くださる?」
詩乃は、電話を切るや否や、自転車に乗って家を飛びだした。目がまぶしくなるほどの強い日差しだ。
中学校までは六〇〇メートルほどの距離である。途中、下校する生徒に出会うかもしれないと思ったのに、子どもたちの姿は全然ない。この時間だ。いないのが当たり前である。
急いだので、五分ほどで学校に着いたが、ここもがらんとして人影は見あたらない。ただ、運動場のすみのプールだけが人声で騒々しい。
詩乃は、自転車を校門の脇に置いてプールに近づいた。子どもたちは二十人くらいいる。もうすぐ、区の対抗試合があるから練習しているにちがいない。
知っている顔がないかと見まわしたとき、ちょうどプールから上がってきたばかりの中山(なかやま)ひとみと目が合った。ひとみは、にっこりわらって頭を下げた。
「ねえ、英治帰ったかしら?」
ひとみは、英治と同じ一年二組で〝玉(たま)すだれ〟という料亭の娘である。
「ええ、帰りましたよ」
ひとみは、一六〇センチをこす上背と、若い娘のように発達したからだをおしげもなく見せて言った。
「そう。いつごろ?」
「さあ、もう一時間以上前だと思います。菊地君、どうかしたんですか?」
「まだ帰ってこないのよ」
「へえ……。じゃ、どこかで遊んでるんじゃないですか?」
「そんなこと言ってた?」
「いいえ、聞きませんでした」
「それとも、成績がわるくて帰るに帰れないのかしら」
「成績わるいのは、私もいっしょ」
ひとみはぺろりと舌を出すと、いきおいよくプールに飛びこんだ。白い水しぶきが上がった。
水泳では中学で一番。区でも優勝するだろうと言われている。泳いでさえいればご機嫌なひとみに、母親の雅美(まさみ)は勉強しろとうるさく言うらしい。
それは、サッカーにばかり夢中になっている英治も同じで、詩乃はつい嫌味を言ってしまう。やはり英治にも、父親の英介のように、一流大学を出て一流企業に就職してもらいたいのだ。
詩乃は、校門を出たところにある電話ボックスに飛びこんだ。中はサウナみたいな暑さで、たちまち汗が全身から吹き出してくる。英治の友だちのだれかの家に電話しようと思った。それなのに、電話番号はひとつも思い出せない。
電話ボックスを出た詩乃は、ふたたび自転車で家に戻った。
クラスの名簿をひらくと、一番は相原徹(あいはらとおる)である。相原の家は両親で塾をやっている。
電話に出たのは、母親の園子(そのこ)だった。
「菊地ですけれど、徹君帰ってきました?」
「さあ」
『徹』と遠くに向かって呼ぶ声がした。
「帰っていないようよ」
「おたくも? うちの英治も帰ってきませんの。どこへ行ったのかしら?」
「あしたから夏休みだから、きっとどこかふらついているんでしょう」
園子は、まるで気にもかけていない様子だ。詩乃は、もし帰ってきたら連絡してほしいと言って電話を切った。
つづいて十番の佐竹哲郎(さたけてつろう)の家に電話した。受話器の向こうで子どもの声がした。
「哲郎君?」
「いいえ、俊郎(としろう)です」
はっきりと否定された。そういえば哲郎には小学校五年の弟がいた。
「お兄ちゃん学校から帰ってきた?」
「いいえ、まだ帰ってきません」
「パパとママはいないわよね?」
佐竹の家では夫婦共稼ぎで、昼間はだれもいないはずだと思いながら聞いた。
「はい」
予期したとおりの返事だった。
「お兄ちゃん、どこに行ったか知らない?」
「知りません」
詩乃は、ありがとうと言って電話を切った。これで、英治を含めて三人が学校から帰っていないということがわかった。そうなると、しめし合わせてどこかへ遊びに行ったのか。この三人は仲良しだから、そういうことがないとも限らない。
電話が鳴った。受話器を耳にあてると、夫の英介からだった。
「どうだった?」
「学校はとっくに出たらしいの」
「じゃ、どこへ行ったんだ?」
「わからないわ。帰ってこないのは英治だけじゃないのよ。相原君と佐竹君に電話してみたけれど、二人とも帰っていないの。ほかにもまだいるかもしれないわ」
「すると、みんなでどこかへ行ったというのか?」
「そうとしか考えられないわ」
「英治は、軽井沢へ行くことを知っていながら、無断ですっぽかしたというんだな?」
英介の声が変わった。我慢(がまん)の限界に達している感じだ。
「誘拐(ゆうかい)されたんでなければね」
「誘拐……?」
「まさかとは思うけれど」
「きょうの軽井沢行きは中止だ。ぼくはこれから家に帰る。それまで、ほかの友だちの家にも電話して聞いておいてくれ」
英介は、とたんに電話を切ってしまった。こんなことで軽井沢行きを中止するなんて、気が短かすぎる。それとも、本気で誘拐を信じているのであろうか。詩乃は、どこに電話しようかと思いながら、指は無意識に柿沼(かきぬま)産婦人科病院のダイヤルを回していた。電話口に、母親の奈津子(なつこ)を呼びだしてもらった。
「直樹(なおき)君、学校から帰ってきた?」
「いいえ、まだ。おたくも?」
「そうなの。いま、あちこち電話してるんだけど、だれも帰っていないのよ。おかしいと思わない?」
「そうね……」
奈津子は、上の空の返事をした。院長夫人とはいっても、薬局に入って忙しいので、子どものことにはかまっていられないのかもしれない。
「じゃいいわ。私、みんなに電話してみる」
「ごめんなさい。結果をおしえてね」
図々しいと言ったらいいのか、おおらかと言うべきなのか。しかし、詩乃はそんな奈津子を決して嫌いではない。
一年二組のクラス全員、英治以外の四十一人に電話し終わるのに三十分以上かかった。男子生徒二十一人のうち、八人はだれもいなくて電話に出なかったが、家にいたのは、谷本聡(たにもとさとし)ただ一人であった。
谷本は、体育の教師酒井敦(さかいあつし)にしごかれ、腰椎(ようつい)をいためて一週間以上学校に行っていない。だから、きょう学校に行った男子生徒は、全員家に帰っていないということになる。
谷本がやられたのは、必殺宙(ちゅう)ぶらりん事件といって、PTA(ピーティーエー)でも問題になりかかったのだが、校長が谷本の両親と話し合って、もみ消してしまった。
バスケットの練習中、相手側にボールを取られると、二回鉄棒にぶら下がる必殺宙ぶらりんという罰則を酒井が決めた。谷本は何度もボールを取られてその都度ぶら下がるうち、力尽きて転落、腰を打って入院したのだ。
谷本は男子生徒が学校から帰ってこない理由は知らないと言った。
一方女子生徒の方はひとみのほかは全員が帰宅しており、彼女たちも、男子生徒がどこに行ったのか、知っている者は一人もいなかった。
午後二時。
男子生徒の母親たちが詩乃の家に集まった。十二畳のリビングルームは、クーラーの限界を超えて、蒸れかえるように暑くなった。
「学校を出るときは、ばらばらだったみたいよ。だから、誘拐じゃないわよね」
宇野秀明(うのひであき)の母親千佳子(ちかこ)が、自分に言い聞かせるように言った。
「子どもたちは、自分の意志で行ったのか、それとも、だれかにつれて行かれたのかしら?」
佐竹哲郎(さたけてつろう)の母親紀子(のりこ)は、ふとっているせいか、ハンカチでしきりに額の汗をふいた。
「つれて行くっていったら人さらい? だって、あの子たち中学生よ。しかも、一人や二人じゃないのよ」
日比野朗(ひびのあきら)の母親邦江(くにえ)は、度の強い眼鏡の奥で、小さい目を光らせた。
「きっと、何かをたくらんで姿をかくしたにちがいありません。どうせ、そう遠くへは行ってないと思います。みんなで手分けしてさがしましょう」
いつの間に帰ってきたのか、夫の英介が言った。
「そうだわ」
英介の言葉に、みんな、はじかれたように立ち上がった。
「荒川(あらかわ)か隅田川(すみだがわ)で、水泳でもしてるんじゃない? きっとそんなところよ」
相原徹の母親園子が、明るい声で言った。
「おたくの徹君はともかく、うちの秀明は、絶対そんなことはしません」
千佳子が憤然と言った。
「むかしの子どもじゃあるまいし、それに、全員が家にも帰らず川泳ぎに行くなんて、そんなこと考えられて……?」
邦江も、皮肉をこめて言った。それは、邦江の言うとおりだと詩乃も思った。子どもたちだけで遊びに行くなんて光景は、いまでは、見たくても見られやしないのだ。
2
子ども捜しは夕方までつづけられたが、手がかりはまったくなかった。二十一人が、蒸発したように忽然(こつぜん)と消えてしまったのである。
「こうなったら、電車に乗って、遠くへ行ったとしか考えられないわね」
だれかが言った。もしそうだとすれば、二十一人もの中学生が切符を買って改札口を通ったのだから、いくら忙しい駅員でも覚えているはずだ。
中学校からいちばん近い駅はK駅である。ここは常磐線(じょうばんせん)、東武伊勢崎線(とうぶいせさきせん)、地下鉄千代田線(ちよだせん)、日比谷線(ひびやせん)が通っている。
そこよりやや南に京成電鉄(けいせいでんてつ)のS駅がある。西へ隅田川を渡って行くと、少し遠いけれど京浜東北線(けいひんとうほく)、東北本線(とうほくほんせん)のD駅がある。
母親たちは駅という駅は全部あたってみた。しかし、どの駅にも立ち寄った形跡はなかった。
「じゃ、車かしら」
二十一人が一度に移動するとしたら、バスか、それともタクシーに分乗したのか。バスの方は営業所に問い合わせてみたが、中学校の近くのバス停で、二十一人もの中学生が乗った事実はないという証言(しょうげん)を得た。
タクシーで行ったとすれば、これはわからない。とにかく、夜になっても帰ってこないようだったら異常事態と考えていい。そのときは警察に届けようということで意見が一致し、それぞれの家に戻った。
相原進学塾の電話が鳴ったのは午後七時だった。園子が飛びつくようにして受話器をとった。いきなり男の声がした。
「こんや午後七時からFM(エフエム)放送を行う。ダイヤルを八八メガヘルツに合わせろ。いいか、八八メガヘルツだぞ」
書いたものを読んでいるような無機質な声。
「もしもし、あなたはだれ? 徹はどこにいるの?」
園子は、受話器に向かってわめくように言ったが、なんの答えも返ってこないまま切れてしまった。
しばらく受話器の前で放心したように座っていると、また電話が鳴った。反射的に受話器に手を伸ばして耳にあてる。
「私、菊地。いまおたくにFM放送聴けって電話なかった?」
詩乃の声は、途中でかすれた。
「あったわよ」
「何かしら?」
「さあ。なんのことだかさっぱりわからないわ」
「身代金の要求じゃないかしら」
「だって放送するんでしょう。そんなことしたら、みんなに聞かれちゃうじゃない」
「そうじゃないの。FMの八八メガヘルツというのはミニ放送で、この近くの人しか聞こえないの。おそらく、私たち以外聞いている人はいないわ」
そういえば、最近若者たちの間で、音楽やおしゃべり番組を流す、ミニ局がはやっているということを聞いたことがある。
「でも、それだけで誘拐されたとは限らないわよ」
「あなたは楽天的すぎるわ」
「うちなんて食べるだけがせいいっぱい。身代金なんて言われたって、ビタ一文出せやしないわよ」
「そんな言い方しないで」
詩乃は怒ったように電話を切ってしまった。
「なんだ、なんの電話だ?」
夫の正志(まさし)が不安そうな顔を見せた。園子は電話のいきさつを正志に話した。
「ひょっとすると、二十一人は人質にとられたかもしれんな」
「子どもジャック?」
「そうだ。身代金は一人一人ではなく、二十一人まとめて、とんでもないものを要求してくるかもしれんぞ」
「でも、みんな無理矢理つれ去られたのではなさそうよ」
「そんなことは簡単さ。子どもなんておもしろいことを言えば、けっこうついて行ってしまうもんだ」
正志は、いつになく厳しい表情をした。
「中学生よ」
「中学生だろうと、高校生だろうと問題じゃない」
「考えるのは、放送をきいてからにしよう」
二十分ほどして、詩乃からまた電話があった。
「全員に例の電話があったらしいわ。七時の放送をきいたら、あなたのところに集まって対策を検討したいんだけれど、教室空いているかしら」
「ええ、いいわ。こんやはお休みだからどうぞいらしてくださいな」
園子は時計を見た。七時まであと八分。いったい何を言いだすのか。考えると胸が苦しくなってきた。
七時三分前に、ラジオのダイヤルをFMの八八メガヘルツに合わせた。まだなんの音もしない。
園子は、デジタル時計の変化する数字を追いつづけた。7:00。
突然、ラジオから音楽が流れだした。ひどく陽気でそうぞうしい曲だ。
「何? これ」
「こいつはアントニオ猪木(いのき)のテーマ『炎のファイター』だ」
「猪木って、プロレスの?」
「うむ」
正志はうなずいた。正志も徹もアントニオ猪木のファンで、この中継のときだけは、二人並んでテレビにかじりついている。
──それにしても、なんだってプロレスなのだ。
音楽のボリュームが落ちた。
『みなさんこんばんは。ただいまから解放区放送をお届けします』
またもや『炎のファイター』。それにかぶせるようにして詩の朗読が聞こえてきた。
『生きてる 生きてる 生きている
つい昨日まで 悪魔に支配され
栄養を奪われていたが
今日飲んだ〝解放〟というアンプルで
今はもう 完全に生き返った
そして今 バリケードの中で
生きている
生きてる 生きてる 生きている
今や青春の中に生きている』
(*編集部注 この本文の「アンプル」とは薬のような意味です)
『こんばんはこれで終わり。あすも午後七時から放送しますから、ぜひ八八メガヘルツにチャンネルを合わせてください。ではおやすみなさい』
放送は唐突に終わってしまった。
「おい、これは徹の声じゃないか」
正志が、大きな声でどなった。
「まさか……」
「いや、まちがいない。たしかに徹だ」
正志と目が合った。その目が激しく揺れている。たしかに、これは紛れもない徹の声だ。
「どうして徹が……?」
「わからん」
「脅迫されて、しゃべらされてるんだわ。そうよ、きっとそうよ」
園子は、自分に言い聞かせようとした。しかし、何かがおかしい。それは、この底抜けの明るさなのだ。