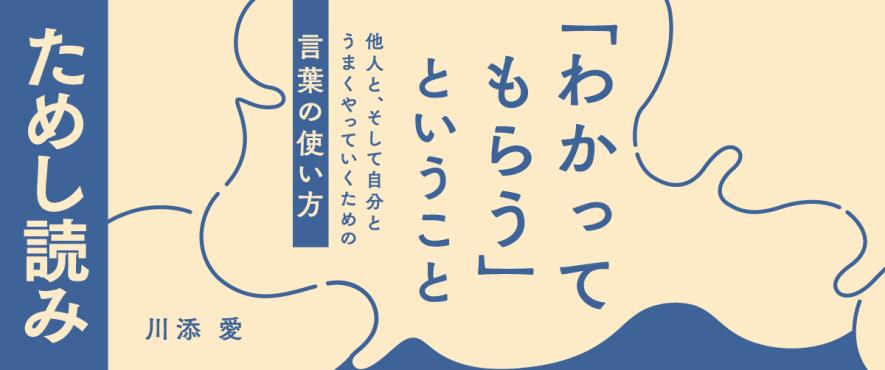
同じ時間を多く過ごす家族のなかでも、なぜか話が通じないことや、うまくお願いが伝わらないことなど、もどかしい思いをしていませんか? 大人にも子どもにも大切なこととして「わかってもらうこと」を挙げるのは、言語学者・作家として活躍する川添愛氏。上手な言葉の使い方を解説する新著『「わかってもらう」ということ 他人と、そして自分とうまくやっていくための言葉の使い方』をためし読み。
※本連載は『「わかってもらう」ということ 他人と、そして自分とうまくやっていくための言葉の使い方』から一部抜粋して構成された記事です。
数の間違いや誤解に気をつける
連絡において注意すべきは、言い間違いや書き間違いといったミスを防ぐことです。とくに日付や数量、金額、電話番号など、「数」がかかわる情報は間違いやすい上、ちょっとした間違いが大きなミスにつながります。
たとえば、相手に連絡した電話番号に間違いがあると、その番号にかけた相手は間違い電話をすることになってしまい、相手にも、間違い電話をかけられた人にも迷惑がかかってしまいます。
金額や数量は、桁が一つ増減するだけで大幅に変わります。2018年の平昌オリンピックのときに、ノルウェー選手団の料理人が卵を1500個注文するところを「15000個」と発注してしまい、必要な数の10倍の卵が届いたというニュースがありました。ちなみに1500個が15000個に化けたのは、AI翻訳の間違いが原因だったそうです。
私も以前、メールで「8月30日」と書こうとして「8月39日」と書いてしまい、気づかずにそのまま送信したことがありました。39日って何だよ!と自分でツッコミを入れてしまいましたが、送信先の方はきっと「30日? 31日? それとも29日の間違い?」と迷われたと思います。その他にも、重要な数値を間違えたり、あやふやな言い方をしてしまったりして、気づいたときにヒヤリとすることがあります。
どんなに慎重な人でも、人間であるかぎりはミスをする可能性があります。情報をやりとりする上で、誤解や見落とし、言い間違い・書き間違いはつきものです。
間違いや誤解によるトラブルを可能な限り回避するために、私はできるだけ「複数の手がかり」を入れるようにしています。
たとえばメールで日付を連絡するときは、「6月20日」のように日付だけを書くのではなく、「6月20日(木)」のように曜日も入れるようにしています。そうすると、仮に日付が間違っていたとしても、カレンダーで曜日を確認する段階で間違いに気づけるかもしれませんし、もし日付と曜日が食い違っていたら相手が間違いに気づいてくれる可能性があります。
数関連でさらに気をつけなくてはならないのは、数を含む文の曖昧さです。
とくに、一定の期間を表す時間表現では、「その中のどの時点なのか」があやふやになりがちです。たとえば、「15日までにこの書類を提出してください」という文では、書類の提出締め切りが15日のいつなのかが不明です。「15日の始業前までに」とも解釈できますし、「15日の終業前までに」あるいは「15日の23時59分までに」という解釈も可能です。
私は以前、とあるカードの有効期限について誤解をしたことがあります。カードに記載された有効期限は「20XX年9月」となっており、規約には「有効期限の三週間前に新しいカードを発送します」と書いてありました。それを読んだ私は20XX年の8月上旬に新しいカードが発送されるんだな、と解釈しました。しかし、8月の終わりが近づいても、いっこうに新しいカードが届きません。
何か手違いがあったのだろうかと不安になりましたが、もう一度頭を整理したところ、別の可能性に思い至りました。私は「20XX年9月」という有効期限を「20XX年9月1日」と解釈したため、8月中に新しいカードが送られてくると思ったわけですが、実際の期限は「20XX年9月30日」かもしれません。そう思って確認したところ、やはり期限は「20XX年9月30日」、つまり9月末でした。これも、「その中のどの時点なのか」が問題になる例です。
修正の連絡で誤解を防ぐ
仕事の上では、書類の間違いを直すなど、修正の連絡をすることが少なくありません。私も職業柄、文章の校正をする機会が多いのですが、「どこがおかしいか」「どんなふうに直すべきか」という指摘が曖昧にならないよう、できるだけ気をつけています。
たとえば、文言の修正をメール等でお願いする場合、私は「修正前の文言」と「修正後の文言」を一行にまとめて書くのではなく、それぞれ別の行に書いて、間に「→」を挟むようにしています。たとえば「今後とも、よろすくお願いします」という文全体を「よろしくお願いします」に修正したいときは、こんなふうに書きます。
今後とも、よろすくお願いします。
↓
よろしくお願いします。
なぜ一行にまとめないかというと、一行にすることで生じる「修正するのは全体なのか、部分なのか」という曖昧さを防ぐためです。もし、先の修正依頼を一行で書いたら、次のようになります。
今後とも、よろすくお願いします。 → よろしくお願いします。
これだと、「よろしくお願いします」に変更するのが「今後とも、よろすくお願いします」全体なのか、それともその一部の「よろすくお願いします」なのかがわかりません。もし後者のように解釈されてしまったら、「今後とも、よろしくお願いします」に変更されてしまいます。この手の勘違いは出版業界で実際に起こっているそうです。
また、文書の内容の見直しをお願いする場合も、指示が曖昧にならないように気をつけています。たとえば他の人が書いた文章の校正をしていて、「3段落目と6段落目にほぼ同じことが書いてあって冗長だな」と感じたとしましょう。こういうとき、単に「3段落目と6段落目の内容が重複しています」と指摘することもできますが、これだけだと相手には「何がどう重複しているのか」が伝わらないかもしれません。
こういうとき、「3段落目と6段落目の内容が、ともに○○についての説明となっており、重複しています」というふうに情報を付け加えることで、伝えたいことが明確になります。こんなふうに、具体的な情報を一言入れることを心がけています。
【書籍情報】
著者: 川添 愛
- 【定価】
- 1,760円(本体1,600円+税)
- 【発売日】
- 【サイズ】
- 四六判
- 【ISBN】
- 9784041148853
【お知らせ】
本記事の筆者・川添愛さんのお話を聞くことができるイベントがあります。興味を持たれた方は是非、下記のリンクから各イベント情報をチェックしてみてください。
① 川添愛『「わかってもらう」ということ』刊行記念トークライブ&サイン会 「わかってもらう言葉の使い方」
開催日時:2025年8月25日(月)19:00~
開催場所:大阪・梅田Lateral(配信チケットあり)
https://lateral-osaka.com/schedule/2025-08-25-16542/
② 8/28『「わかってもらう」ということ』刊行記念 川添愛さんトークショー&サイン会
開催日時:2025年8月28日(木)19:00~20:30
開催場所:ジュンク堂書店池袋本店(オンライン視聴チケットあり)
https://onlineservice.maruzenjunkudo.co.jp/products/j70019-250828
著者プロフィール
川添愛 言語学者/作家
1973年生まれ。九州大学文学部卒業、同大学大学院にて博士(文学)取得。2008年、津田塾大学女性研究者支援センター特任准教授、12年から16年まで国立情報学研究所社会共有知研究センター特任准教授。専門は言語学、自然言語処理。現在は作家としても活動している。著書に『白と黒のとびら』『自動人形(オートマトン)の城』『言語学バーリ・トゥード(〈Round 1〉〈Round 2〉)』(以上、東京大学出版会)、『働きたくないイタチと言葉がわかるロボット』(朝日出版社)、『コンピュータ、どうやってつくったんですか?』(東京書籍)、『ヒトの言葉 機械の言葉』(角川新書)、『ふだん使いの言語学』(新潮選書)など。


























