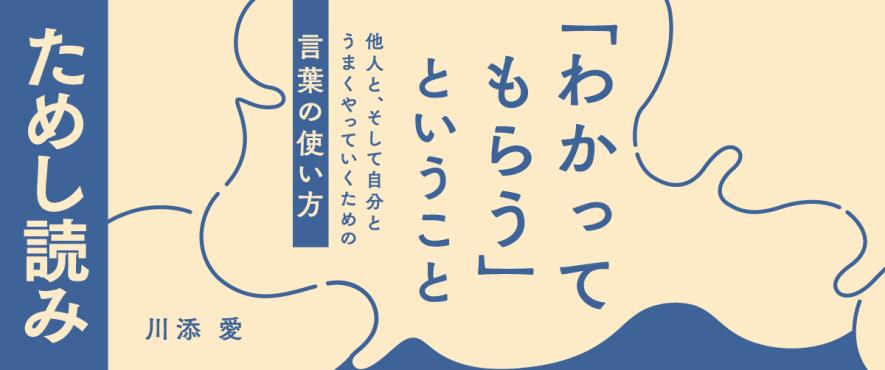
同じ時間を多く過ごす家族のなかでも、なぜか話が通じないことや、うまくお願いが伝わらないことなど、もどかしい思いをしていませんか? 大人にも子どもにも大切なこととして「わかってもらうこと」を挙げるのは、言語学者・作家として活躍する川添愛氏。上手な言葉の使い方を解説する新著『「わかってもらう」ということ 他人と、そして自分とうまくやっていくための言葉の使い方』をためし読み。
※本連載は『「わかってもらう」ということ 他人と、そして自分とうまくやっていくための言葉の使い方』から一部抜粋して構成された記事です。
私たちの生活や仕事は自分一人では成り立たないため、連絡や依頼や指示を行うことで、他人と適切に連携を取らなくてはなりません。その際の言葉の使い方が、仕事の能率やトラブルの回避、ひいては広い意味での幸福度に影響することは言うまでもありません。
私は、連絡・依頼・指示をわかってもらう上では「必要なことを、必要な順番で言うこと」「ミスや誤解を防ぐこと」「相手に嫌な思いをさせないこと」が重要だと考えています。
以下では、それらを実現するために心がけていることをお話しします。
連絡の内容をそぎ落とす
連絡において重要なのは、必要なことだけを言い、余計なことを言わないようにすることです。そのためには、ある程度の準備が必要です。
日常生活では、お店や企業に問い合わせの電話をする場面が頻繁に訪れます。そんなとき、事前に何も考えずに話すと、用件が発生した経緯をダラダラと話してしまいがちです。
たとえば、運送会社に荷物の再配達をお願いする電話で「あの、ええと、昨日の夜9時ごろに家に帰ったら郵便受けに不在連絡票が入っていて、『荷物用のポストに空きがなかったので持ち帰りました』って書いてあったんですが、再配達をお願いします」のように言ってしまうことはないでしょうか? 私はわりと、こんなふうに言ってしまうタイプです。
先日も、美容院への電話で「すみません、前回伺ったときに次回は○○日の14時からって予約したんですが、その日は急な用事が入ってしまって行けなくなって、それで、△△日なら大丈夫なので、もし空きがあるようなら△△日の14時に変更したいんですが」と言ってしまい、後から「余計なことをたくさん言ってしまった」と反省しました。
相手の立場に立てば、「再配達をお願いしたい」「予約を△△日の14時に変更したい」といった用件がもっとも重要で、私がそういう連絡をするに至った経緯などは不要です。こういうことは冷静に考えればわかるのですが、緊張していたり、頭がよく整理できていなかったりすると、ただただ自分の記憶を思いつくままに話すことになってしまいます。相手のことを考えれば、連絡をする前に、無駄な情報をそぎ落としておく必要があります。
また、こちらの用件をスムーズに理解してもらうためには、「カテゴリーの情報から話す」ことが重要です。まず、自分の連絡が大まかにどのようなカテゴリーに入るかを話し、その後で詳細を話すのです。
お店の受付や企業のサービスセンターで働く人のことを考えれば、電話をしてきた人の用件がどういった「カテゴリー」に入るかを早く知りたいはずです。たとえば「新規の予約」なのか「予約の変更」なのか、あるいは「サービスや商品についての問い合わせ」なのか、大まかなカテゴリーが分かれば心構えができます。
先ほど挙げた美容院への電話でも、私は早めに「予約の変更をお願いしたいんですが」と言うべきでした。そうすれば、お店の人は「どの日時からどの日時への変更だろう」と考えます。そして、そう尋ねられたら「○○日の14時に予約していたんですが、△△日の14時に変更できますか?」と言えばいいわけです。
用件を聞かされる相手の立場に思いを馳せるとき、相手がどんな思考をたどって行動を決定するのかを想像するのは大切です。たいていは、「大まかなカテゴリー」から徐々に詳細に向かっていくのが普通ですが、自分に余裕がなかったり、視野が狭くなっていたり、「相手はわかってくれるだろう」という甘えがあると、いきなり詳細から入りがちです。
まず大まかなカテゴリーの情報から入るのは、知識を説明する上でも重要です。
相手の時間を無駄にしない
連絡の内容が多い場合、一度の連絡でどれほどのことを伝えればいいか悩むことがあります。私は、できるだけ最小限のやりとりで済むようにすることを心がけています。
たとえば人に仕事を依頼するときは、その人が引き受けるか断るかを判断するのに必要だと思われる情報をすべて、依頼のメールに書きます。もし講演を依頼する場合は、講演の日時、場所、報酬、話してほしい内容、講演会の目的、参加者の属性などを、箇条書きで見やすく書きます。ポイントは、相手に「この依頼を受けた場合、自分は具体的に何をしなければならないか。また、それは自分にどんなメリットをもたらすか」がすぐにわかるようにすることです。すべての情報が揃っていれば、相手が諾否を判断してから返事することができるので、やりとりが一回で済みます。
中には「まずは打診から」と考えて、必要な情報を一部しか書かない人もいます。とくに、「最初からお金の話を出すのは失礼かも」という思いから、報酬を明記せずに依頼をするケースも見受けられます。しかし、依頼をされる側にとって、報酬は重要な情報です。これがないと、「報酬の有無をお知らせ下さい」という余計なやりとりが発生します。世の中には、最初の依頼の文面に報酬が明記されていない場合は「報酬はゼロなんだな」と解釈する人もいるようです。
お仕事のご依頼をいただいた場合は、早めに返事をすることも大切です。私はとくに、相手の申し出を断る場合は迅速に連絡するようにしています。
返事を急ぐのは、相手の時間を無駄にしないためです。私は昔、仕事で講演会の準備や冊子の編集などをしたことがあり、大勢の方に講演や原稿の依頼をしました。そのとき感じたのは、承諾か辞退かにかかわらず、早めにお返事をいただくのが非常にありがたい、ということです。お返事をいただくまではこちらの予定が決まらないし、仕事を次の段階に進めることができないからです。
とくに「お断りします」という連絡を早めにいただくと、すぐに別の方に依頼を出すことができます。逆に、相手の返事を長く待ったあげく「お断りします」と言われてしまうと、次の人に依頼する際に、締め切りや準備期間を短く設定せざるを得なくなります。そうなると、次の人にも断られてしまう可能性が高くなります。
つまり仕事のご依頼を早めにお断りすることは、依頼元の方の時間を無駄にしないだけでなく、その仕事を引き受けるかもしれない誰かに機会を与えることでもあるわけです。
【書籍情報】
著者: 川添 愛
- 【定価】
- 1,760円(本体1,600円+税)
- 【発売日】
- 【サイズ】
- 四六判
- 【ISBN】
- 9784041148853
【お知らせ】
本記事の筆者・川添愛さんのお話を聞くことができるイベントがあります。興味を持たれた方は是非、下記のリンクから各イベント情報をチェックしてみてください。
① 川添愛『「わかってもらう」ということ』刊行記念トークライブ&サイン会 「わかってもらう言葉の使い方」
開催日時:2025年8月25日(月)19:00~
開催場所:大阪・梅田Lateral(配信チケットあり)
https://lateral-osaka.com/schedule/2025-08-25-16542/
② 8/28『「わかってもらう」ということ』刊行記念 川添愛さんトークショー&サイン会
開催日時:2025年8月28日(木)19:00~20:30
開催場所:ジュンク堂書店池袋本店(オンライン視聴チケットあり)
https://onlineservice.maruzenjunkudo.co.jp/products/j70019-250828
著者プロフィール
川添愛 言語学者/作家
1973年生まれ。九州大学文学部卒業、同大学大学院にて博士(文学)取得。2008年、津田塾大学女性研究者支援センター特任准教授、12年から16年まで国立情報学研究所社会共有知研究センター特任准教授。専門は言語学、自然言語処理。現在は作家としても活動している。著書に『白と黒のとびら』『自動人形(オートマトン)の城』『言語学バーリ・トゥード(〈Round 1〉〈Round 2〉)』(以上、東京大学出版会)、『働きたくないイタチと言葉がわかるロボット』(朝日出版社)、『コンピュータ、どうやってつくったんですか?』(東京書籍)、『ヒトの言葉 機械の言葉』(角川新書)、『ふだん使いの言語学』(新潮選書)など。


























