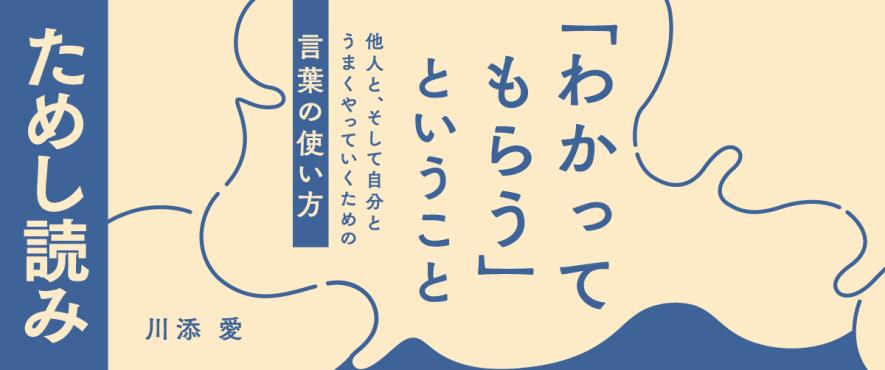
同じ時間を多く過ごす家族のなかでも、なぜか話が通じないことや、うまくお願いが伝わらないことなど、もどかしい思いをしていませんか? 大人にも子どもにも大切なこととして「わかってもらうこと」を挙げるのは、言語学者・作家として活躍する川添愛氏。上手な言葉の使い方を解説する新著『「わかってもらう」ということ 他人と、そして自分とうまくやっていくための言葉の使い方』をためし読み。
※本連載は『「わかってもらう」ということ 他人と、そして自分とうまくやっていくための言葉の使い方』から一部抜粋して構成された記事です。
一言入れることの効果
具体的な情報を一言入れるというのは、文章の校正に限らず、言葉の曖昧さによる誤解を回避する上でも有効です。
たとえば他人からの提案を承諾する場合に、単に「結構です」や「OKです」と返してしまうと、相手に意図がきちんと伝わらないことがあります。というのも、「結構です」「OKです」といった言葉は曖昧で、相手の提案に対して「そのとおりで良いです」と言っているようにも、「そのようにする必要はありません」と言っているようにも聞こえるからです。私はできるだけ、「ご提案のとおりで結構です」とか「そのようにしていただいてOKです」と、一言付け加えるようにしています。
「大丈夫です」を使うときにも注意が必要です。飲み会で「ビール、もう一杯飲みますか?」と言われたときに断るつもりで「大丈夫です」と言っても、相手には「はい、飲みます」という肯定の返事として受け取られる可能性があります。そういうときには「もうたくさんいただきましたので、大丈夫です」のように、一言付け加えると意図が明確になります。私はスーパーやコンビニのレジで「袋はご入り用ですか?」と言われて断るときにも、「なしで大丈夫です」のような言い方をしています。
もちろん、断る場合は「大丈夫です」のような言葉を使わずに「要りません」「要らないです」と言った方が明確です。しつこいセールスや勧誘を断る場合は、こういった直接的な否定をするのが正解でしょう。しかし、こういった否定は相手に強い印象を与えてしまうため、使いづらい面もあります。「○○で(/○○なので)大丈夫です」のような表現は、「大丈夫です」の柔らかさと、意図の明確さが両立できて便利だと思います。
「大丈夫です」のように、二つの正反対の意味を持つ言葉は意外とあるものです。たとえば「やばい」は、かつては「危険だ」という否定的な意味で使われていましたが、最近では「素晴らしい」という肯定的な意味で使う機会も増えています。「あきらめる」といった言葉も、志半ばで望みを捨てざるを得ない苦しい心情を表すこともあれば、見切りをつけることによって生まれる清々しい気持ちを表すこともあります。こういった曖昧さで相手を迷わせないためにも、結論を早めに言ったり、自分の意図を明確にする言葉を足したりする工夫は必要だと思います。
「○○をして」「○○を持ってきて」の曖昧さ
漠然とした質問には答えにくいものですが、それと同様に、漠然とした指示も遂行しにくいものです。
たとえば、始めたばかりの仕事で上司からいきなり「これ、いい感じでやっといて」と言われたら、たいていの人は困ると思います。上司の言う「いい感じ」というのが具体的にどういう状態なのかがわからないからです。
一方、自分が指示をする側になると、けっこう漠然とした指示をしてしまいがちです。というのも、漠然とした指示は「具体的にどうすればいいか」を考える作業を相手に丸投げできて楽だからです。
漠然とした指示は楽なぶん、リスクもあります。相手に「いい感じでやっといて」と仕事を振って「わかりました」と言われたとしても、こちらがイメージしている「いい感じ」と、相手が相手なりに考えた「いい感じ」が一致しているかどうかは、蓋を開けてみなければわかりません。自分と相手が互いのことをよく知っており、なおかつ価値観が近ければ「いい感じ」で通じることもあるかもしれませんが、それ以外の場合はこちらのイメージとずれた結果になることがほとんどなのではないでしょうか。
どれくらい細かく指示をしなければならないかは、自分と相手がどれほど知識を共有しているかによります。たとえば料理をほとんどしたことがない相手に料理をさせる場合は、食材の扱い方、包丁の使い方、火加減などを事細かに説明する必要があるでしょう。しかし、相手もある程度料理ができる人であれば、そこまでする必要はありません。
ただし、知識がある人はある人で、その人のそれまでの経験に基づいて物事を判断しようとします。たとえば「カレーに入れるジャガイモはこれぐらいの大きさに切るものだ」とか、そういった感覚が他人のイメージと食い違う可能性はあります。
一緒に働く経験を積んだ相手でもつねに阿吽の呼吸で動いてくれるとは限りませんし、たいていは「指示の目的」の共有が必要です。たとえば「スプーンを持ってきて」と言う場合にも、何のためにそう言うのかを付け加えないと、ほしいスプーンを持ってきてもらえない可能性があります。カレー用のスプーンを頼んだつもりが、ティースプーンを持ってこられるかもしれません。「カレー用のスプーンを持ってきて」のように目的をはっきりさせた方が、面倒が少なくなります。
世代差によって意図が通じないケースもあります。最近知ったのですが、「4時10分前」のような表現の解釈には世代差があるそうです。中高年がこれを「3時50分」と解釈する一方で、若い人の多くは「4時9分ごろ」と解釈するというのです。つまり「4時10分前に集合して」と指示しても、聞き手によっては正しく伝わらない可能性があります。
また、喫茶店で年配の方がホットコーヒーのつもりで「ホット」と注文したところ、若い店員さんに通じなかったという話もあります。こういったジェネレーションギャップの存在に気づくこと自体、簡単なことではありませんが、もし「伝わっていないのかも」と思ったら別の言い方をしてみる余裕は必要かもしれません。
【書籍情報】
著者: 川添 愛
- 【定価】
- 1,760円(本体1,600円+税)
- 【発売日】
- 【サイズ】
- 四六判
- 【ISBN】
- 9784041148853
著者プロフィール
川添愛 言語学者/作家
1973年生まれ。九州大学文学部卒業、同大学大学院にて博士(文学)取得。2008年、津田塾大学女性研究者支援センター特任准教授、12年から16年まで国立情報学研究所社会共有知研究センター特任准教授。専門は言語学、自然言語処理。現在は作家としても活動している。著書に『白と黒のとびら』『自動人形(オートマトン)の城』『言語学バーリ・トゥード(〈Round 1〉〈Round 2〉)』(以上、東京大学出版会)、『働きたくないイタチと言葉がわかるロボット』(朝日出版社)、『コンピュータ、どうやってつくったんですか?』(東京書籍)、『ヒトの言葉 機械の言葉』(角川新書)、『ふだん使いの言語学』(新潮選書)など。


























