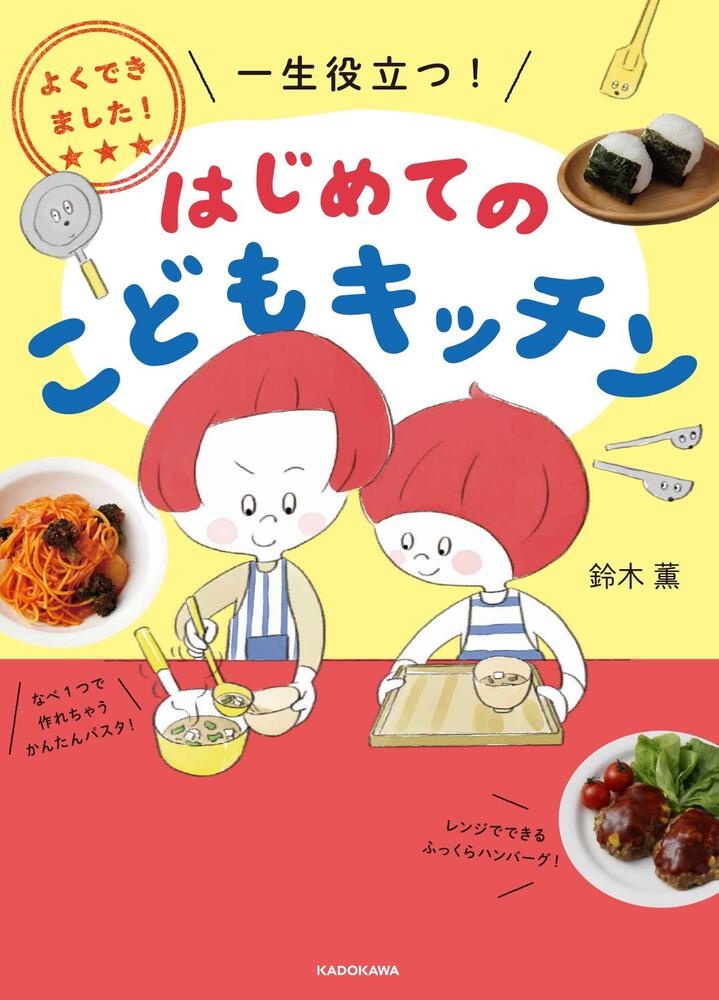好奇心が育ち、達成感が得られる!子どものためのはじめてのお料理本『よくできました! 一生役立つ! はじめてのこどもキッチン』の選りすぐりのレシピを紹介!
<はじめてならまずは、ごはんをたいてみよう!>
ごはんがたけるようになると、ふりかけをかけたり、なっとうをかけたり、自分でおなかをみたすことができる! これってすごいことだよね。大人になってからも、ずっとずーっと役立つからぜひおぼえてね。
ごはん
お米は、お水がすき通るまであらうと、たき上あがったときにつやつやになって、かおりもいいよ!

ーーーーー ー <道具>ーー ーー ー

<ざいりょう(作りやすい分量)>
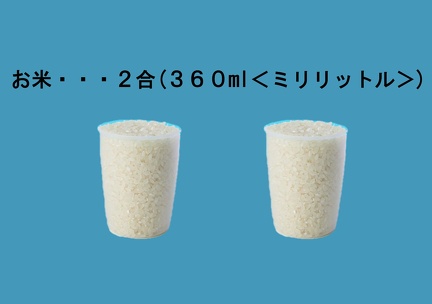
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ーーー ーーーーはかるーーー ーーーー

① 計量カップにたっぷりと米を入れる。

② ゆびでたいらにならし、2合分はかってざるに入れる。
ーーーーーーーあらうーーーーーーーー

③ ②のざるをボウルにかさね、水をそそぐ。

④ 米の上までたっぷりと水を入れたら、すぐにざるを上げて水を切る。水はながす。

⑤ またボウルにざるをかさね、水をそそぎ、指先を広ひろげてぐるぐると10 回くらいかきまぜる。
ざるを上げて水を切きってながす。これを 3 回くらいくりかえす。

⑥ 水がすき通とおったら、ざるを上げ、水をよく切る。
ーーーーーーーーたくーーーーーーーー

⑦ すいはんきの内がまに米を入れ、2 合の目盛もりまで水を入れ、30分おく。

⑧ すいはんボタンをおす。
ーーーーーーーまぜるーーーーーーーー

⑨ たき上がったら、やけどしないように気をつけてふたをあける。
しゃもじで下のほうからさっくりと、全体をまぜる。
おいしいごはん、たけたかな? ごはんがたけるようになったら、『よくできました!一生役立つ!はじめてのこどもキッチン』にのっているのっけごはんやおむすびにもチャレンジしてみてね。
※本には、やさいやくだもののひょうがついていて、ダウンロードもできます!
プリントしてかべにはったり、スマホにほぞんしてお買い物に役立てたりしてくださいね。
「食」への関心がさらに高まる! おはなし①
お米はどうやってできるの?
お米を作るには、たくさんの手間と時間がかかります。それを知ることで、いつものごはんがよりおいしく、大切に思えてきます。
※作業の時期は、地域によってちがいます。
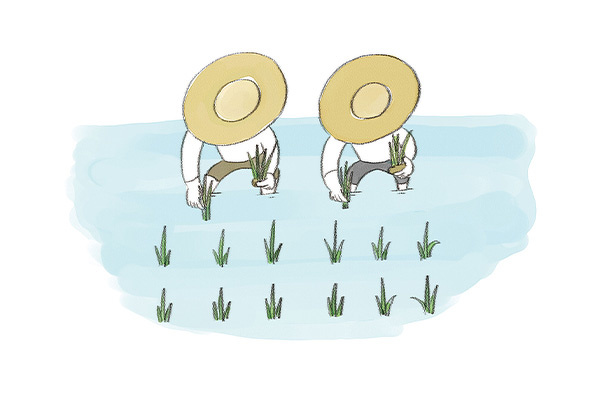
『春』
お米作りは、3~4月ごろ、お米の「たね(たねもみ)」をえらぶことからはじまります。「たね」をしお水につけるとしずむ、みがつまった「たね」だけをえらぶのです。
つぎは、「なえ」作り。はこに土とひりょうを入れ、「たね」をまき、ビニールハウスなどでおんどをちょうせいしながら、大事にそだてて「なえ」にします。
そして5月、いよいよ田うえの時期。田たんぼに水を入れ、土がどろっとするまでかきまぜて、たいらにならしたら、じゅんびオッケー。「田うえ」専用のきかい(田うえき)をつかって、田んぼに「なえ」をうえていきます。
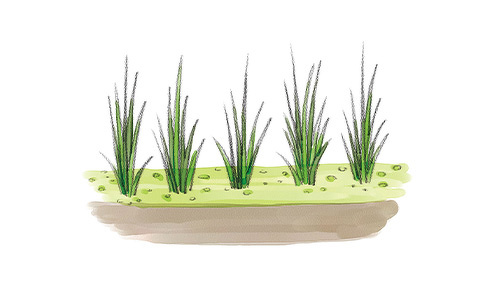
『夏』
田んぼにうえた「なえ」は、「いね」という名前にかわります。「いね」を元気にそだてるために、やることはたくさん。一番大事なのは、水の管理です。田んぼの水が少なくなったら水を入れ、多すぎるときは水をぬき、こまめにちょうせいします。雑草をぬいたり、害虫をとったりもします。
7月、「いね」があるていどそだってきたら、田んぼの水をぬいて土をかわかし、土に空気を通します。これは、「いね」のねっこをそだて、「いね」をじょうぶにそだてるためです。

『秋』
9月、「いなほ」が、よくふくらんでたれさがり、黄金色になったら、「いねかり」の時期。コンバインというきかいで「いね」をかり、「いね」から「もみ」をとります。
つぎに、もみをかんそうさせ、「もみすりき」というきかいで、からをとってから「お米」にします。そのまま食べれば「玄米」、食べやすくするために「精米」という作業で、ひょうめんをけずったものが「白米」です。
ふだん食べているお米は、農家の人たちのはたらきや、太陽や雨、土などの、自然の力によって、長い時間をかけて作られています。ほかの野菜や肉、魚だって、同じこと。「ありがとう」の気持ちをもって、大事に食べましょう。