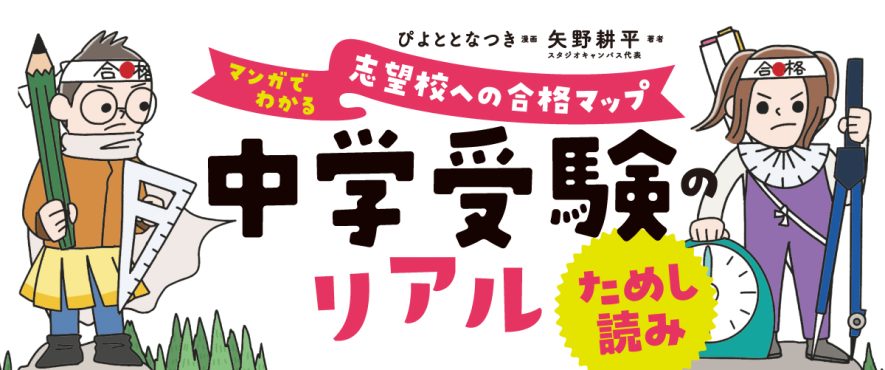
中学受験をはじめる前に知っておきたい「60のポイント」を、講師と保護者の視点を持つ矢野耕平先生が実体験をもとにわかりやすく解説します。
家庭のリアルな悩みを描いたマンガとともに、子どもと親が納得のいく選択を重ねながら、後悔のない受験生活を送るためのヒントをお伝えしていきます。
※本連載は『中学受験のリアル マンガでわかる 志望校への合格マップ』から一部抜粋して構成された記事です。
◆これまでの回はこちらから
どうして中学受験を始めるのですか
周囲が中学受験をするから、ウチも……は危険
第1章では「わが子の中学受験、その前に」と題し、これから中学受験を検討されるご家庭の保護者に考えてほしいことを書いていきましょう。
本書を手に取ったということは、中学受験に関心がおありなのだと思います。それでは、皆さんはわが子に中学受験の世界を選択させることをどうしてお考えになったのでしょうか。
「はじめに」でも言及しましたが、昨今は中学受験が盛況を博していて、皆さんの周囲でもこの手の話がよく交わされるのではないかと思います。
だからでしょうか。中学受験を検討する理由としていちばんに挙がるのは、「周囲が塾通いをして、中学受験をする。だからわが家もその世界に関心を抱いた」というものです。わたしが塾講師あるいは塾経営者として、数多くの保護者と話をしている中での感覚に過ぎないのかもしれませんが。
誰がいつどんな動機で中学受験の世界に興味関心を抱くのか、というのは「偶発性」に依ります。ですから、わたしは一概に「周囲が中学受験をするから」という動機付けを否定するつもりはありません。
中学受験は「大変」な世界
ただし、この「中学受験に関心を持った動機」をそのまま「わが子が中学受験に挑む動機」と同一視してほしくはないのです。中学受験が気になったその先、塾通いをスタートする前に、保護者にはじっくりと考えてほしいことがあります。
まず、中学受験をする子どもたちの大半は、塾通いをします。小学校4年生いっぱいまでは比較的緩やかなカリキュラムで進行する塾が多く、週1〜2回程度の通塾で済むところが大半であり、そこまで大きな負担にはなりません。しかし、進級すればハードな学習が質量ともに求められるようになります。たとえば、小学校5年生以降は前年までと比較するとその様相が一変し、週3〜4回の塾通いが必要となるのが一般的です。なおかつ、授業時間も大幅に長くなる傾向にあります。中学受験をする小学校5年生、6年生は「塾漬け」の日々を余儀なくされるのです。
ですから、仲の良い友だちが中学受験塾に通い始めたから、わが子も……そんな雰囲気に流されて舵を切るのはおすすめしません。中学受験はわが子に「大変な労力が求められる世界」なのだという覚悟を持たなければいけません。それを知らずに中学受験の世界に入ってしまうと、さまざまな由々しき事態が生じる可能性が高くなるでしょう。一例を挙げますと、バレエ教室と塾を両立してほしいと考えていたが、小学校5年生になると、時間的、労力的にそれが厳しい状況になってしまった……それでも、無理に両立を求めることで、結果としてバレエも勉強も中途半端になってしまうし、本人はその両方を嫌がるようになってしまった……。こうなるなら、中学受験を志すことなど端からやめたほうがよかったのではないか……など。
保護者は入試問題を眺めよう
大変な労力が求められるのが中学受験と申し上げました。論より証拠です。保護者は、塾通いをさせるより前に、書店に陳列されている「私立中学校の過去問題集」(過去に実施された入試問題を掲載したもの)を眺めてみましょう。保護者自身が中学受験に縁のない人生を送ってきたなら、きっとその入試問題の内容を見て驚くに違いありません。大人でさえ、到底太刀打ちできないレベルの問題がずらりと並んでいると感じられるはずです。仮にわが子が小学校3年生だとしましょう。たった3年後にこういう難問に取り組まなければならない……そう考えながら過去問題集を見ると、中学受験の世界を少しだけ「体感」できるかもしれません。
それだけではありません。中学受験は「相当な費用がかかる世界」です(もちろん、私立中高一貫校進学後も)。この点の覚悟だって保護者は事前に持っておかなければいけません。たとえば、わが子が嬉々として塾通いを始めて、結果として学力がぐんぐん伸びていったとします。そういう「喜ばしい」タイミングで、「ぼくは○○中学校に行きたい」という希望を口にした際に、「いや、わが家は経済的に厳しいから、中学受験はさせられない」などとはさすがに言いづらいですよね。そのことがわが子を傷つけてしまうリスクもあります。


















