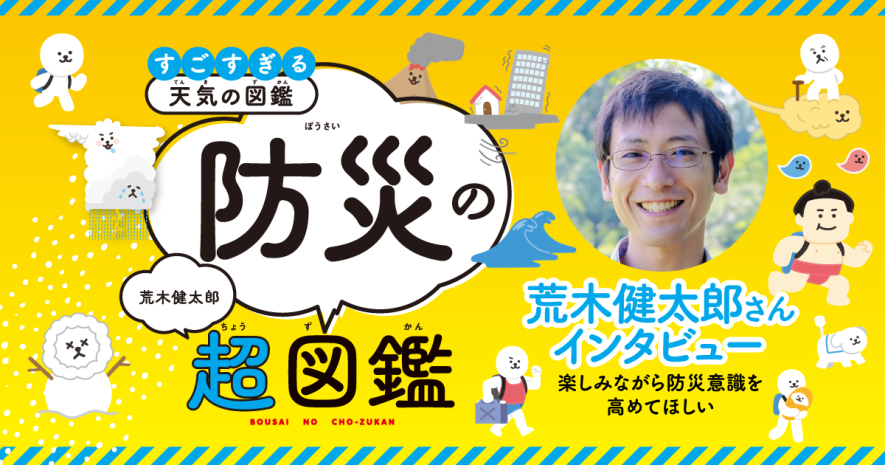
累計60万部突破の『すごすぎる天気の図鑑』シリーズから、スピンオフ第2弾『すごすぎる天気の図鑑 防災の超図鑑』が発売されました。雲のおもしろさと空の美しさを通して防災・減災を目指す著者の雲研究者・荒木健太郎さんに、本書に込めた思いと、親子で実践できる防災対策についてうかがいました。
■科学的に正確な防災の知識を届けるために
――これまでの『すごすぎる天気の図鑑』シリーズでも自然災害や防災に関するトピックを紹介してきましたが、今回改めて防災をテーマに一冊にまとめるに至った経緯を教えてください。
荒木さん:私はもともと防災に強い関心があり、気象災害をもたらす雲の仕組みや、気象監視や予測精度を高める研究を続けてきました。そこで課題に感じたのが、防災の大切さを訴えても、肩に力が入っていては長続きしないということ。そこで、日常的に空や雲を楽しみながら防災意識を高めてほしいと考え、『すごすぎる天気の図鑑』シリーズを執筆してきました。
近年、猛暑を含め自然災害が増えてきていて、自然災害で亡くなる方が毎年多くいます。大雨や台風をはじめ、地震、津波、火山噴火などに対して、どのように備えて、どのように避難するのか? さらに、復旧・復興に関する具体的な情報が求められていると感じていました。子どもから大人まで読めるように防災の知識を整理して1冊にまとめたのが、今回の『すごすぎる天気の図鑑 防災の超図鑑』です。気象の専門家として『防災アクションガイド』の制作に携わった経験をもとに、各分野や災害現場で活躍する専門家にも協力していただき、科学的に間違いがなく、かつガイドラインをふまえた最新の知識をまとめています。
――たくさんの情報が網羅された一冊ですが、読者にとくに読んでほしいページはありますか?
荒木さん:「非常用トイレの使い方」を紹介したページです。
これまでの防災本では、災害時のトイレ対策について記述にばらつきがありました。たとえば、庭に穴を掘って汚物を埋める方法は、サバイバル系の防災本で推奨されることもありますが、衛生上の理由から絶対にしてはいけません。この本では、防災の研究にも携わる専門家の協力のもと、「非常用のトイレは、1人1日5回の使用を目安に準備する」「コーヒーを汚物に見立てて非常用トイレを使う練習をする」といった対策を紹介しています。防災グッズは、備えるだけでなく、実際に使用して慣れることが非常に重要です。
また、身近なものを活用した「いざというときの防災術」も取り上げています。ここで強調したいのは、これらはあくまで最終手段であり、まずは自宅の備蓄、防災バッグを準備してほしいということです。手作り系の防災術に関心を持つ方は多いのですが、基本的な備えが前提であると、ぜひ知ってほしいと思います。
■“雲友”と同じ目線で話をしたい
――『すごすぎる天気の図鑑』シリーズでは、荒木先生のフォロワーである“雲友”をはじめとする有志が原稿全文を“先読み”して、寄せられた意見や感想を反映する取り組みが恒例になっています。今回も、スペシャルサンクスとして1600人以上の協力者の名前が巻末に掲載されていますが、 その中には子どももいるのですか?
荒木さん:たくさんいらっしゃいます。今回も「言葉の意味がわからない」という意見を受け、災害用語集のページを加えました。
これまでの『すごすぎる天気の図鑑』シリーズ本でもそうでしたが、わかりやすさを追求しながらも、子どもに読んでもらうために無理に内容を簡略化したり端折ったりせず、必要であれば難しい情報も盛り込むようにしています。シリーズ1冊目の『空のふしぎがすべてわかる! すごすぎる天気の図鑑』を制作したとき、担当編集者さんから「この内容は難しいのでは?」と指摘されましたが、このままやってみたいと私からお願いし、いまもそのスタンスを守っています。
――平易な表現や内容の簡略化をあえて避けるのは、なぜですか?
荒木さん:本を読んで「なぜだろう?」と疑問を抱いた読者が、自ら調べられるようにしたいからです。より多くの方に興味を持ってもらうと同時に、すでに関心を寄せてくれる読者の興味を、もっともっと尖らせたい。「なぜ?」「どうして?」という疑問を追究できるように、私たち制作側も手加減せず、同じ目線で話をしたいと思っています。
読者が気になったことを調べられるように、今回の『すごすぎる天気の図鑑 防災の超図鑑』にも、たくさんの参考文献を載せました。一度読んでわからない部分があったとしても、しばらくしてから読み返すと、「こういうことだったのか!」と感じるかもしれません。節目ごとに読み直しておさらいしてもらえたらうれしいです。
――荒木先生の思いが伝わっているのか、「内容が難しすぎる」という声は、ほとんど届いていないそうですね。
荒木さん:先読みに参加した子どもたちの意見を反映して修正しているからかもしれません。私や制作チームだけではどうしても視点が偏りますから、いろいろな立場の方からさまざまなご意見をいただける先読みキャンペーンは、内容の改善に非常に役立っています。今回も寄せられた声をひとつずつ精査して、新たに項目を加えたり、根拠となる文献を探して追加したりして、内容をブラッシュアップしました。“雲友”のみなさんは、ふだんは雲を一緒に楽しむ仲間ですが、本を作るときは一緒に制作する「戦友」として支えてくれています。
■防災を継続するコツは、「楽しむ」こと
――防災・減災のために雲や空の魅力を日々SNSで発信されていますが、防災に関する啓発について、思いが強くなったきっかけはありますか?
荒木さん:SNSでの情報発信により力を入れるきっかけとなったのは、2015年9月の関東・東北豪雨でした。前年の2014年に茨城県常総市で防災に関する講演をしていて、「集中豪雨は全国どこでも起こり、鬼怒川が氾濫することもある。ハザードマップをチェックして備えましょう」と呼びかけました。実際、関東・東北豪雨では常総市内の鬼怒川の堤防が決壊して講演会場も浸水したのですが、その後、講演に参加していた被災者から「まさかこんなことが起こるとは思わなかった」という声を聞きました。「まさか……」という言葉に、日常的に災害と向き合う重要性を改めて実感しました。
空は、私たち人間にとっていいこともよくないことももたらします。だからこそ、上手に向き合い、共存するしかない。自然を知って、正しく恐れて向き合うことが、防災につながると考えています。
――子どもの防災意識を高める方法はありますか?
荒木さん:親子で防災体験ができる場に行くのも一案ですし、家の中を防災の視点で見直したり、100円ショップで防災に役立つアイテムを探したりするのはいかがでしょうか。非常用トイレを使った自由研究もおもしろいですね。たとえば、非常用トイレの凝固剤でどんなものが固まるかを調べたり、消臭袋の効果を検証したり。親子で一緒に実験するのと、楽しみながら防災意識を高められると思います。
――そうして高まった防災意識を、どう継続するといいでしょうか?
荒木さん:春の進級時期や、3.11、9月1日の防災の日など、節目の時期に備えを見直し、アップデートすることをおすすめします。食料などの備蓄品に加え、お子さんのSOSカードも定期的に更新しましょう。『すごすぎる天気の図鑑 防災の超図鑑』をAmazonで購入すると、特典としてキッズ用SOSカードとマイ・タイムラインシートの台紙がダウンロードできます。ラミネート加工をして防水対策を施してから子どものカバンに入れておくと、いざというときに安心です。
また、防災ポーチを子どものカバンに入れて、常に持ち歩くことも有効です。ケガをしたときなど日常的にも活用して、使ったぶんを補充する習慣を身につけておきましょう。友達とお互いの防災ポーチを見せ合い、好みのアイテムを追加するのも楽しいですね。楽しむことが、防災行動を続けるコツなのだと思います。
取材・文:三東社
プロフィール

荒木健太郎
雲研究者・気象庁気象研究所主任研究官・博士(学術)。
1984年生まれ、茨城県出身。慶應義塾大学経済学部を経て気象庁気象大学校卒業。専門は雲科学・気象学。防災・減災のために、気象災害をもたらす雲のしくみの研究に取り組んでいる。映画『天気の子』気象監修。『情熱大陸』、『ドラえもん』など出演多数。主な著書に『すごすぎる天気の図鑑』シリーズ(KADOKAWA)、『空となかよくなる天気の写真えほん』シリーズ(金の星社)、『てんきのしくみ図鑑』(Gakken)、『読み終えた瞬間、空が美しく見える気象のはなし』(ダイヤモンド社)、『世界でいちばん素敵な雲の教室』(三才ブックス)、『雲を愛する技術』(光文社)などがある。
▼ためし読み連載実施中!▼
































