三時間目 『今は子育て三時間目』ためし読み 第4回
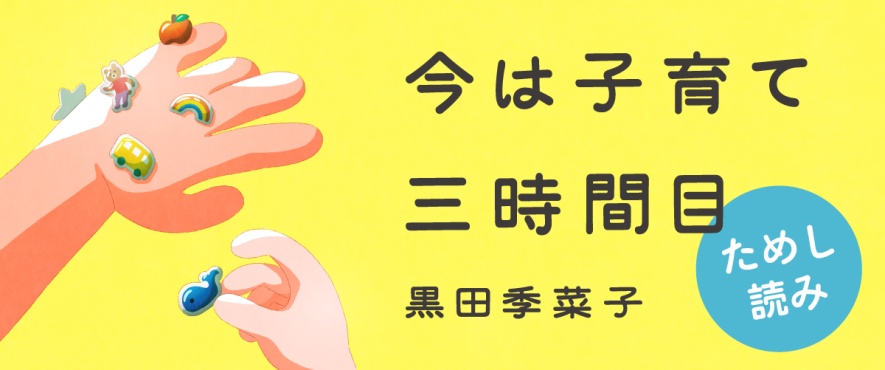
2025年、児童文学の小川未明文学賞で大賞を受賞した黒田季菜子さん。
いま注目の作家による、3人の子どもたちとその周りで起こる楽しくて、切なくて、なつかしくて、うれしいあれこれ…。
ちょっと大変な疾患の子もいるけれど、「ふつうの日常」をみずみずしく透明感あふれる筆致でつづった、珠玉のエッセイ集です。
※本連載は『今は子育て三時間目』から一部抜粋して構成された記事です。
三時間目
六歳は最近、元気すぎるくらい元気な同級生の揃う教室の音が怖いと、学校に行き渋るようになりました。
それはどういう具合のことかと言いますと、朝起きて、朝食を食べて着替え、さあじゃあ学校に行きましょうかという段になってから玄関で座り込み
「行きたくない」
「いや行こうや」
「行かない」
「断言か」
という母子の攻防が続いているという具合です。
これが幼稚園児の頃なら、子どもを無理やり抱っこしてなんとか、ということもできたのですけれど、この六歳児、普段ものすごく偏食のくせに、身長はすくすく伸びて現在一二〇センチ、体重もそれに合わせて二十キロ超。クラスでの背丈の順は真ん中よりもやや後ろの方です。
その上、心臓にそう軽くない病気があって、通学には電動車椅子を使っていて、医療用酸素は二十四時間必要だし、わたしが本人に代わって運んでいるランドセルは結構重いし替えの酸素ボンベはもっと重い。
それだから「学校なんか行かへん」と座り込みをされると、とても中年女性ひとりの、即ちわたしひとりの力では六歳を学校まで運べないのです。
とにかく今、この朝の「行かない」「まあそう言わないで」の攻防が大変で、こっちもちょっと「まあ…それなら無理にも…」なんてくじけそうになるし、強く言いすぎると泣くし、泣いたら途端にSPO2(酸素飽和度)が下がってしまうし、そうなるとびっくりするくらい顔色が悪くなるし。
そもそも教育とは、そこから生まれる知恵とは、突き詰めると人間の幸福のためにあるのではないのですか。
そうして、毎朝玄関でわたしは、ほんとうのさいわいについて考える羽目になるのです。銀河鉄道の夜のジョバンニみたいに。
そんな日常を過ごしているもので、一ヶ月に一回の大学病院の定期健診が入っていた今日は気持ちがすこしだけ楽でした。だって朝、大っぴらに遅刻して行けるから。
さらにこの日、三時間目は、特別支援学級で算数を勉強する予定になっていて、そこで普段は一緒に授業を受けていない、別の特別支援学級(六歳の学校には七つの特別支援学級があって、在籍する子ども達の支援の種類によってクラスが分かれているのです)のお友達が来て一緒に授業を受けて、授業が終わったら一緒に遊ぶそう。
ヨソがどうなのかはよく知りませんが、六歳の在籍する特別支援学級では先生と生徒がほぼ一対一で授業をしています。お陰で授業の進みが普通級よりやや早い場合もあって、それで余った時間にちょっと休んだり、皆で遊んだりしているらしいのです。
特に六歳は年相応の体力の持ち合わせがなくて、とても疲れやすいので、休むことも六歳達の大切な授業のひとつになっています。
それでこの日の三時間目、同じ一年生の別の特別支援学級の子と授業を受けた後に、みんなで一緒にアイロンビーズをするのだと言って意気揚々、六歳はまず朝一番に病院に出発したのでした。
六歳は出来得る限りすべての積極的治療を三歳の段階で既に終えてしまっています。だから今やっていることは、これからじわじわやってくる状態の悪化を可能な限り緩慢に、先延ばしにしてゆきましょう、というもので、根治という考え方はありません。
故に毎月病院に行ってやっていることといえば、血液検査と、それから生後二ヶ月の頃からもう長いお付き合いになる主治医との、お喋りという名の問診など。
採血のために処置室に呼ばれるまでに長くて一時間
採血から血液検査の結果まで一時間
診察室に呼ばれる時間は時の運
会計までにはまた十数分
大学病院とは、予約が予約の意味を然程持たない世界です。仮にちゃんと予約時間きっちりに行ったとして一診療科の検査受診会計は全部終えたら上手くやれても半日仕事。
そこに主治医が病棟に呼ばれたりすると更に時間がかかります。小児科に集う子どもらそれぞれの抱える難病を診療できる専門医は皆の、日本の宝であるのでそんなことに文句を言ってはいけないのです、急変か緊急の子のみがファストパスを持つ世界。
それが当たり前なのですけれど、この日は六歳が
(勝手知ったる)
という風情でひとり、処置室に入って採血を済ませ、小さなご褒美シールを握りしめてわたしの元に戻って来た時、背後の看護師さんが笑顔でこう言いました。
「六歳ちゃんは、三時間目に間に合いたいんよね!」
どうやら六歳は採血の前、毎月採血で顔を合わせる看護師さんとの世間話の中で、今日は三時間目にお楽しみがあるのだと、話したらしいのです。
採血時、看護師さんと楽しく世間話ができる。それがプロ疾患児。
「えへへそうなんですよう、最近はちょっと色々あって学校に行きたがらないんですけど、今日は特別みたいで」
わたしは、この数年ですっかりこちらも顔見知りになった看護師さんにそう答えました。するとそれから採血の結果を小一時間待って、番号で呼ばれた診察室で主治医は開口一番に
「今から三時間目、間に合うか?」
そのように仰る。どうやら看護師から伝達があったらしい。
「ウーン…まあぎりぎりってとこです」
腎臓の数値がちょっと悪いな、お水飲んでな。などという話を主治医から聞いて(原因は経口からの水分不足)、それからまた暫く待って処方箋予約票もろもろを受け取った小児科受付でも、いつも大変お世話になっているレセプト担当のマダムから
「どう? 三時間目間に合うよね?」
なんて念を押されてわたしは、元気に答えました。
「あとはわたしの脚力次第です!」
大学病院には、わたしが毎回自転車で連れて行っているもので。
さてこの日、処置室、中央検査部、主治医、レセプト担当、その他わたしの知らない各担当者、それぞれの皆さんがまさか本気で『巻き』を入れてくれたのかどうかは不明ですが、とにかく「三時間目ね!」と会う人皆に気にされて、普段よりも随分と早く検査受診会計を終えたわたしは、帰り道に二度ある上り坂を駆け上がってまた駆け下りて、そうして学校到着は十一時十分、三時間目の終了時刻は十一時二十五分なので、ぎりぎり間に合ったのです。
間に合いましたよ、関係各所。
そうしてまたこの日の十四時すぎ、わたしが六歳を迎えに学校へゆくと、この日もクラスは、元気印は相変わらず元気でやや荒れ模様だったということでした。
でも、六歳はまあまあいつも通り、『普通』って顔をして「泣かなかったよ」とのこと。
あの病院の皆様の、「三時間目ね、間に合わせるからね!」という気合のこもった優しい後押しが効いたのかもしれません。
明日もまた朝になれば「行かへん」「行こうや」「行かへん」「行こうよッ!」という玄関での攻防は続くような気はしますが、それでも時折、こういう日もあるよということで。
子どもとの時間は、長いようで意外とあっという間。
子育てをしたことがある人ならだれでも感じるせつなさ、なつかしさ、淋しさ……この本にはそれらが宝物のように詰まっています。
【書籍情報】

























