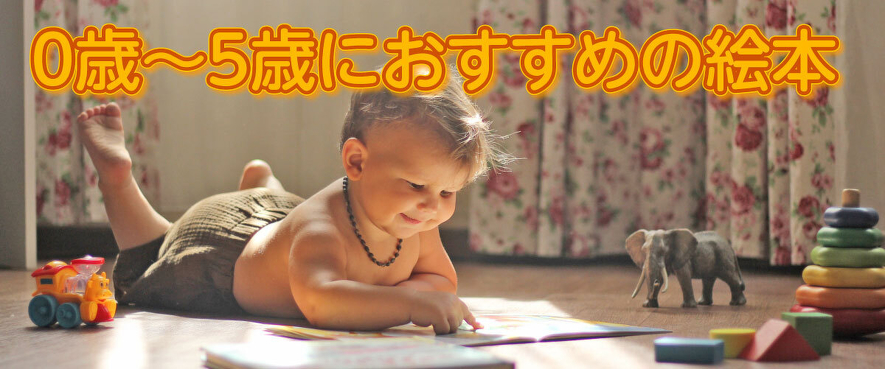7歳と1歳のママであり、今話題のモンテッソーリ教育のオンラインスクールを主宰しているモンテッソーリ教師あきえ先生。
前回の記事では、「イライラのコントロール法」についてお届けしました。今回の記事では、イライラしたり、不安になったりネガティブになりがちなシーンごとの具体的な解決策についてお話を伺います。
「こんな時、どうする?」にあきえ先生がアンサー!

Q 「ママ、遊ぼう!」と言われますが、仕事で疲れていたり、やらなくてはならない家事があったりして、イライラしてしまいます
A ずっと一緒に遊ばなくてOK!
子どもと一緒に遊んであげたいけど、体力的にも時間的にも難しいことがありますよね。基本的には、ずっと一緒に遊ばなくても大丈夫です。
まずははじめの数分、一緒に遊び、「時計の長い針が6になるまでね」「3回一緒にやろうね」などと、子どものわかる範囲で制限を設けて遊び、「じゃあ、ママはごはんを作ってくるね」と、その場を離れて大丈夫です。
子どもが「もっと!」と言う場合は、あと数分付き合ったり「ごめんね、ごはんを作らないといけないんだ」と話したり、様子を見てあげましょう。もし、できるようなら、一緒にキッチンに立って、料理をするのもおすすめです。
もうひとつ大切なのは、子どもが遊びに集中できる環境を用意してあげることです。おもちゃを雑多に置いただけでは、遊び方がわからなかったり、飽きてしまったりして大人を頼ることが多くなります。
子どもが今、何に興味があるのかを観察し、その欲求を満たすことができるようなグッズを用意します。
例えば、紙を切るのが好きならば、不要な紙や新聞紙を用意し、好きなだけ切らせてあげる。絵や字を描くことにハマっていたら、大きな画用紙を用意し、好きなだけお絵描きをさせてあげる。子どもがやりたいことが叶う環境であれば、一人でも集中して遊ぶことができます。
しかし、本当に疲れていたり、やることが山積みになっていたりする時は、少しお金はかかってしまいますが、ファミリーサポートなどに頼り、家事や育児をアウトソーシングすることもひとつです。そうすることで、ママやパパの肩の力が抜け、リフレッシュすることができ、イライラの気持ちが軽減できます。

Q 育児書やママ友からの「〇歳までに〇〇をする」ということがプレッシャーになることが……。
A 育児における主軸を持っていれば大丈夫!
育児書でたびたび目にする「目安」という言葉の通り、発達の平均値を記したものが育児書です。ママ友からの言葉も、その人の中での平均や決まり事なので、気にすることはありません。
とはいえ、頭では流されないと思っていても、ふと「大丈夫かな?」と不安に感じることがあると思います。そんな時に試してみてほしいのが「何を大切にして子どもを育てていきたいか」という育児における主軸について考えることです。
「自分で考える力を助けてあげたい」
「困っている人に手を差し伸べられるやさしさを持ってほしい」
「子どもも自分も毎日楽しいと思えるような親子関係でいたい」
このように、何を大切にしたいかを考えてみましょう。
もちろん、「頭が良くなってほしい」「運動神経が抜群の子に!」と考える方もいるかもしれません。どんなことでもいいので、一番大切なことは何かを決めておくと、流されにくくなります。これをパートナーと話し合い、共有することで、より家族のチーム力がアップします。
Q 下の子が生まれ、上の子もはじめは喜んでいましたが、次第に下の子に意地悪することがあってモヤモヤします。
A 今、その姿を見せてくれてよかった!
家族が一人増えることは、大人にとってもビッグイベントであり、喜びはもちろん、不安になることもあります。それは子どもも一緒のこと。
生まれてきて数年は自分のテリトリーだった部屋にベビーベッドやおむつなどのグッズがやってきて、ママの隣というポジションは自分だけのものではなくなるのです。それに戸惑う気持ちと、下の子をかわいいと思う気持ちが複雑に入り混じり、「意地悪」という形になっているのかもしれません。
しかし、その姿を今見せてくれて、ママやパパがそれに気づくことができたのだから、上の子をフォローしてあげることができますよね。
・「あなたのことをいつも見ているよ、大好きだよ」という気持ちを言葉や態度で伝える。
・話しかけられたら、手を止め、目を見て対応する。
・ハグをしたり、背中をさすったり、スキンシップを多めにする。
このようなことを意識しながら、上の子にかかわってあげるといいですね。

Q きょうだいげんかが絶えず、たまに手が出ることも! 「やめなさい」といつも叱ってばかりです。
A 家庭は1番はじめに社会性を育む場所
年齢が低ければ低いほど、社会性を育んでいる最中であり、自己コントロール力も未発達な時期。もちろん、手を出すことを許してはいけませんが、そのようなけんかをすることは、おかしいことではありません。
家庭は子どもにとって一番安心できる場所であり、一番はじめに社会性を学ぶ場所でもあります。
人に危害を加えるということは社会的にもNGな行為なので、それを許容しないよう、手が出たところで間に入って手を止め「たたくことはしないよ」と伝えましょう。そして、そのあとに必ず「おもちゃを返してほしかったんだよね。そういう時は『かえして』と言うんだよ」と、具体的にどうすればよかったかを伝えるようにします。
何回言っても同じことをくり返す!と思う方もいるかもしれませんが、人に危害を加えることを許容することはできないので、何十回でも何百回でも伝えていきます。そして、もし、一度でも手を出さずに解決できた時は、「今、きちんと口で伝えられていたね。見ていたよ!」と、正しい行動を認める声かけをすることを忘れないようにしましょう。
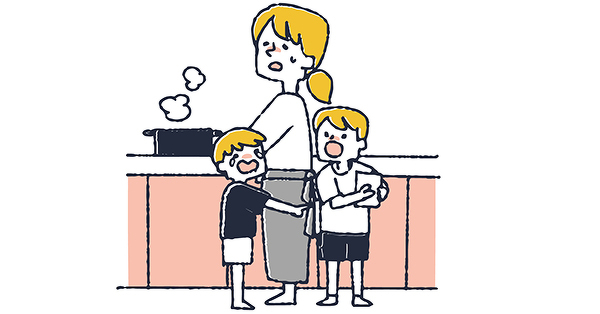
Q 幼稚園に行き始めて、他の子と比べて、娘ができないことが目につき、イライラしてしまいます。
A 凹凸があるから社会で共存できる
集団生活が始まると、今までは自分の子どもしか見ていなかったのに、他の子のことが気になってしまうことがありますよね。これは前回の記事でもお伝えしたように、「こうでなければ!」というフレームを強く持ち過ぎないことで、ネガティブな感情をコントロールすることができます。
あとは、できないことに目が行きがちですが、できることにも目を向けてみましょう。
仕事に置き換えてみると、話すのが得意な人、書くのが得意な人、作るのが得意な人、そのみんなが力を合わせてひとつのものを作っていますよね。話すのが得意な人は、作ることは苦手かもしれません。物事は一面だけではなく、多面があります。さまざまな凹凸があるから、社会で共存することができるのです。
オール5を目指すのではなく、自分の子どもができているところを認めてあげるようにしましょう。
イライラしたり不安になったり、ネガティブな感情は自然なこと

育児をしていると、子どものことを思うあまり、イライラしたり、不安になったり、ネガティブな感情が芽生えることはよくありますよね。しかしそれは、子どもがいてくれて幸せ、楽しいと思うポジティブな感情が芽生えるのと同じくらい自然なことです。
親である私たちも自分の感情と向き合いながら、自立に向かう子どもを支えていきたいですね。
写真・イラスト:PIXTA
監修:モンテッソーリ教師あきえ
国際モンテッソーリ教師ディプロマ(AMI)、保育士、幼稚園教諭。
公立の幼稚園教諭をしていた頃、日本の一斉教育に疑問を抱きモンテッソーリ教師に。現在は「子どもが尊重される社会」を目指して、モンテッソーリ教育に沿った子どもや子育てについての発信、オンラインスクール「Montessori Parents」の運営、ベビーブランド「mu ne me(ムネメ)」ファウンダー、オンラインコミュニティ「Park」を主宰。
◆「Montessori Parents」
◆「mu ne me(ムネメ)」
◆「Park」
年齢別おすすめ絵本を紹介