
カラフルだったり、巨大だったり、世界中には変わった昆虫も存在しますが、この連載で取り上げるのはあえて「身近な昆虫」です。「知っているつもりのあの昆虫に、こんな姿が!」という新しい感動が巻き起こること間違いなし! 知識やトリビアはもちろん、実際に観察できる場所、探し方も紹介します。夏休みの自由研究にも役立ちます!
※ためし読みでは、本書の内容の一部を抜粋してお届けします。
★その他の昆虫はこちら から
カブトムシの角ができる驚きの仕組み
カブトムシのオスの立派な角はどうやってできるか知っていますか? 幼虫には角はありませんよね。なんと、蛹になってからわずか100分で角ができてしまうのです。最近の研究で、カブトムシの角ができる仕組みが明らかになってきました。じつは幼虫の段階で、すでに角の素になる「角原基」と呼ばれる蛇腹を折りたたんだような組織がカブトムシの頭の中にはあるのです。
蛹になると、その角原基に体液が流れ込むことで風船のように膨らみ、10倍の長さに伸びていきます。
しばらくすると、角の先端部分の4か所が固まり、残りの部分はしぼんでカブトムシ特有のかっこいい角の形ができあがっていくのです。
カブトムシの角は、これまで長い時間をかけて進化してきました。目的はオス同士の戦いに勝つためです。角を相手の体の下に入れて投げ飛ばしやすいように、先端が広がって進化したといわれています。
成虫になるまでの変化を見てみよう

一生の約8か月を幼虫として過ごす
カブトムシの幼虫は土の中で過ごすので、冬眠のような形で越冬も可能。
この間は腐葉土などを食べて育ちます。このころには頭部には表皮組織が見られます。

遺伝子が働き角の素が活発に
8か月が過ぎると、その後5.5日で前蛹(蛹になる前の状態)に。
幼虫期から見られた頭部の表皮組織でオスの特徴をつくる遺伝子が働き、これにより角原基と呼ばれる角の素ができます。
頭部に空気が抜けた風船のような袋状のものがコンパクトに折り込まれているため、表面にはしわが多くあります。
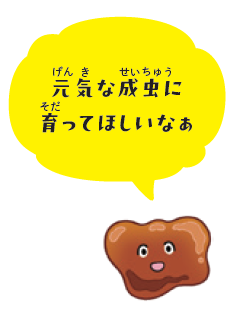
<豆知識>
日本全土に生息(北海道は人為分布)し、沖縄には固有亜種のオキナワカブトムシが生息します。成虫は里山のクヌギやコナラなどの樹液を好み、幼虫は腐葉土、発酵が進んだ牛糞の中で見つかります。
カブトムシの角ができるまで
角で戦うカブトムシの必殺技
角を相手の下に差し込みすくい投げ
頭の角を相手の体の下に入れ、すくい投げするようにして相手を投げ飛ばすのが得意技。よく見ると、角を差し込むときには自身の前肢をたたみ、姿勢を低くしていることがわかります。

角を相手の体の下に差し込むように入れています。
角と胸の角を使って相手を挟み、動けなくすることもできます。挟む力が強いと、相手の体に穴が開いてしまうことがあります。
この連載を読んでくれた大人の方へ
昆虫に興味を持ったら、お子さんたちに自然の中で過ごす時間を増やしてあげてください。初めて見る生き物や美しい風景が心に深い印象を与え、自己肯定感を高める要素となります。研究によると、自然環境での体験はストレスを軽減し、心理的な健康を促進する効果があることが示されています。
子どもたちが自らの好奇心を持ちながら事象を探求し、学ぶプロセスを通じて、子どもたちが自らの足で歩み、世界を探求する力を育まれることを願っております。
好評発売中!『すごすぎる身近な昆虫の図鑑』
- 【定価】
- 1,430円(本体1,300円+税)
- 【発売日】
- 【サイズ】
- 四六判
- 【ISBN】
- 9784046065841


















