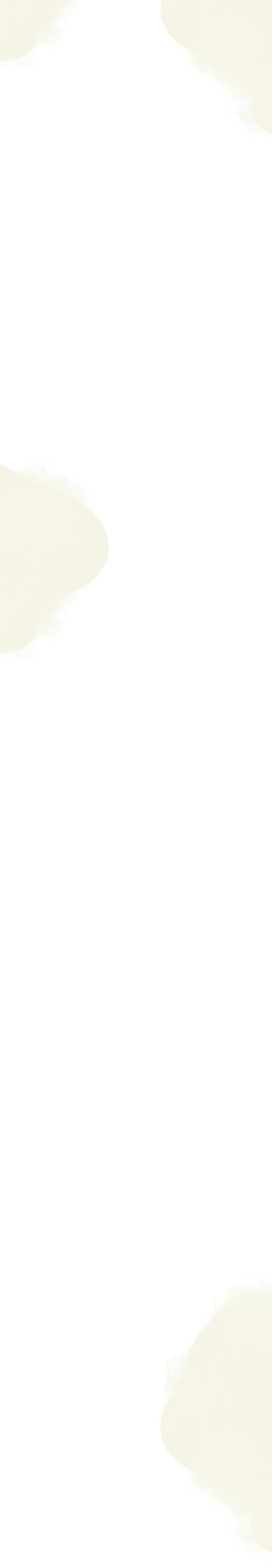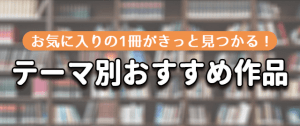受賞多数!! 絵本『わすれていいから』大森裕子さん アトリエ潜入インタビュー! 今すぐDLしたい『巣立ちカレンダー』を期間限定配布中!

第17回MOE絵本屋さん大賞2024第2位、キノベス!キッズ第3位ほか、たくさんの方々に支持されている絵本『わすれていいから』。色鉛筆による多彩なニュアンスが魅力の絵本です。今回は、著者である絵本作家・大森裕子さんのアトリエにお邪魔して、愛用している道具や絵本づくりについてお話を聞きました。また期間限定でオリジナル「巣立ちカレンダー」がダウンロードできます! ぜひ記事を最後までチェックしてみてくださいね。
650色の色鉛筆で広がる世界
アトリエに入ってすぐ目に飛び込んだのは、整然と並べられた色鉛筆の数々。大森さんは、ホルベインの『アーチスト色鉛筆150色』と、フェリシモの『500色の色えんぴつTOKYO SEEDS』の2種類を使用しています。
「色鉛筆は、絵具のように物理的に色を混ぜ合わせることは基本はできませんが、紙の上に異なる色を重ねることで、さまざまな色味や深み、ニュアンスを表現できる画材だと思います。たとえば赤と青の2本でも、赤を先にのせてから青をのせるのと、青を先にのせてから赤をのせるのでは違う色になりますし、筆圧やタッチによってもまったく異なる色や質感が出せます」

ホルベインの『アーチスト色鉛筆150色』

フェリシモの『500色の色えんぴつTOKYO SEEDS』
もともとホルベインの150色の色鉛筆だけを長く使い続けていた大森さん。人伝いに500色の色鉛筆の存在を知ったあとも、色鉛筆の数を増やすという選択肢はしばらく考えなかったといいます。
「150色あれば、重ねることでどんな色もニュアンスも表現できるし、そうしたほうがいい。色数を増やすのはどこか邪道だと思っていました。そんなとき、知人から『150色でそれだけのことができるなら、500色の色鉛筆が加われば、さらに細やかでもっと複雑な表現ができるんじゃない?』と言われて、ハッとしました。
というのも、今まで色の組み合わせや塗り方、塗る順番など工夫していたものの、本当に微妙な差なのですが、150色のなかに欲しい色がなくてほかの色をかわりに使った結果、うまく描けなくて違和感を感じていたことが何度もあったのです。そうした違和感を無視していた自分に気づいて、500色の色鉛筆も使うようになりました。いまは合計650色の色鉛筆を使っています。一色で描くときも、色を重ねるときも、使いたいぴったりの色があるので、迷いなく手が動きます」
画材は「パートナー」
「画材は“パートナー”です」と大森さん。色鉛筆は基本的に手で削り、長さが6〜7センチになったらペンホルダーをつけて使います。
「色鉛筆は、私にとって手の延長のようなもの。色鉛筆の先端は、手の感覚をおろす最後の部分なので、自分が思うような角度や丸みになるように、こまめに手で削って調整しています。手で削ることにこだわりすぎて左手が腱鞘炎になったことがあったので、最近は自動鉛筆削り機も導入して、使い分けています」

芯の先をすぐに調整したいので、手元でこまめに削る
「ペンホルダーも、欠かせない道具のひとつです。私が愛用しているのは『ヘルベチカ・ペンシルエクステンダー』です。短くなった色鉛筆を入れて、キュッキュッと締めて使います。私が知っているものの中では最高のホールド力です。持ちやすく、手が痛くなりづらいですよ」

左のペン立てに入っているのが「ヘルベチカ・ペンシルエクステンダー」
短くなった色鉛筆は、デスクに置かれたガラス瓶へ。絵本作家として色鉛筆を使い始めて以来、1本も捨てたことがないそうです。はじめて購入した色鉛筆も、ガラス瓶の中に入っているのだとか。「短くなった色鉛筆がかわいくて、捨てられなくて。瓶に入れておいたらどんどんたまって、ますますかわいくなりました」という言葉から、大森さんの色鉛筆への愛情が伝わります。
「色鉛筆は、どの色もストックがきれないように気をつけています。うっかりストックがきれてしまった緊急事態には、ガラス瓶の中から同じ色を探して使うこともあります」


小さくなった鉛筆たちは、ガラス瓶に入れて保管
上の写真の下に並んでいる、5本の白いちび色鉛筆。一見、同じ色に見えるかもしれませんが、じつは3種類の色鉛筆が混在しています。①、③、④は、ホルベインの「ソフトホワイト」、②はホルベインの「ホワイト」、⑤のちび白鉛筆は白ではなく「ウォームグレイ」。こうした色鉛筆を、どのように使い分けているのでしょうか?
たとえば「白」という色について、大森さんはさまざまな表現方法を使い分けていると話します。
「色鉛筆で何層にも色を重ねていると、あるところから色がのらなくなります。そこにハイライトとしてホワイトをのせても、つるつるすべってのりません。そんなとき、油分が多いソフトホワイトなら、色をざらりとのせることができます。ただ、ソフトホワイトは油分が多いぶんやわらかいため、たとえば猫や犬の目の輝き、細かい毛などを1本1本描くのには向きません。そういう時は、色鉛筆で描いた上からアクリルガッシュという絵具の白で描いています。
また、紙の白を計画的に残すように描いて、明るさを出すこともあるそう。紙も画材のひとつとして、色鉛筆をどう見せたいのかを考えて選んでいるといいます。
『わすれていいから』を描くにあたり、紙も一から選びました。これまで細密な表現をするためにきめ細やかな紙を使うことが多かったのですが、『わすれていいから』にはタッチの勢いや線の動き、はやさをとらえる紙が合うと思い、ややざらっとした質感の『ウォーターフォード』という紙を選びました」
もっと知りたい、仲良くなりたい気持ちで描く
大森さんは、いい絵が描けたとき、独特の感覚になるといいます。
「いい絵が描けたとき、描画した絵の部分じゃなくて、何も描いてないまわりの紙の白がぼんやり光って浮き上がって見えることがあります。そんなときは、少なくとも自分の中に『うまく描かなくちゃ』とかいうエゴはない状態なんですよね。
『わすれていいから』を描いているときは、物語の男の子と猫に教えてもらうような気持ちで描いていました。男の子と猫がご飯を食べて、勉強して、遊んで、泣いて、笑っている空間がパラレルワールドのように存在していて、その世界に私が入れてもらい、会話するような気持ちで描きました。子どものころ絵本を読んで、その世界に入り込んだ感覚を味わったことがある方もいるかもしれませんが、それに近い感覚です。子どものころから空想を膨らませて遊ぶのが好きでした。そんなふうに男の子と猫の空間や時間に入り込むと、とても心地よくて、手が自然に動き出しました。作品をつくるときは、描いている対象をもっと知りたい、仲良くなりたいという気持ちで描いています」
『わすれていいから』オリジナル巣立ちカレンダーポスターをプレゼント!
子どもが巣立つまであと少し…。
そんな残り少ない日を大切にできるよう、オリジナルの巣立ちカレンダーを作りました。2026年1月〜3月の3カ月のカレンダーは、卒業、就職などで巣立つまでの残り時間を刻みます。
送り出す人も、新しい一歩を踏み出す人にも使ってほしい 、未来への一歩を応援するカレンダーはプレゼントにもぴったり。ぜひダウンロードして飾ってくださいね。

取材・文:三東社 撮影:澤木央子
【作家プロフィール】
大森 裕子

神奈川県生まれ。東京藝術大学大学院在学中よりフリーランスで活動をはじめる。『おすしのずかん』『パンのずかん』『おかしのずかん』『ねこのずかん』『なにからできているでしょーか?』「へんなえほん」シリーズ(白泉社)、『ぼく、あめふりお』(教育画劇)、『ちかてつ もぐらごう』(交通新聞社)など著作多数。