はじめに 『今は子育て三時間目』ためし読み 第1回
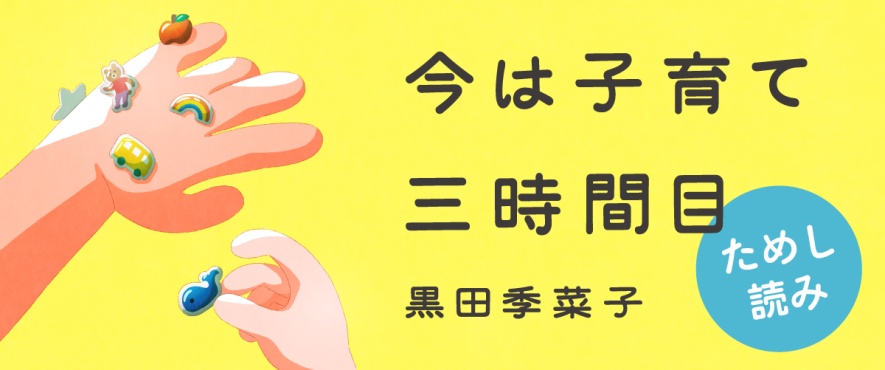
2025年、児童文学の小川未明文学賞で大賞を受賞した黒田季菜子さん。
いま注目の作家による、3人の子どもたちとその周りで起こる楽しくて、切なくて、なつかしくて、うれしいあれこれ…。
ちょっと大変な疾患の子もいるけれど、「ふつうの日常」をみずみずしく透明感あふれる筆致でつづった、珠玉のエッセイ集です。
※本連載は『今は子育て三時間目』から一部抜粋して構成された記事です。
はじめに
最近、外を歩いている時、「なんだか顔に見覚えのある青年が前から歩いてくるなあ」と思ったらそれが自分の息子だった、ということが三回ありました。
当たり前のことですが、子どもは時間が経てば大きく成長していくもので、親であるわたしも子どもの健やかな成長を願って、日々を過ごしているはずなのですけれど、子育ても中盤に差し掛かった最近は、わたし自身の(うちの子は、いまこのくらい)というイメージと、現実が大きく乖離し始めてきているような気がします。
我が家は二〇二五年現在、一番上の子どもが高校二年生になり、とうとう背丈・体重ともに母親のわたしを追い抜きました。細身ながら肩幅は青年らしく大きくがっしりとして、幼稚園から小学生の高学年まで、クラスで一度も前ならえをする機会を与えられなかった子には、もう見えません。
二番目の子は中学二年生。何故だかわたしよりも、わたしの実姉に外見がそっくりな彼女は、小柄な姉と殆ど同じ身長で、ついぞ親のわたしの背丈を抜く事はありませんでしたが、それでもちゃんと大人サイズの、十四歳になりました。
三番目の末っ子はとうとう小学生、それも今や二年生になり、以前はまるで羽二重餅のようだと評された両頬がどんどん細く、そして過去一度、病床で諸般の事情により一部が禿げてしまったことのある髪は、どんどん長く、ポニーテールを揺らして歩くその姿は、外見だけはもう立派に少女です。
月日は必ず過ぎ去るもの、時間はさかさまには行きません。わたしはどんどん老けてゆくし、季節はあっという間に巡ります。
それぞれがまだ小さな赤ちゃんだった頃は、こんなか弱くて放っておいたら直ぐに死にそうな弱々しい生き物を二十四時間守り育てるなんて、ホンマにとんでもない、早く大きくなって頂戴よと思っていたのに、いざ子ども達が自分の足で堂々、歩きはじめると、あのよちよち歩きの後姿を追いかけた日々が途端に恋しくなるのだから、親なんて勝手なものです。
とはいえ、ちょっと油断すると通学証明書を無くしてくれたり(高校生)、電子レンジがバクハツしそうで怖いと言ったり(中学生)、「今日の宿題が一体何なのかわからない」とランドセルを逆さに振ったりする(小学生)、それなりにしっかりしていない、年よりやや幼い気のする子どもらを育てている今、この現状を本書の担当編集者である川田さんは
「子育て、三時間目ですね」
このように仰いました。言い得て妙というか、ほんまにその通りやなと思います。そしてそれがそのまま、本書のタイトルになりました。
それは、一時間目程の緊張と新鮮さはないけれど、四時間目程は気が抜けないし、下校まではまだまだかかる、そういう時間。
その上わたしは、まだあと十年くらい、登下校を共にしなくてはならない(かもしれない)、医療用酸素を持ち歩く末っ子がいるもので、仮に今が子育ての三時間目といっても下校時間が一体いつなのか、未だ皆目わかりません。もしかしたら七時間目があるのかもしれないし。
そんな日々の中で、わたしはずっと文字を書き続け、去年はとても有難いことに児童文学を対象にした文学賞をいただきました。授賞式のあった新潟県上越市は大阪から遥か遠く、それでも故郷である富山によく似た、静かでとても美しい街でした。
雪が降ればきっともっと美しい街でしょう。三時間目には良い事も時々あるのです。
さて、一体いつまでが三時間目で、いつ下校時間なのか、少しもわからない毎日に、わたしは毎日文字を書き、子ども達に食事を作り、掃除をして洗濯をして、また文字を書いて暮らしています。
きっと、あと十年くらいはこんな毎日が続いていくでしょう。そういう毎日のことと、たまに思い出す昔の事と、そして実家のいぬの事なんかを、この本には書きました。
最後のページを捲るその時まで、のんびりお付き合いいただけたらと思います。
黒田 季菜子
子どもとの時間は、長いようで意外とあっという間。
子育てをしたことがある人ならだれでも感じるせつなさ、なつかしさ、淋しさ……この本にはそれらが宝物のように詰まっています。
【書籍情報】

























