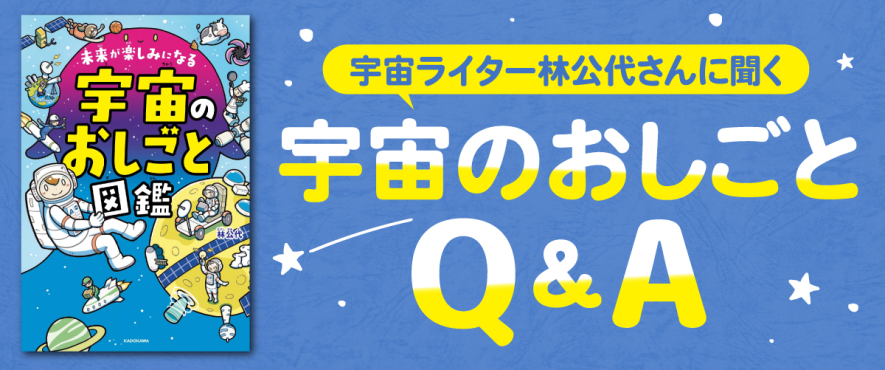
宇宙に関するおしごとや、宇宙でのくらしについての質問に、宇宙ライターの林さんがお答えします!
この記事では、『未来が楽しみになる 宇宙のおしごと図鑑』(著:林公代)発売記念イベントでよせられた質問と回答を、本の中身をお見せしながら紹介します。
ブラックホールを研究するおしごとをするには、どうしたらいいですか?

林さん:
質問ありがとうございます。天文学者にもいくつか種類があるんですね。
ブラックホールって、アインシュタインの理論からある物理学者の人が存在を予言したんですけれど、そうやって、スーパーコンピュータとかを使って理論的に考える「理論天文学者」という種類がまずひとつあります。
それから、「観測天文学者」っていう人がいます。
たとえば理論天文学者が「こういう条件で、こういうところを探せばブラックホールが見つかるかもしれない」と考えた理論に基づいて、実際に望遠鏡を使って観測する人が観測天文学者です。
ブラックホールは、「イベント・ホライズン・テレスコープ」っていう、世界中の理論天文学者たちや観測天文学者たちが協力して、電波望遠鏡をつなぎあわせて地球サイズの大きい望遠鏡をつくるプロジェクトで観測することに成功したんですね。
ですから、観測をする天文学者になるか、理論的に考える天文学者になるか、大きく考えるとその二通りの方法がありますけども、どちらに進むにしても大事なのは算数ですね。算数をがんばること。あと理科(物理)をがんばること。
質問者:
社会?
林さん:
社会もいいですね。どの勉強も大事なんだけど、まずは算数と理科(物理)の知識は天文学者になるためには必要になってきます。ですからまず勉強ではそれをがんばること。
それから、観測天文学者の本間先生に伺った話では、今の観測っていうのは一つの国ではできないんですね。いろんな国と協力しながら、みんなが得意なことを持ち寄っていろんなアイデアを寄せ合って作らないといけないので、いろんな人と協力すること。チームワークっていうのが、ブラックホールに限らず、宇宙ステーションに行くにも、月に行くにも、どんな分野にも必要になるので、チームワークを磨くこと。
それから本間先生が強調されたのは、とことん追求する力。なにか興味を持ったらそれを徹底的に調べること。だからブラックホールが好きだったら、ブラックホールについていろんなことを調べたり、あるいは聞きに行ったり。今日もイベントに来ていただいて質問していただいたので素質は十分だと思いますけれども。
黒田さん:
ね、すばらしい。
林さん:
「突き詰める力」っていうのが大事ですよっておっしゃっていたので、がんばっていただきたいなと思います。
質問者:
ありがとうございます!
林さん:
どうもありがとう!
第4回に続く
深宇宙展グッズ&宇宙図鑑があたるキャンペーン実施中!
日本科学未来館で開催中の特別展「深宇宙展」のオリジナルグッズと『未来が楽しみになる宇宙のおしごと図鑑』または『角川の集める図鑑GET!宇宙』のセットが抽選で計6名様にあたるキャンペーンをXとInstagramで実施中!
イベントの様子を動画でお届け!
たくさんの質問が飛び出した『未来が楽しみになる 宇宙のおしごと図鑑』の発売記念イベントの様子は、YouTubeチャンネル「KADOKAWA児童図書チャンネル」でご覧いただけます。ぜひお楽しみください♪
▼14:00~の回
▼16:00~の回



















