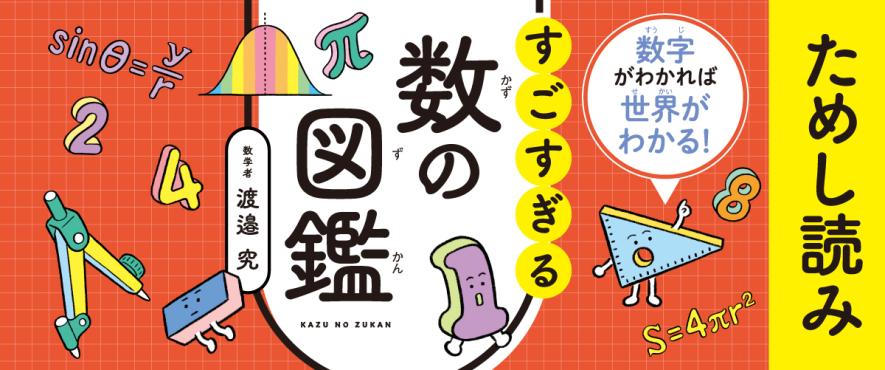
普段の生活のさまざまなところで使われている数。
『すごすぎる数の図鑑』では、学校の算数や数学が苦手だった人も、読むと思わず「そんな仕組みがあったのか!」「こんなところにもつながっているのか!」と感じる数のエピソードを集めました。
たくさんのイラストとわかりやすい説明があるので、もちろん小学生でも大丈夫。さあ、一緒に数の不思議を体感してみましょう!
※本連載は『数字がわかれば世界がわかる! すごすぎる数の図鑑』から一部抜粋して構成された記事です。
<すごすぎる図形>円の面積はなぜ「半径×半径×円周率」なのか?
円は、私たちの生活の至るところにあります。たとえば、マンホールの蓋は円の形をしています。四角い蓋は斜めにすると穴に落ちることがありますが、円は直径がどこでも同じなのでどんな向きでも落ちません。そもそも円とはどんなものでしょう? 円は平面上で定点Oから同じ距離r(rは正)にある点の集まりです。点Oを円の中心、rを円の半径といいます。
糸と定規を使って図1、2の半径1㎝と2㎝の円の円周の長さを測ってみてください。円周の長さを直径の長さで割った値はどちらも3に近い値になりませんか? どんな円も相似なことから、円周の長さを直径で割った値は円の大きさによらずに一定であることが知られています。この値を円周率といいます。このことから、円周の長さは(直径)×(円周率)と表されることがわかります。それでは円の面積はどのように表されるでしょうか。左のページで、円をたくさんの細かい扇形に切り分けて、円の面積を求めてみましょう。
豆知識
周の長さが同じ正三角形、正方形、円のうち一番面積が大きくなるのはどれでしょう? 周の長さをとするとそれぞれの面積は約1.90、約2.47、約3.14となり、円の面積が一番大きくなります。これを等周問題といいます。
数について知ることで、身の回りにあるものの多くが数の仕組みや計算で成り立っていることがわかるのではないでしょうか。
数式やルールを全て理解する必要はありません。この本を通して、「こんなところにも算数や数学がつながっているのか」と気づき、次の学びにつながることを願っています。
- 【書籍情報】


















