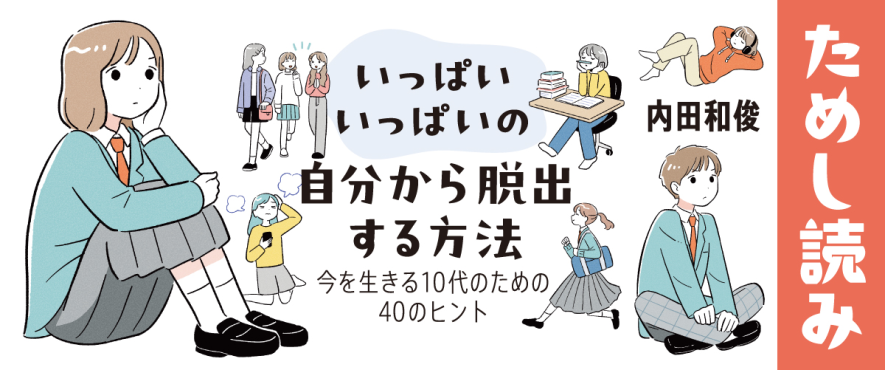
「友達をつくるのが苦手」「将来がなんとなく不安」「なんにもやる気が起きない」……。この本はそんな悩みで「いっぱいいっぱい」になっている中学生・高校生のための「毎日のお守り」です。「学校生活」「親」「友達」「自分」の4つのカテゴリーの悩みに寄り添う内容で、解決のヒントが見つかる1冊です。
※本連載は『いっぱいいっぱいの自分から脱出する方法 今を生きる10代のための40のヒント』から一部抜粋して構成された記事です。一部写真は本には掲載されていません。
苦手科目って、どう克服したらいいの?
「苦手科目を、どう克服したらいいですか?」
これは私が塾や予備校で教師をしていた頃、生徒本人だけでなく、保護者からも多かった質問です。
勉強だけでなく、スポーツや習い事に関しても共通して言えることなのですが、弱点克服を最優先課題にしてしまうことは、日本の教育における悪しき伝統のような気がしてなりません。
たいてい、好きな科目は得意科目ですし、嫌いな科目は苦手科目ですよね。
食べ物を筆頭に、嫌いなものを好きになるのは至難の業です。無理強いされてしまったら、よけい嫌いになってしまいます。
弱点克服よりも長所伸展を意識して、得意科目を伸ばすことを、まずは優先しましょう。

画像提供:PIXTA
苦手科目克服のファーストステップ
私が提案する苦手科目の克服方法をご紹介します。
まず、苦手科目に費やす時間を増やす必要はありません。それよりも、得意科目に費やす時間を増やし、今より10点~15点アップを目指しましょう。
このとき、取り組む順番が大事です。
まずは、得意科目から取り組んでください。食事で言えば、好きなものから真っ先に食べちゃいましょう。
得意科目から取り組めば、やる気と集中力、そして持続力が確実に高まります。
こんなふうに、まずは勉強に対するモチベーションが高まっている状態にして、「そのついでに」苦手科目に取り組むくらいの感覚でいいのです。
実は「動いている物体は動き続ける」という「慣性の法則」は、物体だけでなく、私たち人間の感情や行動にも当てはまります。
初動に大きなエネルギーが必要ですが、一度動き出しさえすれば、そこから先は意外とスムーズに進むのです。
ですから、得意科目→苦手科目の順で取り組めば、得意科目の勢いとプラスの感情を、そのまま苦手科目に引き継ぐことができます。苦手科目が意外と苦にならず、はかどることとなるでしょう。
一方で、苦手科目→得意科目の順で取り組んでしまうと、苦手科目に伴う嫌な感情が得意科目にまで引き継がれてしまいます。得意科目が思ったほどはかどらないなんてことも起こりがちです。
この取り組む順番は、とっても重要なポイントになります。
長所伸展の嬉しい副産物
これを実践してもらうと、とても不思議な現象がよく起こりました。
得意科目ほどの上昇はありませんが、なぜか苦手科目も得意科目に連動して、テストの点数が上がるのです。
一例ですが、得意科目の英語が七十五点から八十八点に上がると、苦手科目の数学も四十五点から五十二点に上がったというような現象がよく起こりました。
もちろん、これは得意科目から取り組むという順番が生み出した効果です。
得意科目の上昇は、さらなる効果を生み出します。
意識が変わるのです。
先の例で言えば、英語が七十五点から、コンスタントに九十点前後を取れるようになると、入学できる進学先のレベルが上がります。
すると、数学が五十点前後のままでは、さすがに合格は無理だよねということになってきます。
ここから苦手科目に対する自発性が芽生えるのです。
やらされ感でイヤイヤ苦手科目に取り組むのではなく、必要に迫られて自分の意志で苦手科目に取り組むこととなります。
これが結果的に、苦手科目の克服へとつながっていくのです。
まとめ
▶ まずは得意科目の勉強時間を増やし、得点アップを目指そう。
▶ 苦手科目は得意科目のあとで取り組むと、勉強がはかどる。
▶ 得意科目の点数が上昇すると、苦手科目への自発性が芽生える。
書誌情報
著者: 内田 和俊
- 【定価】
- 1,540円(本体1,400円+税)
- 【発売日】
- 【サイズ】
- 四六判
- 【ISBN】
- 9784046072399
















