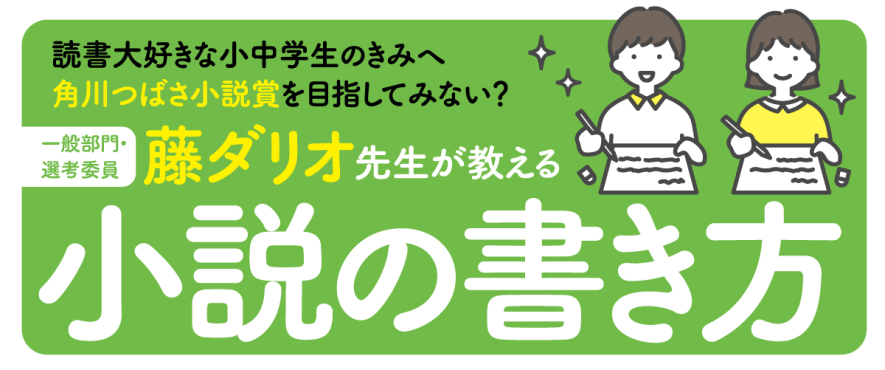
本を読む子なら一度は「いつか自分でも書けたらな」って考えたことがあるのでは? 今はまさに夏休み。そして「角川つばさ文庫小説賞〈こども部門〉」の受付期間中!……でも、なにを書けばいいかわからない? そこで〈一般部門〉の選考委員で、つばさ文庫の大人気シリーズ「絶体絶命ゲーム」の作者・藤ダリオ先生から、ヨメルバのために特別に、小説の書き方を教えてもらう連載です!(全3回更新)
はじめに
みんな、こんにちは。
小説家の藤ダリオです。
前回から小中学生のみなさんに「小説の書き方」を伝えるこの講座をはじめました。
今回はその2回目です。
まだ第1回を読んでいない人は、こちらからどうぞ。
ちなみに、昔、映画界でこんなジンクスがあったのを知っているかな?
「ヒットした映画の2作目は、失敗作になる」
映画「ジョーズ」「エクソシスト」「スピード」など、1作目は大ヒットしたのに、2作目が失敗作に終わった映画は、けっこうあるんだよ。
ぼくの「小説の書き方」の2回目はそうならないように、がんばって書くね。
(ちなみに、2作目の評価が高かった映画もあります。
「007」「エイリアン」「ターミネーター」で、これらは今もシリーズがつづいているよ)
1)物語は3つの部分に、わけて考えよう
物語をつくるときには、いわゆる「起承転結」にわける考え方があります。
これは、小学校の授業でもならいますね。
起承転結は4つのようですが、「起」「承」「転・結」と「転」と「結」を1つとして、3つだと考えて、三幕構成(設定・対立・解決)と考えることもできます。
「あれ? なにか、いきなりむずかしくなったぞ」と思ったかな?
かんたんに言うと、前半・まんなか・後半ということです。
前半は、第1回に書いた「書き出し」の部分です。
読者が読みだしたとき、「この話、おもしろそうだ」と思わせる、つかみの部分です。
前半がおもしろくても、まんなかで中だるみすると、すぐにあきられてしまいます。
そこで、「まんなか」でも、おもしろくするということです。
言うのはかんたんですが、実はこれがむずかしいんです。
読者は小説を読むとき、「これは、どういう物語なのか?」「主人公はどういう人物なのか?」「主人公のまわりにいる人はどういう人なのか?」などの興味を持っています。
前半は、そのあたりがおもしろく書かれていれば、満足します。
次に、読者は「このあとはどうなるのだろう?」と期待します。
それが、「まんなか」になるわけです。
2)まんなかは「おもいっきり」やっちゃえ!
ここからが、本番です。
みんなは考えた話を、思いきり書きたかったはずです。でも、書き出しは読者の興味を引くように、書きたい気持ちを少しおさえていたと思います。
まんなかでは、それを解放します。
自分の書きたかった話を、ここで思う存分に書いてください。
ここで、ぼくの書いた『絶体絶命ゲーム 1億円争奪サバイバル』を例に説明しましょう。
前半では、どうしても、お金の必要な登場人物たちが「絶体絶命ゲーム」に集まります。
特に、滝沢未奈は妹の病気の手術費が必要で、どうしても1億円がほしいです。
このあとがまんなかになります。
お金がほしくて集まった人たちが、なにをやるのか?
作者のぼくは、ここで思いきり書きたいことを書きました。
登場人物に奇妙なゲームをやらせて、それぞれの人間性を出していきます。
ゲームに勝つために、人をだまそうとするもの、逃げだすもの、裏切るもの、戦いを楽しむもの……などです。
ここで、ぼくは少し心配になりました。
魅力的な人物をたくさん出したから、このあと、どうしたらいいかな……?
みんなも、まんなかで話をおもしろくできたら、このあと後半(結末)が心配になるはずです。
それでも、後半(結末)のことは、ここでは考えなくていいです。
いきおいのまま、書きたいことを書いてください。
そう言われても、
「起承転結の『転結』、三幕構成の『解決』にあたる結末はどうなるの? 心配だよ」
そう思う人がいるかもしれません。
作者がそう思いながら書くということは、読者もそう思うわけです。
これが、「ハラハラする部分」になります。
「おもしろいけど、この話ってどうなっちゃうの?」
読者にそう思わせたら、作者の勝ちです。
3)それで、最後は……?
小説は、書き出しが重要です。
でも、最後も重要なんです。
「読後感」という言葉をきいたことがあると思います。
読者が読んだあとに、どう感じるかということです。
書き出しがおもしろくても、まんなかがおもしろくても、最後がおもしろくないと、読後感は最悪になります。
書き出しはまあまあで、まんなかもまあまあで、最後がおもしろいときはどうでしょう?
読後感は、悪くないはずです。
「この小説、なかなかおもしろかった」となります。
もちろん、書き出しから最後までおもしろい小説が書けるのが、ベストです。
でも、すべてがおもしろいのは、なかなか書けません。
小説の感想は、読み終わったあとに感じたものです。
つまり、読後感がいいと、読者は「その小説はいい小説だった」と感じるのです。
それだけ、起承転結の「転結」は重要になります。
だから、まんなかで思いきり書きたいことを書いても、結末は考えておいたほうがいいです。
もっと言うと、小説を書きだすとき、最後の部分、特に結末は考えておくのがいいです。
「まんなかで書きたいものを思いきり書けと言っておいて、結末は最初に考えておけって、矛盾しないかな?」
そう思う人がいると思います。
ここで言う結末は、「とりあえずの結末」で、正式なものではありません。
まんなかで思いきり書いて力を使いはたして、もうなにも考えられない。
「書きたいことは書けたから、もうこれで終わりでいいよ」と中途半端に終わると、読後感は最悪になります。
例えば、きみは、町のはずれにあるお化け屋敷に冒険にいく話を考えるとします。こわい妖怪やおばけがたくさん襲ってくる。みんなは助け合いながら逃げる。でも、逃げられない。
書いているうちに、結末が思いうかぶと思ったけど、いいアイディアが出なかった。
そのときのために、「とりあえずの結末」を用意しておくわけです。
例えば、「死んだおじいちゃんが助けにきて、逃がしてくれる」という「とりあえずの結末」を用意しておくんです。
そうすると、結末のアイディアが浮かばなかったとき、「とりあえずの結末」が役に立つわけです。
まんなかを書いたあと思いきり、新しい結末を思いつくこともあります。
そのときは、「とりあえずの結末」を「新しい結末」に変更すればいいんです。
小説の作者は、きみです。
その小説の中では、きみがルールブックで、神です。
「結末は『とりあえずの結末』ではなく、『新しい結末』を変更します」と言っても、反対するものはいません。
だから、結末は「とりあえずの結末」でいいので、書き出す前に決めておきましょう。
そして、「新しい結末」が浮かんだら、変更しましょう。
小説の印象は、結末で決まります。
その小説で強くうったえたいテーマのある人は、結末しだいで、テーマが伝わらなくなることがあるので、結末は慎重に決めてください。
4)どれくらいの枚数を書けばいいのか?
書き出し、まんなか、結末まで書いて、ようやく小説が完成しました。
でも、枚数の制限はないのかな?
友人に読ませたり、学校で発表するなら、何枚だって問題ないでしょう。
でも、小説賞に応募するときは、応募規定があります。
角川つばさ文庫小説賞の場合は、400字詰原稿用紙で30枚までです。
くわしくは、ホームページを見てください。
https://tsubasabunko.jp/award/kodomo.html
締め切りや枚数制限などの応募規定は、必ず守りましょう。
そうじゃないと、せっかく書いた小説を読んでもらえないこともあります。
それから、コンクールに応募するときは、書きっぱなしではなく、必ず読みかえして、直すべきところがないか、考えましょう(「推敲する」といいます)。
パソコンで書く人だと、修正は簡単だと思います。
原稿用紙に手書きで書いた人は、修正箇所を消しゴムで消したり、二重線で消して、その横に、新しく書き足してください。
小説には、その物語にあった長さ(枚数)があります。
たくさん書いたほうが有利だとか、短いと不利だとかは関係ありません。
枚数に関係なく、長いと感じる小説もあるし、短いと感じる小説もあります。
応募規定の枚数のぎりぎりまで書きたす必要はありません。
長く書くとそのぶん、ダラダラしてしまうこともあります。
それより、むだなところをけずる気持ちで修正するのがいいでしょう。
5)藤先生からのアドバイス!キャラクターの作り方
小説はストーリーも大切ですが、登場人物も大切です。
みんなの中には、人物のキャラクターを作るのが苦手という人もいると思います。
そういうときは、その人物の長所と短所を考えてください。
たとえば、「長所はまじめで、短所はこわがり」。
少し工夫して、長所と短所につながりを持たせることもできます。
たとえば、「長所はまじめ、短所はまじめ過ぎて、かたくるしい」とか。
長所も、度をこすと短所になることがあります。
人物の魅力は、長所よりも短所(欠点・弱点)にあります。
『絶体絶命ゲーム』の武藤春馬は、優しくて、頭がよくて、運動神経ばつぐんで、とにかく万能な少年です。
ただ、「お人よし」という大きな欠点があります。そのせいで、たびたび絶体絶命になります。
『パーフェクト・セキュリティ』の古賀快星(こが・かいせい)は、柔術の達人で、大人にも負けない無敵の少年です。ただ、弱点は血液恐怖症で血がこわくて、格闘中でも血を見ると体が動かなくなってしまいます。
春馬も快星も、短所がなかったら、こんなに苦労しないんだけど……。
でも、短所があったほうが親近感が生まれます。
みんなも、自分の書いた小説の主人公の短所を考えると、キャラクターが出るよ。
それと、主人公の友人は、主人公の欠点のカバーをする性格にするといいです。
『パーフェクト・セキュリティ』では、ヒロインの平松美月のクラスメイトで、井坂香純という子が登場します。無鉄砲な美月とは対照的に、香純は沈着冷静な性格です。性格がちがうからこそ、気が合うということもあるようで、2人は親友同士です。
香純の冷静な判断で、美月は助けられます。ただ、そのあと……。これ以上はネタバレになりますね。
6)きみの書いた原稿をみんなが待っている!
角川つばさ小説賞では、つばさ文庫をつくっている編集者たちが、みんなの小説を待っています。
ぼくが書いている『絶体絶命ゲーム』シリーズの編集者も、ひのひまり先生の『四つ子ぐらし』シリーズの編集者も、あさばみゆき先生の『サバイバー!』シリーズの編集者も、一ノ瀬三葉先生の『時間割男子』シリーズの編集者も、つばさ文庫の編集者全員が、みんなの小説を待っています。
みんながどういう小説を書くのか、作家のぼくたちも、つばさ文庫の編集者たちも、興味しんしんです。
それは、みんなの小説には、「今」のリアルな小中学生が書かれているからです。
そして、みんなの中から、将来、つばさ文庫で人気シリーズを書く作家が出てくるかもしれません(たとえば中学1年生のとき「こども部門」で入賞している七都にい先生のように!)
だから、「自分にはむりだよ……」なんて思わずに、ぜひ角川つばさ文庫小説賞に挑戦してください。
7)「読んでもらう」楽しみと喜び
最後に、小説にはたくさんの「楽しい」があるということを書きたいと思います。
小説を書くことは楽しいですが、読んでもらうことも楽しいんです。
それは、みんなの感想がきけるところです。
『絶体絶命ゲーム』『パーフェクト・セキュリティ』を書いたあと、みんなから感想の手紙やメールがたくさん届きました。
『絶体絶命ゲーム』のファンの女の子からは、クラスにも。読んでいる男子がいて『絶体絶命ゲーム』がきっかけでなかよくなりました、というものがありました。
小説には、書く楽しさ、読む楽しさ、小説を読んでいる人と友だちになれる楽しさなど……、たくさんの「楽しい」があります。
紙と鉛筆と想像力だけで、無限の楽しいがひろがります。
この夏、まずは、小説を書いてみましょう。
ぼくの講座が、みんなの役にたてたらうれしいです。
角川つばさ文庫では、夏休みの間、小・中学生のみんなの書いた小説を募集中。
くわしくはこちらを見てね!この講座を読んで、作品ができあがったら、ぜひ応募してほしいな!










