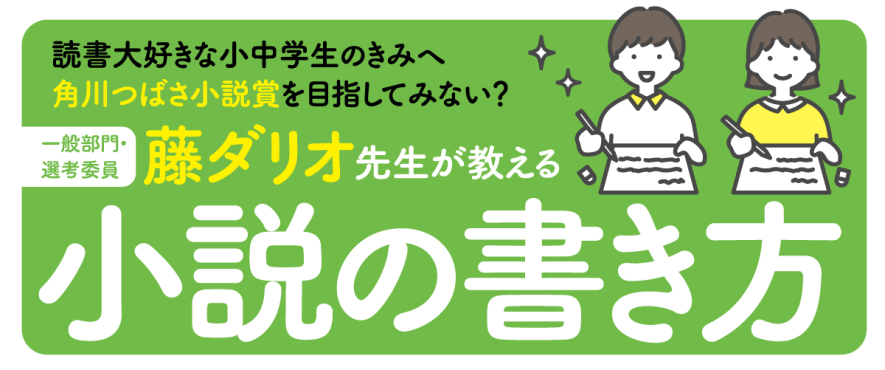
本を読む子なら一度は「いつか自分でも書けたらな」って考えたことがあるのでは? 今はまさに夏休み。そして「角川つばさ文庫小説賞〈こども部門〉」の受付期間中!……でも、なにを書けばいいかわからない? そこで〈一般部門〉の選考委員で、つばさ文庫の大人気シリーズ「絶体絶命ゲーム」の作者・藤ダリオ先生から、ヨメルバのために特別に、小説の書き方を教えてもらう連載です!(全3回更新)
はじめに
みんな、こんにちは。
小説家の藤ダリオです。
ぼくは子供のころ、国語が大の苦手でした。
小説はあまり読んだことはなく、夢中で読んだのは小泉八雲さんの『怪談』くらいです。そのころから、こわい話が好きでした。
中学生のときに映画『犬神家の一族』が公開になり、原作小説の作者である横溝正史さんがブームになったのをきっかけに、小説を読むようになりました。
それでも、小説を読むより映画を観るほうが好きでした。
そんな、ぼくがどうして小説を書くようになったのか……?
今回は、そういう話からしてみようと思います。
1) 小説、書いてみない?
今、これを読んでいるみんなは、たくさん本を読む人かな?
いつか自分でも、小説を書いてみたいと思っている人もいるのかな?
そうではなく、ぐうぜん、このサイトにきただけ、とか。
あるいは、『角川つばさ文庫小説賞の〈こども部門〉』に応募してみたいと思っている人かな?
もし、少しでも小説を書くことに興味があるようなら、ぼくがなぜ小説家になったのかという話は、参考になると思います。
ぼくが小説を書くようになったのは、大人になってからです。
それまで、国語が得意だったわけではなく、特に本をたくさん読んでいたわけでもありません。
映画が好きだったので、映画やテレビアニメの脚本家になりました。
脚本家をやっていると、ときどき、「映像にはなりにくいけれどおもしろい」という話を思いつきます。
その話をそのまま、うもれさせてしまうのは、もったいないと思いました。
それで、その話を小説として書いてみたのです。
ぼくが小説家になったきっかけは、「おもしろい話を思いついたから」です。
「それだけで、『小説』を書けるの?」と疑問に思った人もいるかもしれません。
小説の書き方を知らなかったぼくは、本棚から数冊の小説を引っぱりだしてきて、それをお手本にして小説を書きました。
見よう見まねです。
ぼくの小説の先生は、本棚にあった小説です。
最初に書いた小説が本として出版されるまでは、「小説は子供のころから本を読むのが好きで、国語の成績がいい人が書くものだ」と思っていました。
でも、最初の小説が本になり、2冊目、3冊目の本が出るようになって、ぼくの考えはかわりました。
小説は、だれが書いてもいいんです。
国語が苦手でも、読書よりゲームが好きな人でも、スポーツに夢中になっている人でも、だれが書いてもいいんです。
「文章には自信がない」という人がいるかもしれません。
でも、小説は、国語のテストではありません。
だから、文章力は気にすることはありません。
メチャクチャでもハチャメチャでもいいんです。
おもしろい、悲しい、うれしい、つらいなど、読む人が感じてくれるのが一番です。
小説を書くときに大切なのは、まわりの目を気にせず、「思いきり書く」ということです。
最初は一行のメモでいいので、ノートのあまったページに小説のアイディアを書いてみましょう。
2)でも、なにを書けばいいのかな?
それは、自由です。
そう言われても、逆に書きにくいかな?
ではたとえば、今までで一番悲しかったこと、今までで一番こわかったこと、今までで一番頭にきたこと、今までで一番うれしかったことを元にして書いたら、どうかな?
「小説」なので、実際に起きたことをそのまま書く必要はありません。
それを元にして、想像をふくらませて、話を作ればいいんです。
……そう言われても、まだ思いつかない人っていうもいるかな。
それなら、夢を元に作るのはどうかな?
みんなは、不思議な夢を見たことはない?
空を飛んだり、怪獣に追いかけられたり、デパートで豪華なスイーツが食べ放題だったり、スポーツでヒーローになったり、有名なユーチュバーになったり……。
それを元に話を作ればいいんです。
それでも、まだ思いうかばないかな。
それなら、「日ごろ思っているけど、実際にはできないこと」を、小説の中で実現させるのはどうだろう?
最高にかわいいアイドルになったり、いきなり魔法が使えるようになったり、過去にもどったり、未来にいったり、人の心を自由自在にあやつったり、小説の中ではなんでもできます。
「いやいや、せっかく書くんだから、みんなの心にうったえたい!」という人もいるでしょう。
でも、うったえたいことをそのまま書いても、おもしろくないと、みんなは読んでくれません。
そういうときは、お話の中に、うったえたいことを入れればいいんです。
「この世界の戦争がなくなればいい」とうったえたいときは、戦争のなくなった世界を書けばいいんです。たとえば、戦争がなくなった平和な世界がきたと思ったら、それは世界が滅んだ世界でしたとか……。
そんなのこわいよ、と言われるかもしれないけど、気にすることはありません。
これは、小説です。
みんながどう思うかではなく、自分がなにを書きたいかが大切なんです。
みんなが驚くようなブラックな内容のお話でも、大歓迎です。
小説は、好きなことを、自由に書いていいんです。
3) 「読ませる工夫」をしよう
「よーし、小説を書くぞ!」とやる気まんまんになったかもしれないけど、ちょっと待ってください。
書きはじめる前に、作戦を立てましょう。
作戦ってなに?
せっかく、考えた小説なので、読む人に、最後まで夢中で読んでもらいましょう。
それには、読ませる作戦が必要です。
サッカーだって、野球だって、テニスだって、バレーボールだって、作戦を立てたチームは強いです。
小説も同じです。
読者に「この小説はつまらないな」と途中で読むのをやめられたら、せっかく書いた小説がかわいそうです。
自由に書けないのか、つまらないな……。
そう思わないでください、小説はここからがおもしろいんです。
自分の考えた話で、読者を楽しませるんです。
当然だけど、読者は、あなたがどういう小説を書いたのか知りません。
小説を読む前、読者はどういうことを考えているでしょう?
この小説って、どんな話なのかな?
おもしろいのかな、つまらないのかな?
この作者は才能があるのかな?って、最初は意地悪な目で、読みはじめるかもしれません。
つまらないと思ったら、途中で読むのをやめるかもしれません。
でも、その小説がおもしろかったら、その作品は、その人にとって、一生の宝物になるかもしれない。
貴重な体験になるかもしれない。
もしかしたら、まだ世に出ていない天才小説家との出会いかもしれない。
読者は、そんなことを考えています。
読者の頭の中は、期待と不安が入りまじっています。
だから、最初からていねいに主人公の性格、この物語がどういう話かを書いていきましょう…………、というのは嘘です。
実は、ぼくは少し意地悪です。
だから、小説の中で読者に知らせる情報は、少しずつ出していきます。
読者は、読みながら「どうして?」と思わないと、興味をなくします。
でも、「どうして?」ばかりでも、興味をなくします。
「どうして?」の加減が大切です。
読みすすめるのに必要な情報を見せながらも、「どうして?」という疑問を少しずつ残してあげると、読者はあきずに読んでくれます。
4) 書き出しが、最初の勝負です
小説では、書き出しが重要です。
最初の数行で、勝負が決まることだってあります。
「これはすごい!」という書き出しができたら、大成功です。
読者は、その小説に期待して、最後まで読んでくれるはずです。
そこまでいかなくてもいいので、書き出しには工夫しましょう。
それでは、書き出しのかんたんな例を1つあげましょう。
例1
放課後、近所の公園で勇人と幸太郎はキャッチボールをしていた。
「おまえたち、なにをしている!」
近所のおじさんが、真っ赤な顔をして怒鳴りこんできた。
ここ公園は、キャッチボール禁止なのだ。
勇人と幸太郎は、あわてて逃げだす。
わかりやすい書き出しだけど、少し工夫する必要があります。
例2
「おまえたち、なにをしている!」
近所のおじさんが、真っ赤な顔で怒鳴りこんできた。
勇人と幸太郎は、あわてて逃げだした。
2人はキャッチボール禁止の公園で、キャッチボールをしていたのだ。
例1と例2は、同じ話です。
おじさんが怒鳴りこんできた描写を先にすると、読者は、つづきが気になります。
こういうのを『あと説』と言って、出来事を先に書いて、あとから説明する方法です。
小説の出だしは、『あと説』にすると、読者が興味を引かれます。
『あと説』の反対は、『まえ説』といいます。
『まえ説』は、出来事が起きる前に説明をする方法です。
『まえ説』だと、つづきにおこる出来事がわかってしまうので、よほど上手に使わないとつまらなくなります。
それでも、使いかたによっては、おもしろくできます。
同じ話を『まえ説』にしますが、少し話をかえさせてもらいます。
『まえ説』の例
放課後、近所の公園で勇人と幸太郎はキャッチボールをしていた。
「ここ、キャッチボール禁止だから、怒られたら、逃げようぜ」
勇人が言うと、幸太郎が「そうだな」と返した。
「おまえたち、なにをしている!」
近所のおじさんが、真っ赤な顔をして怒鳴りこんできた。
勇人と幸太郎が逃げだすと、公園のまわりに真っ赤な顔をした、たくさんのおじさんが取り囲んでいる。おじさんたちの顔は、まるでコピーしたように、すべて同じだ。
こうすると、『まえ説』の効果があります。
『まえ説』と『あと説』は、効果を考えて使い分けるのがいいです。
ここで、ぼくの小説『絶体絶命ゲーム 1億円争奪サバイバル』の出だしの話をしましょう。
この物語の主人公は武藤春馬という少年です。
でも、小説の出だしは滝沢未奈の話から始まります。
これは、未奈が、この小説のテーマを、になっているからです。
未奈は、病気の妹の治療費が必要で1億円をもらえるという『絶体絶命ゲーム』に参加します。
この小説を書いたとき、「小学生が1億円をかけて、命がけのゲームをやるなんて不道徳だ」と言う人がいました。
たしかに、そのとおりです。
でも、小説は道徳の教科書ではありません。
それに、これには未奈たちの本音がつまっています。
大人がしっかりしてないから、子供が苦しい思いをするんだと、大人たちへのメッセージになっています。
小説の出だしで、ぼくの言いたいことを書かせてもらいました。
興味のある人は『絶体絶命ゲーム』を読んでみてください。
さて、今回は、ここまでにしましょう。
次回を楽しみにしていてください。
角川つばさ文庫では、夏休みの間、小・中学生のみんなの書いた小説を募集中。
くわしくはこちらを見てね!この講座を読んで、作品ができあがったら、ぜひ応募してほしいな!










