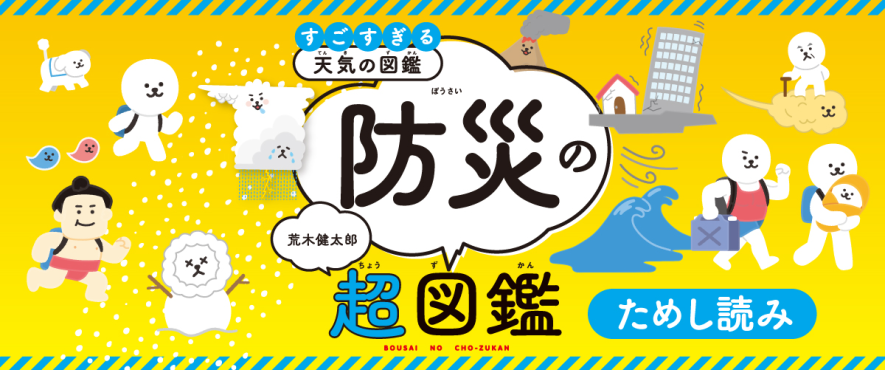
「すごすぎる天気の図鑑」シリーズのスピンオフ第2弾のテーマは、ずばり「防災」! 気象庁気象研究所主任研究官で「雲研究者」としても知られる荒木健太郎氏が、大雨・台風、竜巻、雹、地震・津波、大雪、火山噴火、猛暑などについて徹底解説。避難の心構えや被災後の対処なども詳しく掲載されており、これ一冊で備えは万全です!
連載第4回は、「すごすぎる避難と復旧、支援え」の中から「ほんの少しでも『お金を送る』ことが被災地の大きな支援につながる」と「物資の支援は自分が要らないものを送ることじゃない」を紹介します!
※本連載は『すごすぎる天気の図鑑 防災の超図鑑』から一部抜粋して構成された記事です。
ほんの少しでも「お金を送る」ことが被災地の大きな支援につながる
大きな災害発生後、「自分にも何かできることはあるかな」と思ったら、ほんの少しでも被災地にお金を送るのが有効です。
被災地へのお金の支援には、種類があります。ひとつは、支援金。これは災害発生直後に緊急性の高い救命や復旧の活動など、支援団体の活動に使われるお金です。支援金はその団体の判断と責任で柔軟に使用されるため、すぐに被災地の支援につながります。もうひとつは義援金で、寄付金がすべて公平・平等に被災者に配布されます。被災者の数などを確認したあとに配布されるため、支援までに時間がかかります。義援金には手数料等は一切ありませんが、支援金では支援団体が被災地で活動するために必要な経費を手数料としてまかなう場合も。手数料は団体によって異なり、支援活動の内容を調べるのがおすすめです。
お金の支援は、ひとりひとりは少額でも多くの人が参加すれば大きな支援に。ただこれは支援の方法のひとつなので、無理なく自分にあった方法で支援しましょう。
支援金と義援金の違い
防災の豆知識
自治体などが銀行口座の情報を公開して、義援金を募集することがあります。一方、公的機関や実在する団体を装い、電話や直接訪問などで義援金とうそをついた振り込め詐欺も。自分で調べて確認してから支援を。
物資の支援は自分が要らないものを送ることじゃない
被災地への支援として、物資を送る選択肢もあります。どんな物資を選んで、どのように被災地に送るのがよいでしょうか。
災害直後は被災地の受け入れ体制が整っていないため、基本的に支援団体や自治体を通して物資を支援します。団体や自治体のウェブサイトで最新の情報の確認を。団体や被災者が必要なものを私たちが購入し、現地に届けるマッチングサービスもあります。被災地の道路状況が復旧して緊急車両の通行を妨げず、受け入れ体制も整って迷惑をかけないなら個人で届ける場合も。
物資の支援では、自分が要らないものは送らないことが大切。賞味期限切れの食品や着古した衣類など、もらっても使えません。千羽鶴や冷凍・冷蔵保存が必要な食品などは処理・保存に困るので送らないで。詰め合わせは現地で仕分けるのが負担なので、種類に合わせて箱を分けるなど工夫を。
物資の支援では、過去の災害で役に立ったものなどを参考に、被災者の立場を考えて本当に必要なものを送りましょう。
送り方を確認しよう
送るものを吟味しよう
防災の豆知識
社会に良いことをしているようで、実際には良い影響を与えていない自己満足な行動をスラックティビズムといいます。被災地に千羽鶴を送る行為がまさにこれ。自分が取り組むボランティア活動は大丈夫か、見直してみて。
防災はとても大事だけれど、巷には不正確だったり根拠のない情報もあふれています。この本は、科学的な根拠をもとに、できる限り正確で最新の情報を盛り込んでいます。子どもでも簡単に読めるので、ぜひ家族全員で一緒に見てみてくださいね!
- 【書籍情報】





















