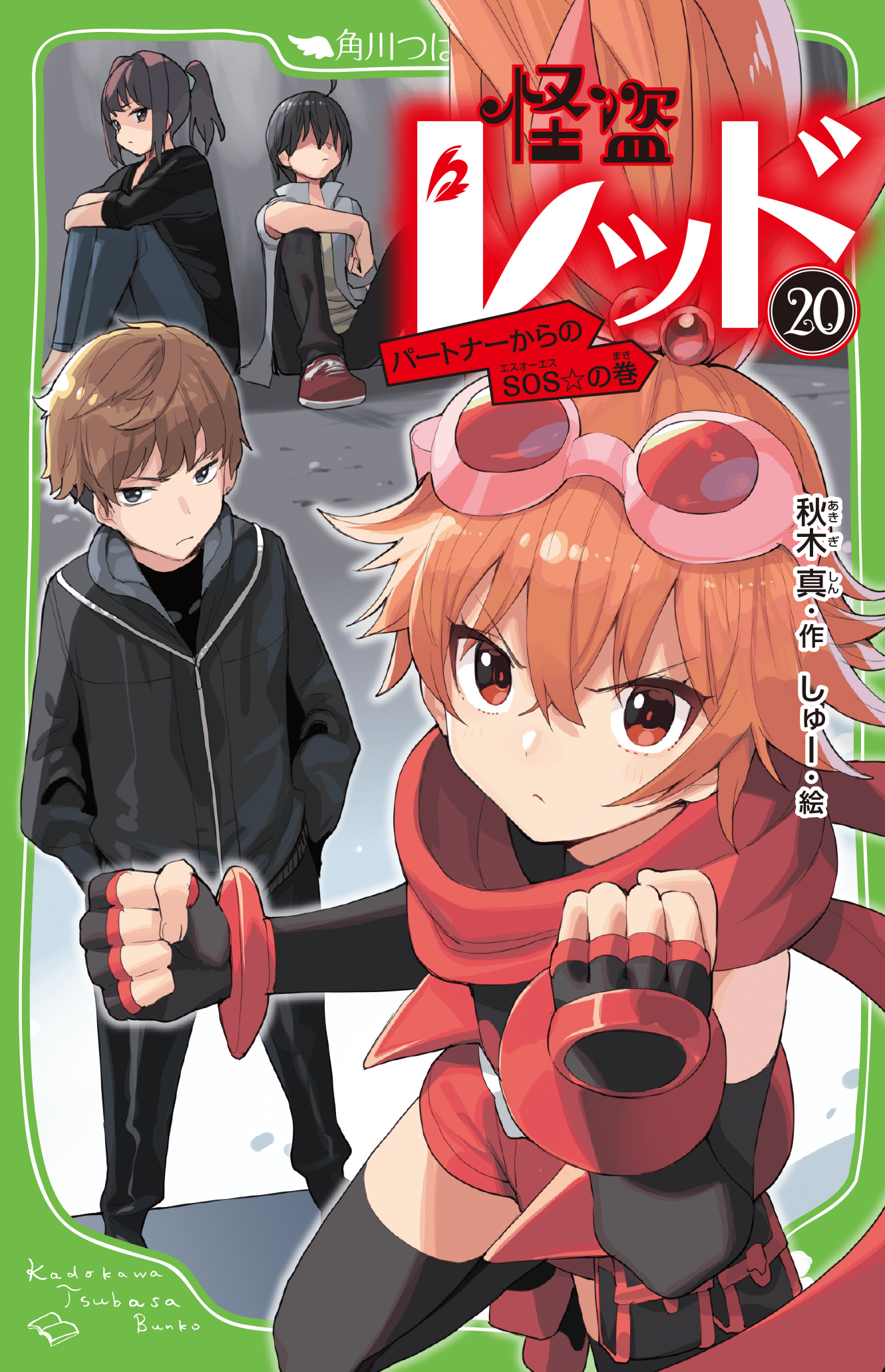中学生だけど、みんなにはヒミツで「正義の怪盗」をやってる、アスカとケイ。
そんな2人のかつやくを描いた「怪盗レッド」シリーズは、累計135万部を超える、つばさ文庫の超人気シリーズです!
怪盗レッド20巻発売記念のスペシャル短編!
今回の主人公は、20巻のもう1人のヒロイン・桜子と、高校生探偵としてアスカとともに犯人を追う・七音(なお)のお話。
15巻で一度顔を合わせている桜子と七音。
20巻では「2人は同じ高校に通っている」としか書かれていないけど…じつは、こんな事件があったのです!
「ねえ、宇佐美さん。今日、学校におくれてきたのは、どうして?」
教室の窓ぎわの席にすわるわたし――宇佐美 桜子に、クラスメイトたちの視線が刺すように向けられている。
「…………?」
今は高校の昼休み。
クラスメイトは、お弁当を食べている人もいる。
そんな中で、急にきつい口調できかれて、わたしはとまどう。
わたしはわずかに顔を上げると、質問してきた相手を見る。
セミロングの髪に、つり目のはっきりとした顔立ちの女の子。
名前は……田野井さんだったはず。
「昨日おそくまで本を読んでいたせいで、寝坊して、1限目の授業に間にあわなかっただけよ」
わたしは、素直にこたえる。
昨日というか……今日の明け方まで、研究書を読んでいたんだよね。
「それ、本当?」
まちがいなく、本当のことなんだけど、田野井さんの向けてくる視線は、きついまま。
どうしよう?
なにかかみあっていない気がするけど、どう答えるのが正解なのか、わからない。
「わかってると思うけど、もう一度説明するわ」
田野井さんが言う。
ぜんぜん、わかってないから、助かる。
それに「もう一度」って言われても、田野井さんがクラスメイトとなにか話していたのは知っていても、わたしは考えごとをしていて、内容はきいてなかったんだよね。
そもそも、わたしに話しかけていたわけじゃないし。
それを「きいていて当たり前」というように言われるのも、理不尽だ。
と思ったけど、それは口にしない。
田野井さんは、イライラしたように、しゃべりはじめた。
「今日の1限目の体育の前、わたし、つけていたネックレスを外したの。それが、授業が終わったら、なくなっていたのよ。
今日の体育を休んだ生徒は3人いるけど、そのうちの2人は学校を休んでて、遅刻してきたのは宇佐美さんだけなの。
これが、どういうことかわかるでしょ?」
田野井さんが、きつい目で見つめてくる。
つまり、田野井さんが言いたいのは、こういうことだよね。
――わたしが、田野井さんのネックレスを盗んだんじゃないか。
それができるのは、わたしだけじゃないかって、こと。
反論することは、もちろんできる。
田野井さんの話は、わたしに疑いをかける根拠にとぼしいから。
彼女の言い分が、いかに論理的でないか、説明するのはかんたんだ。
でも、そんな反論をしたら、火に油を注ぐってことぐらいは、わたしにだってわかる。
学校っていうのは、そういう場所だ。
頭ごなしに「あなたが犯人でしょ」と名指しされていないだけ、まだいいほうかもしれないけれど……。
クラスメイトに目をやるけど、遠巻きにして、話にかかわるのを、ためらっている感じだ。
少し前まで、わたしはクラスの中では完全に浮いていた。
わたしは高校に在学しながら、大学の研究室にも出入りしている。
友だちと雑談をするのも苦手で、そもそも以前は、人と距離をちぢめる努力も、するつもりがなかったから。
最近は、少しずつクラスメイトと会話するようにはなったけど。 こういうときに、かばってもらえるほど、なかよくはない。
でもわたしは、本当にネックレスのことなんて知らない。
そして――
今ここで、どういう返事をするのがただしいかの判断もできない。
こんなとき、どうふるまえばいいかなんてこと、今までほとんど学んでこなかった。
やっと「友達付き合いというのを始めてみた」ぐらいなんだから。
こんなことに対応するのは、難しすぎる。
いったい、どうしたら……。
そのとき。
ガラッ
教室のドアが開く音がして、だれかがツカツカと、わたしと田野井さんのほうに、歩いてきた。
「――なにか、問題が起きているみたいね」
……えっ、この子って……!?
まっすぐにやってきて、わたしと田野井さんの前で立ち止まったその女の子は、にっこりと笑う。
「え~と…………、七音さん?」
「覚えていてくれてよかった。宇佐美さん、ひさしぶり」
目の前にとつぜん現れた彼女――深沢 七音さんは、にこっと笑顔を見せる。
彼女と会ったのは、たった一度だけ。
あれは……マサキといっしょに「ある大事件」にかかわっていたとき。
悪者におそわれそうだったわたしを、助けてくれたんだ。
あのナゾの少女が、今、わたしと同じ制服を着て、目の前に立っている。
……どういうこと?
わたしが混乱していると、田野井さんが、けげんそうな目を、七音さんに向ける。
「どうして、となりのクラスのあなたが、ここにいるの?」
七音さんって、となりのクラスなんだ。
学校のことについて、うとくて、ぜんぜん知らなかった。
「このクラスで、なにかトラブルが起きてるらしいって、きいてさ」
七音さんは、当たり前のように答える。
田野井さんは、七音さんの答えに、いらだったように顔をしかめる。
「そういうことじゃなくて。となりのクラスの、しかも1週間前に転校してきたばかりのあなたには、関係ないでしょ!」
田野井さんが、声をあららげる。
あ、七音さん、1週間前に転校してきたばかりなんだ。
それなら、わたしが知らなかったのも当たり前……でもないか。
田野井さんは、知ってたみたいだし。
やっぱり、わたしが学校生活に対して、無関心すぎるらしい。
「まあまあ、田野井さん。……こういうときは、第三者の冷静な視点というのも必要でしょ? 1つずつ整理してもいいと思うんだ。あなたにとっては、なくしたネックレスが返ってくればいいわけなんだから」
七音さんは、田野井さんにけわしい目を向けられても、平気な顔で言いかえしてる。
田野井さんも、そんな七音さんにあきらめたのか、大きなため息をつく。
「それなら本当に、冷静に判断してよね。この状況、だれがどう見ても、あやしいのは宇佐美さんでしょ」
「――そうでもないと思うよ」
七音さんが首を横にふって、まわりで聞き耳をたてていたクラスメイトも、ざわっとした。
「えっ……どういうこと?」
田野井さんが困惑したように、ききかえす。
「トラブルが起きたときは、まずどんなふうに物事が起きたのか、冷静に思いかえしてみるのが、一番だと思う。というわけで、あたしが調べたかぎりで、順序だてて説明させてもらうね」
七音さんは、田野井さんだけじゃなく、わたしやクラスメイトに向けて話しかけるように、顔をめぐらせる。
そのせいか、教室全体が、とりあえず七音さんの話をきいてみよう、という雰囲気に変わっていく。
「……わかったわ」
田野井さんは、不満そうな顔ではあるものの、うなずいた。
七音さんは、落ちついた声で話しはじめる。
「このクラスの1限目は、体育だった。田野井さんはネックレスをはずして体操服に着替え、授業に参加した。そして、授業が終わってもどってみると、ネックレスがなくなっていた」
七音さんの説明に、田野井さんはうなずく。
「その体育の授業に出なかったのは、クラスでは3人。そのうち2人は学校を欠席していて、宇佐美さんは遅刻で、あとから学校にきた。体育の授業中になくなったわけだから、ほかのクラスも当然だけど授業中。だれもが勝手に学校内をうろつけるわけじゃない。だから田野井さんは、遅刻してきた宇佐美さんが怪しいと考えた」
「そうよ! だって宇佐美さんを教室で見たのは、体育の授業からもどってきたときだったし」
田野井さんが、わたしを横目でにらむ。
そんなことを言われても、わたしはなにも知らないんだから、どうしようもない。
いったい七音さんは、どういうつもりなんだろう?
犯人がだれか、わかっているのかな。
「ところで、田野井さん。あたし、転校してくるときに確認したんだけど、この学校の校則では『アクセサリーは、学校内で表立ってつけないことを条件に可(高価なものは除く)』となっているのは知ってる?」
七音さんが、田野井さんの顔をのぞきこむ。
「ええ……そうよ。だから学校では見えないように服の下につけてたわ。それが今、関係あるの?」
アクセサリーを身につけることは、校則違反じゃないんだ。
アクセサリーに興味がないから、知らなかった。
「じゃあ、あなたがネックレスをしていることを、ほかのクラスメイトは知っていた?」
七音さんが、きく。
「ええ。友だちは知ってたわ。でも、友だちを疑ってるなら、見当ちがいよ。アクセサリーといっても高価なものではないし」
「でも、大事なものだったんじゃない?」
「どうして……! わたし、そんなこと言っていないけど」
七音さんの言葉に、田野井さんがおどろいた顔をする。
「そんな疑心暗鬼になる必要はないわ。みんな、あなたがネックレスを大事にしていることは知っている。。
もちろん、宇佐美さんもよ」
「じゃあ、どうして……!」
田野井さんは、じれったくなったのか、声をあららげそうになる。
「ところで田野井さん。ネックレスは、どこにしまったの?」
七音さんが、重ねてきく。
「教室で外して、かばんにしまっておいたわ」
「そのかばんは、教室にあったのね?」
「そうよ! だから、遅刻して教室にきた宇佐美さんが、あやしいって話になっているんでしょ」
そうだったんだ。
これまでの田野井さんの話には出てこなかったから、わたしには初耳だ。
たしかに、外したアクセサリーを更衣室においていたなら、わたしがうたがわれるのは、おかしいものね。
「でも、田野井さん。授業中の教室に入れるのは、遅刻した生徒だけじゃないでしょ?」
「どういうこと?」
田野井さんが、けげんそうな顔をして、七音さんを見かえす。
「たとえば、授業のない先生とか」
「先生!? それはそうだけど、先生は、生徒のかばんの中身までは見ないでしょ」
「そうだけど、……田野井さん。もしかしてネックレスを外していたとき、いそいでいなかった?」
「それは……ネックレスの留め金がなかなか外れなくて、授業におくれそうで、あわててたかもしれないけど……」
田野井さんの声は、だんだん自信なさげになっていく。
「かばんに入れたつもりのネックレスが、ちゃんと入っていなくて、教室の床に落ちてたら……そしてそれを、見まわりをしている先生が見つけたら、どうすると思う?」
「まさか……!」
田野井さんが、おどろいた顔をする。
「もちろん、ひろって預かるでしょ。あたし、ここにくるまえに職員室でちょっと、きいてみたの、アクセサリーの落とし物はありませんでしたかって。そうしたら、あるって。見せてはもらわなかったけど、それが田野井さんのものじゃないかな?」
七音さんの言葉に、教室がざわめく。
思ってもいなかった答えに、クラスメイトもとまどっているみたい。
「……わたし、確認してくる」
田野井さんはそう言って、走って教室を出ていく。
5分ほどして、もどってくると、田野井さんの表情はわかりやすく、気まずそうなものに変わっていた。
「……職員室にあった。先生が、教室に落ちてたのをひろったって……」
田野井さんが、言いづらそうにぼそぼそと言う。
その言葉に、クラスメイトがざわつく。
一方的に宇佐美さんのことをうたがってひどい、みたいな声もきこえる。
わたしとしては、うたがいが晴れたのなら、それでいいんだけど。
田野井さんは気まずそうだし、これで彼女の立場がなくなるほうが、かえってこまる。
どう言ったらいいのか、迷っていると、七音さんが、
「よかったわね田野井さん、アクセサリーが見つかって! 大切にしているものなんでしょう?」
人なつっこい笑顔で、ほがらかに言った。
「え、ええ……」
「大切なものをなくしたって思うと、取り乱しちゃうよね。でも、なくしものって、だいたい、ちょっとしたかんちがいだってことも多いの。誤解で決めつけて、クラスがギスギスしたら、つまらないわよね。おたがいに気をつけましょ!」
七音さんが、よく通る声で言う。
その明るいようすに、なんとなくみんながホッとした雰囲気になる。
ざわついていたクラスメイトが、静かになって、雰囲気も「見つかってよかったね」というものに変わっていく。
クラスメイトが流されやすいというよりは、七音さんがみんなの気持ちが収まる流れをうまく作った、というほうが正しそう。
どうしてだろう、七音さんの話し方って、ふしぎに説得力がある……と考えていた、そのとき。
「あの……宇佐美さん」
気づいたら田野井さんが、目の前にいた。
「うたがって、ごめんなさい」
田野井さんが、申し訳なさそうに頭をさげてくる。
「べつに気にしてないよ。七音さんが言ったみたいに、誤解がとけたなら、それでいいんだから」
わたしの答えに、田野井さんは、ほっと息をついている。
これで解決、とクラスメイトの集まっていた視線も、それぞれに散って、いつもの昼休みの教室にもどっていく。
ふぅ……。
なんとかなって、よかった。
それもこれも、七音さんのおかげだけど。
「ありがとう、七音さん。……また助けられたわ」
わたしは、七音さんに言う。
「誤解だったんから、あたしがこなくてもいずれとけていたでしょうけどね」
そうかもしれない。
けど、そのときはこんなふうにスムーズに、話は終わらなかったと思う。
うまく立ちまわれないわたしと、アクセサリーをなくしていらついていた田野井さんの間で、クラスが気まずいムードになっていたはず。
こじれずにすんだのは、やっぱり七音さんのおかげだ。
「ところで、宇佐美さん。……あのときのことは、どうにかなったの?」
七音さんが、ふいに声をひそめて、わたしにきいてくる。
あのときって……はじめて会った、七音さんに助けられたときのことだよね。
「う、うん、だいじょうぶ。あの日も今日も、ありがとう。すごく助かった」
わたしも小声で答える。
「そう。それはよかった」
七音さんは、それ以上はきいてこない。
わたしも、かるがるしく説明できないことだから、質問されないことが、ありがたい。
「七音さんっていったい、なにものなの?」
わたしは、代わりに気になっていたことをたずねる。
だって、どう考えたって、ただの高校生には思えない。
「会ったときに、ちゃんと言ったじゃない。――探偵だって」
七音さんは、少しだけ不満げに、頬をふくらませる。
探偵って……。
たしかに、ニュースでときどき名前をきく、高校生探偵の白里響みたいな人もいるけど……。
ああいう人は、ごくごく例外のはずだ。
七音さんが、同じっていうわけないだろうし。
わたし、ごまかされてるのかな?
「それはそうと、『さん』はいらないよ」
七音さんが、親しみのこもった笑みを向けてくる。
「そ、それならわたしのことも、桜子で」
名前呼びをする友だちなんて、はじめてだ。
ちょっと緊張しつつ、わたしもこたえる。
「これからよろしくね、桜子」
七音は、右手を差しだしてくる。
「こちらこそ、……七音」
わたしは、七音の右手を、おそるおそるにぎる。
――こうして、わたしと七音は、友だちになったんだ。
おわり
『怪盗レッドスペシャル』はこれからもつづくよ!
七音と桜子がかつやくする『怪盗レッド20 パートナーからのSOS☆の巻』は3月9日発売!