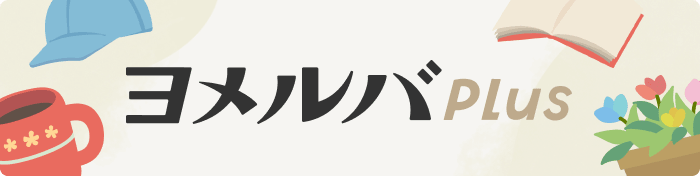ヨウくんってば転校してきたばかりだって言うのに、すっかりクラスになじんでる。
スポーツが得意なヨウくんは、男の子ともすぐにとけ込んでるし。
裏では女の子たちが、ヨウくんのことを王子様っていうあだ名で呼んでる。
あたしだってヨウくんが来た初日に同じこと思ったから、それはナットクなんだけど。
「あの転校生、花菱くんって言うんだっけ? あたしのクラスに転校してきてくれたらよかったのになぁ」
そんな風にため息まじりで言ったのは、あたしの元クラスメイト、芽衣(めい)だ。
「あれ、芽衣がこのクラスに来るの、めずらしいね」
芽衣のクラスとは校舎が別だからか、めったにこのクラスに顔を出しに来ないのに。
「転校生を見に来たに決まってるじゃん。うちのクラスでも王子様の話題でもちきりだよ」
「えっ、そうなんだ?」
ってか芽衣までヨウくんのこと王子様って呼んでるし。
「ほんと、かっこいいよね。うらやましー」
みんな口をそろえて同じこと言うなぁ。
でも確かに、ヨウくんはかっこいいと思う。
あたしって周りの女の子たちが騒(さわ)ぐほど、男の子にキョウミがないみたい。
人並みに、かっこいいとかは思うけど。
でもそれは、雑誌で芸能人やモデルの人を見るのと同じ感覚っていうか……。
不思議なのが、そんなあたしでも最近のヨウくんを見てると、ちょっとドキドキしちゃうんだ。
……でも、なんだろ?
このドキドキって、前にも感じたことある気がするんだけどなぁ?
「あっ、そうだ。ねぇゆずは、今度あたしにメイクのしかた教えてくれない?」
「えっ? いいよ。でも芽衣が教えてって言うなんて珍しいね」
芽衣はダンス部に所属(しょぞく)してるからかスタイル良くて、服装もすごくおしゃれ。
ヘアスタイルも毎日のように変えてるし、制服の着くずし方もかわいい。
今だって、制服のリボンをフワフワのシフォン生地のリボンに替えてて、すごく似合ってるし。
だからこそメイクも自分でしてると思ってた。
「この間、ママのやってるのを見よう見まねでやってみたんだよね」
そう言いながら、芽衣は大きなため息をこぼした。
「自分でするのって、ママのメイクや雑誌で見るみたいに上手くはいかないんだね」
「それ、すごくわかる。不思議だよね──」
あたしだって、メイクの練習は何度やってきたことか。
今でもメイクって思い描いた通りには、なかなかいかないことだってある。
だからこそすごく奥が深いんだ。
「ゆずはだったらメイクに詳しいでしょ? だから一度お願いしたいんだよね」
「そういうことなら、お任せあれ!」
人にメイクできるのって、すごく嬉しい。
自分にするのとはまた違うし。
「じゃあちょっと色々考えたいから、教えるのは明日でもいいかな?」
「うん。じゃあ明日よろしく!」
「オッケー!」
あたしは芽衣が去ったすぐ後で、カバンの中からひとつのスケッチブックを取り出した。
これにはあたしのアイデアがたくさん詰まってる、いわばメイクノート。
ちなみに、このスケッチブックの使い方は3通りあるんだ。
1つ目は、雑誌を読んでいいなって思ったメイクのページを切り貼りする、スクラップブックとして。
2つ目は、雑誌からヒントを得たり、いいなと思ったりしたメイク方法を自分なりにメモるため。
3つ目は、実際に人の顔の絵を描いて、そこに色えんぴつで色を乗せるため。
ファッションデザイナーさんって、イラストを描いてデザインのイメージを膨らますんだって。
これはその、メイクバージョンって感じ。
雑誌の記事に書いてあったんだけど、ケイさんもメイクノートを持ってるって言ってたの。
この色のアイシャドウには、どういう色のリップを選ぶか、とか。
流行色に、ほかにどういう色を組み合わせたらいいのか、とか。
だからあたしもケイさんにならって、スケッチブックを持つようにしてるんだ。
それにあたしはこの、絵を描いて色を乗せていく工程(こうてい)が大好き。
自分でメイクをデザインしてるって感じがして、すっごく楽しいの!
そもそも頭の中でイメージしてるだけだと、すぐに忘れちゃうし。
でもやっぱり、実践(じっせん)でメイクするのが一番好き!
芽衣も言ってたように、するのと見るのとでは全然違うんだもん。
こうやって特訓しても、実際に人にメイクするチャンスはなかなかないしね。
「──ゆずはちゃん、お絵描き中?」
「わっ、びっくりした!」
突然声をかけられて、思わず大きな声を出しちゃった。
おどろいて顔を上げると、あたしの絵をのぞき込んでるのはヨウくんだった。
「なんだ、ヨウくんかぁー」
芽衣のメイクを考えてたせいで、ヨウくんがあたしのそばにいることに気づかなかった。
「ごめん、驚かせちゃった?」
「ううん、大丈夫。ちょっと集中しすぎてたみたい」
あははとあたしが笑うと、ヨウくんはいつものキラキラスマイルでほほえみ返してくれた。
「うん、すごい集中力だったね。一体なにを描いてるの?」
そう言って、ヨウくんは再びあたしのスケッチブックをのぞき込む。
「えっと、人……だよね?」
スケッチブックに描いた絵を見て、ヨウくんが困ったような顔をしてる。
「あはは。あたしの絵、めちゃめちゃヘタだよね?」
「えっ、いや。なんていうか、個性的だね?」
おお! さすがは王子様。
ヨウくんってば、ものすごく言葉を選んで言ってくれてる。
カドが立たないように、やわらかい言葉に言い換えてくれるところが、さすがって感じだ。
自分で言うのもなんだけど、あたしって壊滅(かいめつ)的に絵がヘタだから。
「絵はヘタでもいいの。あたしは絵を描いて、メイクの色とバランスを見たいだけだから」
胸を張ってそう言うと、ヨウくんはおどろいたように瞳を満月みたいに丸くさせていく。
「……ゆずはちゃんって、すごいね」
「えっ? 何が?」
どこを見てすごいって言ってるのかがわかんなくて、あたしはスケッチブックとヨウくんの顔を、何度も見くらべた。
ヨウくんは心からカンシンしたような目で、あたしのスケッチブックを見つめてる。
「色々すごいなって思ったんだけど、何が一番すごいってさ──」
ヨウくんはあたしのスケッチブックの表紙を指さした。
「これがすでに、20冊目に突入してるところかな?」
スケッチブックの表題に、メイクブックNo.20って太字のペンで書いてるそれをヨウくんは指さした。
「そうこれ、記念すべき20冊目なの」
数字的にキリがいいよね。
「でもこれももうすぐ終わっちゃうから、また新しいの買ってもらわなくっちゃ」
あたしはノートより少し大きくて、枚数の多いスケッチブックが好きなんだ。
紙も分厚いから切り抜きをのり付けしても、裏に写んないし。
「ママには1年で50冊以上は買わないって言われてるから、超えないように気をつけなきゃ」
「えっ? これって、〝今まで〟の合計数じゃなくって、〝今年だけ〟で20冊ってこと?」
ヨウくんの優しい瞳がいつも以上に見開かれてる。
「あははっ、そうなんだよね。まだ5月にもなったばかりなのに、やばいよね?」
なんて、正直笑ってらんないんだけど。
なんだか50冊におさえられるのか、不安になってきちゃった。
雑誌もたくさんためないようにって、ママに言われてるんだよね。
だから必要なメイクのところを切り取って、このスケッチブックに貼るようにしてる。
あたしがスケッチブックの冊数を心配してる最中、ヨウくんはカンシンした様子であたしを見てた。
「ゆずはちゃんが言ってたメイクアップアーティストになりたいって夢、本気なんだ」
ええー? 本気に決まってるじゃん。
「ヨウくん、信じてなかったの?」
「いや、そうじゃないけど……ゆずはちゃんの本気度が、僕の想像を超えてたから」
ふーん、そうなんだ?
「ところでさ、このアイシャドウとリップの色、ちょっとハデすぎない?」
「えっ? そうかな? そう思う?」
ヨウくんの指が、トンッとあたしのイラストのひとつを指さした。
「もっと色にメリハリつけるといい気がする」
メリハリ?
「むらさき色のアイシャドウに真っ赤なリップなら、アイシャドウの色をグラデーションにするとか?」
グラデーション?
あたしは首をかしげながら、まじまじと自分のイラストを見る。
ヨウくんは自分の言葉に補足(ほそく)を入れるように、さらにこう言った。
「ほら見て。このイラストはチークの色もピンク色でしょ?」
あたしのイラストの頬に乗せたピンク色。
そこから口元の赤いリップをヨウくんは指でなぞってる。
「これじゃ全体的に色がケンカし合ってるみたいに見えない?」
「うーん。そうかな?」
こんなもんだって思ってるからか、そう言われてもしっくり来ないんだけど。
でも、ケンカし合ってるように見えるくらい、色合わせよくないのかな?
「例えば服で想像してみてよ」
ヨウくんは自分の制服の裾を、親指と人さし指で小さくつまんだ。
「濃いむらさきのトップスに、真っ赤なスカート。さらにピンクのマフラーを巻いたら、ちょっとハデすぎると思わない?」
ヨウくんのアドバイスを聞いて、もう一度あたしの描いたイラストを見る。
「洋服なら全身で表現してるからいいかもだけど、顔ってパーツが小さいでしょ?」
……確かに、そんな風に言われると、あたしのこれはハデかも。
「だからむらさき色をグラデーションにすると色が薄まって、ほかの色とケンカしないと思うんだ」
そう言って、ヨウくんは指でアイシャドウの色をぬぐう。
「ただの濃いむらさき色よりも自然でしょ?」
さっきまで濃い色をしていたむらさき色が薄くなって、口元が際立(きわだ)って見える。
「ほんとだ。ヨウくんの言う通りだ!」
口元の赤さが目立って、さっきよりもダンゼンかわいく見えてきた。
なるほど、これがヨウくんの言いたかった、メリハリってやつかぁ。
「ちなみにチークの色もここで濃く入れるとハデになるから、おさえた方がいいと思う」
ヨウくんはふっと笑いながら、さらりとアドバイスを入れてくる。
っていうかヨウくんのアドバイス、すごくない?
めちゃくちゃ的を射てるし、わかりやすい。
「ヨウくんって、すごいね!」
さっきはあたしのことすごいってほめてくれてたけど、ヨウくんの方がすごいよ。
「それに、ヨウくんってメイクのことめちゃくちゃ詳しいよね?」
チークやアイシャドウなんて言葉も、さらっと使っちゃったり。
その上、あたしのイラストを一瞬見ただけで、ズバッとアドバイスできるんだもん。
正直びっくりするくらい、ヨウくんってば知識持ってるよ!
「えっ、いや、僕は別に……」
「ううん、めちゃくちゃくわしいよ! でも、なんで? どこで勉強したの?」
あたしは思わず席を立って、ヨウくんの手をにぎりしめてしまった。
だってヨウくんってば、今にも逃げ出してしまいそうな顔するんだもん。
絶対逃がさないよ!
こんな風にアドバイスしてくれた友だちなんて、今まで一人もいなかったんだから!
「あー……僕の知り合いにメイクにくわしい人がいてね。その人が言ってたのを覚えちゃったんだ」
ヨウくんは慌(あわ)てるように、身ぶり手ぶりでそう説明してくれる。
「知り合いってヨウくんのお友だち? それならあたしに紹介して欲しい!」
そしたら絶対、その人と友だちになれる自信がある!
あたし、メイクの話ができる友だちがほしかったんだよね。
「そっ、その人は僕たちよりかなり年上だし、前に住んでた家の近くの人だから、ごめん!」
いつもにこやかなヨウくんなのに、いつになく慌てた様子でそう言い切った。
「なんだぁ。残念……」
せっかくあたしの同志(どうし)が見つかった! って思ったのになぁ。
そう思って、席に座り直そうとした、その時。
「って、わー!」
あたしはずっとヨウくんの手をにぎりっぱなしだったことに、今ごろ気がついちゃった。
「ごめんね! つい、思わず!」
あたしは慌てて、ヨウくんの手を解放した。
「ううん。こっちこそ、期待させちゃったみたいでごめんね」
そう言ってヨウくんは、柔らかそうな髪をフワリと揺らしながら、ほほえんだ。
あたしってば、勝手に盛り上がって恥ずかしい~!
照れをごまかすかのように笑いながら、あたしは頭を下げた。
すると瞳と口元を弓なりにしならせて、王子様はその場を去っていった。
*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*
「ゆずはー、約束通りメイクしてくれるー?」
お昼を食べ終えた芽衣が、あたしのもとまでやって来た。
「オッケー。じゃあさ、中庭にある温室に移動しない?」
「うん、いいね。行こう」
温室は、中庭の真ん中にあるガラス張りの建物で、たくさんの植物が育てられてるんだ。
中にはガーデニング用のテーブルとイスもあって、なかなか快適。
あそこはあたしのお気に入りスポットなの。
「ってか、ゆずはのメイクボックス大きいね。なんかプロのメイクさんみたい」
「へへっ、でしょー? ママが昔使ってたやつだけど、もう使わないからってもらったの」
この中にはママのおさがりの道具や、おこづかいで少しずつ集めたコスメが入ってるの。
「さてと。さっそく始める前にさ、芽衣がどういう感じでメイクしたいのか知りたいかも」
プロ(見習い)として、依頼主(いらいぬし)の希望を聞くのは必須(ひっす)よね。
「そもそも、基本的なところが知りたいんだけど」
「例えば?」
「例えば……アイシャドウってよく聞くんだけど、実際どういうものなの?」
「アイシャドウっていうのはね、まぶたや目の際にぬるメイクのことだよ」
あたしはメイクボックスからみどり色とみず色のパレットを取り出して見せた。
パレットの中には濃い色と薄い色の計4色がそれぞれに入ってる。
「じゃあさ、アイブロウとチークっていうのは?」
「アイブロウはまゆ毛だよ。アイシャドウと同じ〝アイ〟ってつくけど、目元のことじゃないんだ」
昔、アイブロウってまゆ毛って意味だって知った時、ちょっとショウゲキだったんだよね。
「チークっていうのは、ほおに乗せるメイクのこと」
あたしはピンク色とオレンジ色のパウダーを、それぞれメイクボックスから取り出した。
「ほらよくアイドルってほおがほんのりピンク色してたりするでしょ? あれだよ」
「そっか、なるほどねー」
なんだか芽衣の様子を見てると、昔の自分を思い出しちゃう。
あたしもよく書いてある言葉の意味がわかんなかった時は、ママに聞いたもん。
じゃあ実際にメイクを試してみようってなった、その時だった。
「おい、お前たち。こんなところで何してるんだ」
その声にふり向くと、あたしたちのすぐ近くには見たこともない男の子が立っていた。
制服を一切着くずさず、生徒手帳に載ってる見本通りに着こなしてる。
シャツの一番上のボタンまでキッチリ留めてる生徒って、初めて見たかも。
ちゃんと着こなした制服に細メガネがすごく似合ってて、なんていうか……硬派(こうは)な感じ?
メガネをクイッと中指で持ち上げる様子も、なんかちょっと絵になるような男の子。
「何って……メイクしようとしてただけだけど?」
「メイク?」
硬派な男の子はあたしのメイク道具をちらりと見て、こう言った。
「そんなもの、必要ないだろ」
えっ? 必要ない……って。
「必要ならあるよ。あたしは将来、メイクアップアーティストの仕事に就きたいんだから」
メイク雑誌や道具は全部、あたしの将来の仕事道具。
だからこれはあたしにとって、必要不可欠なアイテムだ。
「柊沢くんこそ、こんなところで何してるの?」
柊沢くん?
芽衣はこの子を知ってるの?
「俺は昼休み中に風紀を乱す輩(やから)がいないか、校内をチェックして回ってるんだ」
はい? なんでそんなこと?
その男の子はあたしの顔を見た後、自分の制服のそでをグイッとつかんであたしに見せつけた。
「風紀、委員?」
柊沢くんの左腕には〝風紀委員〟と書かれた腕章(わんしょう)がついてる。
風紀委員なんてあったんだ?
今まで聞いたことなかったんだけど。
っていうか、腕章つけてる人なんて、初めて見たし。
「メイク道具なんて学業に不要なものは、没収(ぼっしゅう)だな」
「えっ、没収!?」
ちょ、ちょっと待った!
「なんで没収されなくちゃいけないの!?」
思わずメイク道具をかばうように抱き寄せた。
「うちの学校ってさ、雑誌持ってくるのもメイク道具持ってくるのも自由のはずだよね?」
さすが、芽衣! 冷静にあたしの代わりに言いたいことを言ってくれた。
「メイクなんて大人がするもんだろ。子どもの俺たちがするもんじゃない」
「ええー! なんで? あたしたちだってメイクしてもいいじゃん」
メイクは大人がするもの、なんていうのは決めつけじゃない?
「メイクが学業に不要で、風紀を乱すっていうんなら、メイクより先に服装を注意すべきじゃない?」
そう言ったのは芽衣。
芽衣は自分の制服に手を伸ばして、さらにこう言う。
「あたしなんて今日、制服のリボンじゃなくてママに借りたスカーフ結んでるんだけど? これは注意しないの?」
確かにー!
昨日はシフォンのフワフワリボンで、今日の芽衣はスカーフをリボンタイにして結んでる。
ほんと芽衣はおしゃれだなー……なんて、感心してる場合じゃない!
「服装はよくてメイクはダメって、そんなのただの言いがかりでしょ」
言いがかりというか、ただのいじわるだ。
この風紀男子は小さくため息をついたあと、再びメガネをクイッと持ち上げた。
「そもそも制服に関しては自由が決められてる。アレンジ程度であればな」
「それならメイクだってよくない?」
「制服の着方は生徒手帳にも書いてあるが、メイク道具に関しては書かれてないだろ」
えー、そういう基準なのー?
「生徒手帳に書いてないことは、風紀委員の俺が判断する」
なにそれ! なんてオーボーな!
「だから髪も服装も、奇抜(きばつ)でなければ許す」
許す? それじゃあ、許すも許さないも、風紀委員の言い分次第ってこと?
それっておかしくない?
「だからそのメイク道具もダメだ」
「だからなんで!?」
「それは武器になる。荷物も多いし、何より重い」
ぶっ、武器!?
ちょっと意味がわからないんですけど!
「持ち運んでる時、ほかの生徒にぶつかったら危ないだろ」
「えっ、じゃあパソコンはどうなるの?」
あれも持って来てる子いるじゃん! 重いじゃん!
「パソコンはふり回さないだろ」
「メイク道具もふり回さないよ! っていうか、人を歩く凶器みたいに言わないでよね!」
ひどくない?
今日が初めましてなのに、なんて言いざまなの?
「ってかゆずは。そのメイク道具持って来ていいか、わざわざ先生に相談してなかったっけ?」
そうだった!
さすがはしっかり者の芽衣だ。本人が忘れてることも覚えててくれるなんて!
「そうそう! ちゃーんと先生にも許可もらってるもんね」
初めてこれを学校に持って行く時、ママに言われたんだ。
きちんと先に先生に相談してからにしなさいってね。
すると、この風紀男子はナットクしたのか、急に静かになった。
どうだ参ったか! って、そう思っていた矢先……。
「じゃあその先生からの許可証(きょかしょう)、見せてみろ」
はい?
「わざわざ許可もらったんだろ? ならその証明書があったっておかしくないだろ」
いやいや、おかしいでしょ!
「そんなのないよ!」
ってか先生だって絶対、許可証なんてもの用意してないよ。
「じゃあお前は、どうやって俺にそれが先生が許可したって証明するつもりだ?」
いやいやいやいや。
「そもそもなんで、あんたに証明する必要があるっていうの?」
風紀男子はしつこくも、腕章をあたしに見せつけた。
いやもう、そのくだりはいいから!
「だったらもう、あたしの担任の若松(わかまつ)先生に聞いてくればいいじゃん!」
こぶしに力をぎゅっと込めてそう言うと、風紀男子は考え込むように腕を組んだ。
「わかった。若松先生だな。聞いておく」
カッチーン!
とうとう、ゆずはちゃんの堪忍袋(かんにんぶくろ)の緒(お)が切れたぞ!
なにが『聞いておく』だ。どこまで頭でっかちなんだ。
憤慨(ふんがい)してるあたしをその場に残し、柊沢くんはフンと鼻を鳴らして去って行く。
もっと文句を言いたいところだけど、イライラしすぎて言葉も出ない。
芽衣は風紀男子の後ろ姿を見つめながら、肩をすくめた。
「……なんか、ごめん。厄介(やっかい)な人に見つかっちゃったね」
「いや、芽衣は全然悪くないよ。ってかさ、あの人なんであんなに偉(えら)そうなの?」
「えっ? もしかしてゆずは、柊沢くんのこと知らない?」
「知らない。ってか今日初めて知った。あの人そんなに有名なの?」
「柊沢 烈くんって言って、変人の風紀委員っていうのでかなり有名だよ?」
えっ、そんなに有名なんだ。
初めはちょっと硬派でクールな感じ、とか良いように見てた自分がバカみたい。
今となっては完全に前言撤回(ぜんげんてっかい)するけど。
「柊沢くんって学年で成績もトップだからさ、先生にもかなりちやほやされてるんだよね」
「えっ、そうなの?」
いくら頭が良くたって、あんなに高圧的(こうあつてき)な態度を取る男の子なんてごめんだよ。
「とにかくゆずは、柊沢くんには気をつけて。さっきので目をつけられちゃったみたいだし」
芽衣は心配そうな顔でそう言った。
「ありがと。でも、あたしなら大丈夫!」
あいつが実際に頭が良いとか先生に気に入られてるとか、あたしはよく知らないけどさ。
メイクのことなんて、なーんにも知らないくせに。
あたしがどれだけ本気でメイクと向き合ってるのかだって知りもしないで、否定ばっかだし。
あー、思い出したらまたムカついてきちゃった!
あいつがまた何か言ってくるようなら、今度もまた受けて立ってやる
*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*
昨日は1日雨だったのに、今日はお日様日和(びより)。
なんたって今日は、学期ごとに一度だけある授業参観の日!
「ゆずはちゃん、今日も元気だね」
太陽の光に負けないくらいのキラキラスマイル。
そんな笑顔をふりまきながらやって来たのはヨウくん。
「元気はあたしの取り柄だからね」
ゆずはちゃんはいつも元気だね、明るいし、おもしろいね、って。
小学校に入ってから、こういう風に言われることがかなり増えた。
メイクを知って、ケイさんに出会って。
あたしがなりたいあたしになれた証拠だ。
えへへって笑い返すと、ヨウくんはさらに笑顔を倍増させてくれた。
口元を綻(ほころ)ばせて無邪気に笑うヨウくんの顔を見てると、なんだかすごく安心する。
ヨウくんって優しいし、気が利くし、なにより笑顔がすっごくステキだ。
ただひとつ不思議なのが、ヨウくんの笑顔って、やっぱりどこか懐(なつ)かしさを感じるんだよね。
それがなぜか、あたしをドキドキさせるというか……。
でもその懐かしいって感じる理由も、なんでなのかよくわかんないんだけど。
「午後からの授業参観が楽しみだね」
「うん。まぁ、僕のところは仕事で来られないみたいだけど」
「そっかぁ……それは残念だね」
ヨウくんのところはパパさんがお仕事でアメリカにいるって言ってたっけ。
ママさんもお仕事が忙しいんだって、前に言ってたもんね。
「でも僕としては、来られなくてほっとしてるけど」
「えっ?」
ヨウくんの声があまりにも小さくて、なんて言ったのか聞き取れなかった。
「ううん、なんでもないよ」
ヨウくんはいつものスマイル全開で、あたしに笑いかけた。
なんとなく話をはぐらかされた感じもするけど、まぁいっか。
ヨウくんの笑顔につられて、あたしも笑顔を返した。
──お昼休み。
ちょうど同じタイミングでお昼ごはんを食べ終えた凛と、あたしは一緒に教室に戻る途中。
「あっ、そう言えば」
凛は何かを思い出したように手をたたいた。
「芽衣ちゃんがこの間、ゆずはちゃんのことをすっごくほめてたよ」
「えっ? なんで?」
「メイクについて、ものすごく物知りだって言ってた」
「ほんと? 嬉しー!」
実際、この間はメイクせずに終わっちゃって、残念だったんだけどね……。
近いうちにリベンジしたい!
でも、メイクの話をしただけでも喜んでもらえたのなら、良かった良かった。
「私も、メイクしたらかわいくなれるかな?」
「えっ? 凛は今のままでもすっごくかわいいよ」
「あっ、ありがとう……」
凛はほんのり頬を赤らめてほほえんだ。
そんな様子がいつも見てる凛とは少し違って見えて、あたしは思わず目をこすった。
なんか凛がすっごく大人っぽく見えた気がしたけど、気のせいかな?
「今度もし私にメイクしてって言ったら、ゆずはちゃんは引き受けてくれる?」
「えっ、もちろんだよ!」
むしろ喜んで!
「でも珍しいね、凛がメイクしたいなんて。肌が弱いからメイクは怖いって言ってなかったっけ?」
「うん、そうなんだけど……」
凛はそれ以上なにも言わず、うつむいた。
「あっ、そういえば私、先生に呼ばれてたんだった。ゆずはちゃんは先に教室戻ってて?」
「えっ? うん、わかった」
なんとなく凛が何かをごまかしてるみたいに見えたけど、あたしは立ち去る凛を見送った。
凛はなんで急にメイクしたいって思い立ったんだろう?
あたしとしてはメイクできるなら嬉しいけど──って。
「わぁ!」
食堂のある校舎の角を曲がった時に、思いっきり誰かとぶつかっちゃった。
「わっ、ごめん! 大丈夫!?」
校舎のカゲから突然飛び出してきたのは、女の人。
ぶつかったあたしが倒れないように、女の人は抱き止めてくれてる。
「はっ、はい、大丈夫みたいです」
あいたたた!
コケなかったけど、相手の人の体で鼻を思いっきり打っちゃった。
「急いでたから前方不注意だった。ごめんね!」
誰かのママさんなんだろうなーって思って顔を上げると──。
「えっ……?」
あたしは思わず固まってしまった。
えっ、だって、ウソでしょ! そんなのあり得ないじゃん!
頭の中が混乱して、とっさに言葉が出てこない。
そんな中で目の前にいる女の人は、あたしの体を引き離して、腕時計に目を向けた。
「やばいっ、遅刻だ! ってか大遅刻だわ!」
「ちょっ、ちょっと待ってください!」
今にもかけ出しそうになっているところを、あたしは服のそでを引っ張って引きとめる。
うそっ! こんなことってある!?
これ、夢じゃないよね!?
あたしは必死になってこの女の人を引きとめる一方、空いてるもう片方の手でほおを思いっきりつねった。
痛い! ってことは、やっぱりこれは夢なんかじゃない!!
「ごめん、本当に急いでるの!」
急いでるのはわかります!
その様子を見てればよくわかりますとも!
そう思いながら、あたしは声の出る限り叫んだ。
「あのっ! ケイさん、ですよね!? メイクアップアーティストの!」
あたしの言葉に、ケイさんは体から力が抜けたように立ち止まった。
「えっ? なんで私のこと知ってるの?」
ケイさんは驚いた顔をして、あたしを真っすぐ見つめてる。
その顔、その声。
あたしが忘れるわけがありませんから!
「あたし、ケイさんの大大大大っファンなんです!!」
あたしは溜(た)めに溜めまくって、大ファンをより強調させた。
ぐぐぐっとにぎりこぶしを作って、力いっぱい力みながら。
「ケイさんのメイクは、いつもあたしを幸せにしてくれるんです!」
あたしのあこがれで、あたしに魔法をかけてくれたケイさん。
ケイさんはやがて、驚いた表情から満面の笑みになる。
それは5年前のあの日と同じ、まぶしい笑顔だ──。
「あたし、ケイさんが書いてる雑誌のメイク特集、かかさず読んでます!」
って言っても、大人向けだからわかんない言葉や漢字も多くて、ママに教えてもらいながらだけど。
「そこで前にケイさんが言ってたように、あたしもイラスト描いてメイクの練習もしてるんです!」
「えっ、それって人の顔を描いて、アイシャドウやリップをぬったり、っていう?」
「そうです! それです! スケッチブックに……って、今持ってないんですけど!」
ああ、もうっ! なんでこんな大事な場面で、あれを持ってないかな!?
お昼ごはん食べるからと思って、スケッチブックは教室に置いて出て来ちゃったよー!
いつでも書き込めるようにって、スケッチブックもなるべく持ち歩くようにしてたのに。
あー、あたしのバカ~!
「とにかくケイさんのメイクはいつも魔法がかってて、すっごくステキです!」
ケイさんはおどろいた表情をしたあとすぐに、にっこりとほほえんでくれた。
ああ、あの時のキラキラした笑顔は全然変わってない!
……って思うのに、なんでかな?
一瞬、その笑顔がどこかヨウくんの笑顔に見えて、あたしは首をひねってしまった。
だってケイさんとヨウくんじゃ、性別も年齢も違うのに。
それなのに同じように見えたのって、変だよね?
あたしが首をひねってる間に、ケイさんは感心したような顔であたしをマジマジと見下ろしてる。
「しかし、こんなに小さなファンがいたなんて、カンゲキだわ」
「あの、実はあたし──!」
あたし、5年前にも一度、ケイさんに会ったことあるんです!
そう言いたいところだけど、ケイさんは再び腕時計に目を向けて、大きな瞳をさらに見開いた。
「ああっ、ごめんね! もっとお話したい気持ちは山々なんだけど、私はもう行かなくちゃ」
「あっ、待ってください!」
もう少しだけ話がしたい。
ケイさんに会えるチャンスなんて、次いつあるのかわかんないもん!
だけどケイさんはそんなあたしに背を向けた。
「ほんと、ごめん!」
「あのっ!」
腕をつかもうとしたけど上手くかわされて、そのままケイさんはかけ出した。
──ちょうど、そんな時だった。
「あっ、やっと見つけた!」
そう言いながら、ケイさんが飛び出してきた校舎の陰から慌てたように現れた、一人の男の子。
「母さん! 忘れ物だ、よっ……!?」
叫びながらかけてきたのは、あたしのクラスの男の子──ヨウくんだった。
ヨウくんがあたしがここにいることに気がついて、どこか気まずそうな顔をした。
まるで〝しまった〟って言いたげな表情で。
待って。ヨウくん今、ケイさんのこと母さんとか呼ばなかった?
──えええっ!?
ってことはもしかして、ケイさんってヨウくんのママさん──!?