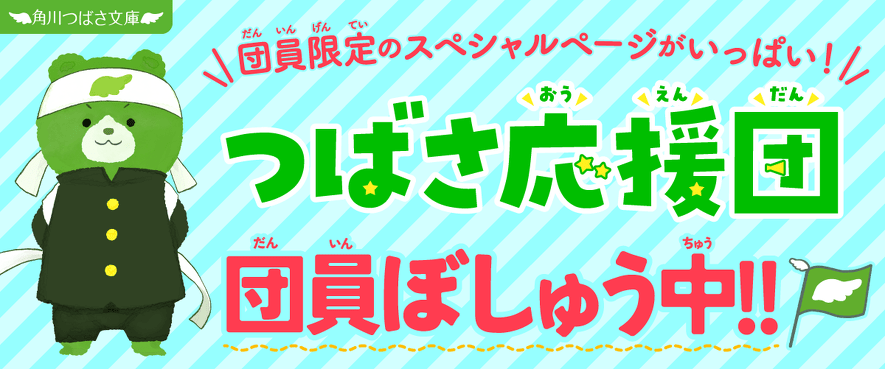【学校でもない。家でもない。見つけた!わたしの大事な場所】大人気作家・夜野せせりさんが、つばさ文庫に登場! 『スピカにおいでよ』1巻冒頭を特別連載♪ ユーウツな気分をふきとばす、応援ストーリーです!
6 甘くてすっぱいクリームソーダ
学校に行ってない? 一度……も?
そういえば、教室に、いつも空いている席があるのを思い出した。
「あの、それって」
どうして、と聞こうとしたところで、
「こんにちはっ!」
と、背後で明るい声がした。
振り返ると、背の高いひょろっとした男の人がいた。まんまるいふちなしのめがねをかけている。
もしかして、この人が先生?
「おっ。もしかして見学の子かな?」
男の人は、にこっと笑った。ほほえむと、めがねの奥の目が三日月みたいに細くなる。
七瀬(ななせ)くんが、さっきと同じように、わたしのことを紹介してくれた。
「くるみさん、よろしく。僕は春日奏太朗(かすが そうたろう)。大学3年生。学校の先生を目指して勉強してるんだ」
「は、はい」
「まだ学生だけど、じっさいに子どもたちと触れ合いたい、教えたいって思いが強くて。家庭教師や塾のバイトも考えたけど、おばがカフェのスペースを借してくれることになって。自分で塾を開いたんだ」
『おば』って、オーナーの葉子(ようこ)さんのことだよね。
「葉子さんも、もと教師だから、奏ちゃん先生がたよりない時はさりげなーく助けてくれるんだ」
七瀬くんがこっそりわたしの耳もとでささやく。奏ちゃん先生って呼んでるんだ!
先生は、七瀬くんの告げ口がばっちり聞こえていたらしく。
「こほん!」と、わざとらしくせきばらいした。
「スピカがひみつきちになるのは、毎週水曜日。今のところ、生徒は、昴(すばる)くんと野々村(ののむら)さん。そして、もうひとり中学生の男の子が来ている」
こくりと、うなずく。
「せまいスペースだけど、あとふたりぐらいなら教えられるよ。苦手科目があったり、もっと伸ばしたい得意科目があったりする子、それから」
先生はいったんことばを区切って、
「家や学校に居場所がない子も、大歓迎」
と、つけくわえた。
「ここが、そんな子たちの、ひみつきちになればいいなって思ってる」
居場所が……ない子? ひみつきち?
どきんとした。
学校でのわたし。ぜんぜん友だちができなくて、それどころか、避けられてるっぽくて。いつもひとりで過ごしている、わたし……。
家に帰ってもひとりだし、やっとママが帰ってきても、なんだかピリピリしてる。
「学校はどう?」ってなにげなく聞かれても、心配をかけたくなくて本当のことを言えないし、ごまかしたり、話をそらしたりして、苦しかった。
先生の「大歓迎」っていうことばを聞いて、はじめて気がついた。
わたし、ずっと、ほっとできる場所がほしかった。
ここにいてもいいんだって、心から思える場所がほしかった。
わたし、この「ひみつきち」に、いてもいいの? みんなの仲間になってもいいの?
ふと、わたしを見つめる視線に気づいた。野々村さんだ。
先生が現れて、話がとぎれちゃってたけど、野々村さん、学校に行ってないって言ってた。
何があったのかわからないけど、野々村さんも、学校に『居場所がない』のかな。
「ちょっといいかしら? 新作の味見をお願いしたいんだけど」
すずやかな声がした。葉子さんだ。
葉子さんが手にしている銀のトレイには、台つきの大きなグラスが4つのっている。
わたしは一瞬で目をうばわれた!
「クリームソーダだ!」
しかも、わたしがよく知っている、グリーンのソーダ水のクリームソーダじゃない。
野々村さんが、テーブルの上に広げていたノートと教科書をそそくさと片付けた。
「高梨(たかなし)さん、すわって」
野々村さんが、自分のとなりの椅子を、とんとんとたたいた。
「う、うん」
わたしが野々村さんのとなり、七瀬くんがわたしの向かい、そのとなりに奏太朗先生がすわる。
葉子さんが、銀色の星のかたちをしたコースターを目の前にすっと置いて、その上に、ことんとグラスを置いた。
「すごい。カフェみたい」
「カフェだし」
七瀬くんがくすくす笑う。
「だって……! ふしぎなんだもん」
カフェなのに塾、塾なのにひみつきち。
クリームソーダはきらきらと夢みたいにかがやいている。
ソーダ水が、淡い黄色なの。グラスのふちには輪切りのレモンが添えられていて、バニラアイスのてっぺんには赤いチェリーがちょこんとのっている。
銀色の細いスプーンでバニラアイスをすくうと、ソーダ水の中に、金色の星くずみたいなこまかい泡がたちのぼって、はじけた。
すごくきれい。ため息がこぼれそう。
アイスは冷たくて、舌の上ですっと溶けた。ソーダ水はすっぱくて、でもほんのり甘くて……。
「レモンだ」
なんだか胸がきゅんとするような、甘ずっぱいレモンの味。
「当店手作りのレモンシロップで作っております、特製レモンクリームソーダでございます」
葉子さんがかしこまった調子で告げて、きちっと腰を折っておじぎをした。
そして、ふたたび顔をあげて、
「どう? おいしい?」
と、いたずらっぽい笑みをうかべる。
「はいっ! すごくおいしいです」
手作りのレモンシロップだなんて、すごいよ。
となりにいる野々村さんが、にいっと、七瀬くんに笑いかけた。
「これって、あのレモンだよね?」
七瀬くんはこくっとうなずく。
「シロップ、前に味見させてもらったけど、クリームソーダにしてもおいしいんだね。すごいな」
七瀬くんの瞳がかがやいている。あのレモン?
わたしの目にクエスチョンマークが浮かんでいたのか、七瀬くんは、
「おれが育てたレモンなんだ」
と、さらっと告げた。
「そ、育てた? 七瀬くんが? レモンを?」
そのレモンがシロップになって、こうやってクリームソーダになって……ってこと?
「レモンって木だよね? 植えたの? わたし、レモンの木って見たことない。すごい、自分で育てられるんだ」
「べつに全然すごくないって」
七瀬くんは、はにかんだように、ほおをほんのり赤らめた。
「それに、きっとレモンの木、見たことあると思うよ。ふつうの家でも育てられるしさ。ただ、それがレモンだって気づいてないだけで」
ぶっきらぼうにぼそぼそと告げる七瀬くん。やっぱり照れてる?
「これ飲み終わったら、見せてあげなよ」
にこにこと提案したのは、奏太朗先生。
見せてあげる?
っていうことは、七瀬くんは、レモンの木を、この「ひみつきち」で育ててるんだ!
7 七瀬くんのレモン
七瀬くんのレモンがあるのは、カフェ「スピカ」の小さなお庭だった。
「ひみつきち」スペースの、引き戸側から見て右側に、お庭に出るためのドアがあった。
「どうぞ」
七瀬くんがドアを開ける。すると、ふわっと、さわやかな草のかおりがした。
小さな花壇に、むらさき色のお花や白いお花が生えていて、風にそよいでいる。
「いいにおい」
「ハーブだよ。葉子さんが育ててるんだ」
「へえ……」
胸いっぱいに空気を吸い込む。からだの中に青い風が吹き抜けていくみたいだよ。
「おれのレモンは、これ」
七瀬くんが指さしたのは、大きな鉢。細い枝にしげった、みどり色の葉っぱがまぶしい。
「鉢植えなんだね」
「うん。直接地面に植えちゃうと、実がなるまでに何年もかかっちゃうんだって」
「へえ~」
なんでだろう? ふしぎだなあ。
「葉っぱもレモンのにおいがするんだよ」
七瀬くんはレモンの葉っぱを一枚ちぎって、手でもんだ。
「ほら」
葉っぱをわたしの鼻先につきつける。
「わあっ。ほんとだ」
さわやかで、すっぱい……レモンのかおり。
「葉っぱのうらに、つぶつぶがあるだろ? それがつぶれるとにおいがするんだよ」
「へえーっ。七瀬くんって物知りなんだね」
「おれも育ててみるまで知らなかったよ」
七瀬くんのほおが、また、ほんのり赤くなった。
もしかして七瀬くんって、けっこう、照れ屋さん?
七瀬くんの髪が春の日差しにふちどられて、金色に光っている。
レモンの、青い葉っぱからただようかおり。なんでだろう、胸がきゅっと苦しい。
「どうしたの高梨さん? おれの顔、なにかついてる?」
「えっ? ううん、べつに」
あわてて目をそらす。わたしってば、七瀬くんに見とれてた。
「と、ところで七瀬くんは、どうしてここでレモンを」
ごまかすみたいに、わたしはたずねた。
「もともとは、うちのベランダで育ててたレモンなんだ。母さんがどこかから苗をもらってきて、鉢に植え替えて、家族で世話してたんだけど」
七瀬くんは深く息を吐く。
「……いつの間にかみんな、レモンの存在忘れてて。放置されて、気づいた時には枯れかけててさ。ちょうどおれがここに通いはじめたころだったから、もしかしたら奏ちゃん先生がなんとかしてくれるかもって思って、鉢を持ってきたんだ」
「そうだったんだね」
レモンのお世話を忘れるぐらい、七瀬くんの家族はみんな、忙しかったのかも。
ひょっとして、急に忙しくなるような、大きな出来事があったのかもしれない。
うちは……そうだった。
ママの顔が、頭をよぎる。パパと別れて、この街に引っ越して、新しい会社に就職して。忙しいのもあるけど、なんだか張りつめてるの。
だからわたし、ママの足を引っ張らないようにしなくちゃって思って、しんどくなる時がある。
七瀬くんの横顔を、そっとぬすみ見る。
さっきまで光をあびてきらめいていたのに、今は雲がかかったように、瞳の色がかげっている。
もしかして七瀬くんにも、家にいづらい理由があるのかな。
きゅうに胸がぎゅっと苦しくなって。レモンを見つめる七瀬くんのせつなげな顔を見ていたら、いてもたってもいられなくなって。
「レモン、すごく元気になったんだね。七瀬くんがここに連れてきて、一生懸命お世話したおかげだね」
わたしは明るい調子で、そう言った。
七瀬くんに笑ってほしかったから。
それに、ほんとうのことだもん。枯れかけてたレモンが、シロップにできるぐらいたくさん実をつけるまでになったんだよ。
七瀬くんはわたしを見て、きれいなアーモンド形の目を、大きく見開いた。
そして、ふわっと笑った。
「ありがとう」
「そ、そんな。べつにお礼なんて……」
どうしよう。どきどきする。七瀬くんの顔をまっすぐに見られない……!
なんで? どうして? 笑ってくれてうれしいのに、今度はどきどきして苦しいの。
「ところで、さ。学校のみんなには、このこと、だまっててくれる?」
七瀬くんはそう言ってほおを人差し指でかいた。
「なんで?」
「その。おれ、こういう、果物育てるとか、そういうの、あんまりキャラじゃないっていうか」
七瀬くんはわたしからわずかに目をそらした。
「そうなの?」
「星が好きとか、そういうのも、あんまりクラスの友だちには言ってないんだ」
そうだったんだ。なんでだろう。七瀬くんってやさしいから、レモンのお世話も「キャラじゃない」なんて思わないけどなあ。星が好きなのも、すてきだなって思うし。
「星ってロマンあるよな、ってなにげなく言ったら、キザっぽいな~って笑われたことがあって」
「それはその人としゅみが合わなかっただけかもだよ?」
「まあ、そうなんだろうけどさ……」
七瀬くん、ちょっとだけしゅんとしてる。
でも、その気持ち、わかる。わたしも、高梨がアイドルとか似合わないって言われてたもん。
「わかった。だれにも言わないよ」
「よかった。よろしくな」
「うん。でも、わたしには大丈夫だったの?」
「え?」
「みんなには内緒にしたいのに、わたしにはいろいろ教えてくれて」
図書室で、まっさきに星の図鑑を手に取ってた。「気になってたんだよ」って言って。
レモンのことも。レモンをここで育てるようになったいきさつまで、話してくれた。
クラスのみんなには見せていない、隠している、七瀬くんの「べつのカオ」を。出会ったばかりのわたしが、知ってしまっている。
「ひみつきちのことだって。高梨さんならいいよ、って」
さいしょに見学にさそってくれた時のこと。思い出すと、胸がどきどきする。
「そう……だね。なんでだろう」
七瀬くんは、わたしの目を見て、じっと考え込んだ。
「高梨さんは、なんだか……。おれのこと、わかってくれそうな気がしたのかも」
えっ! どきんと、大きく心臓がはねた。
わかってくれそうな気がした? わたしが? 七瀬くんを?
ふわりと、やわらかい風が吹く。わたしの髪も、七瀬くんの髪も揺れる。
どき、どき、どき、どき……。
「おーいっ! あたしもまぜてっ!」
とつぜん、明るい声がひびいた。びっくりして肩がはねる。
わたしと七瀬くんは、そろって後ろをふりむいた。野々村さんだ。
目が合うと、野々村さんはふしぎそうに首をかしげた。
「高梨さん、どうしたの? 顔が赤いけど」
<第5回へとつづく>
※実際の書籍と内容が一部変更になることがあります。