
ようこそ、ふしぎアイテム博物館へ。
小学5年生の春崎冬馬(はるさき とうま)くんは、運動がニガテな男の子。
明日の球技大会が、イヤでイヤでしょうがないんだって。
塾の扉を開けたら、『ふしぎアイテム博物館』へ来ることができたみたい――。
.。゚+..。゚+. .。゚+..。゚+
第2話 変身手紙①
.。゚+..。゚+. .。゚+..。゚+
「イヤだな……」
ぼく――春崎冬馬(はるさき とうま)はつぶやく。
塾の階段を上りながら、ひとり、つぶやく。
明日の球技大会が、どうしてもイヤなんだ。
だってぼくは、大の運動オンチ。
球技大会の練習中も、五年二組のクラスメイトから、ぼくはお荷物扱いされている。
「冬馬さえいなきゃ」「冬馬の動きヤバくね?」「冬馬はそこでじっとしてろ!」「冬馬って、勉強はできるけど、ほんと運動は苦手だな」……いったい何度、こんなことを言われただろう。
見返したいって気持ちはあった。
でも、苦手なものは苦手で。
だからこうして、イヤだなぁと思いつつ、塾の階段を上ってるんだ。
授業がはじまるまで予習していよう――そう思って、ぼくは自習室の扉を開けた。そして、すぐに「あれ?」と気づく。
だって扉の先が、長い通路になっていたから。
床には絨毯が敷かれ、天井にはシャンデリアが光り、壁は高級そうな木材でできている、そんな通路に。
「自習室がリフォームされて……って、そんなわけない、よな?」
いったん扉を閉めてから、三秒まって、また開ける。
扉の先は、長い通路のままだった。
「…………」
入るべきじゃ、ないんだろうな。
まずシンプルに怪しいし、それに時間のムダだから。
学校の宿題、塾の予習、家に帰ればピアノのレッスン……ぼくには、やるべきことがある。
ぼくに、遊んでるヒマはない。
それなのに、いつの間にか、ぼくは通路に足を踏み入れていた。
まるで、なにかに引き寄せられるかのように、勝手に足が動いたんだ。
どれくらい歩いただろう。やがて、広い空間に出る。
「なんだ、これ……!?」
そこにあったものを見て、ぼくは自分で自分の目を疑った。
空中に浮く皿。黄金のカブトムシ。伸び縮みする花瓶。涙を流す石像。鎖と縄でグルグルに縛られたランドセル、その他もろもろ……。
通路の先にあったのは、たくさんのガラスケースと、その中に奇妙なモノが入れられた部屋だった。
「ぼくをビビらすためのドッキリ……なわけない、よな……?」
ぼくは少しの間立ちつくして、それから、おそるおそる部屋を見て回った。
ガラスケース、館内撮影禁止の看板、解説文と思われるプレート……すぐに、ここが博物館だとわかる。
奇妙なモノたちは、展示品だったんだ。
しばらくして、ぼくが足を止めたのは、たくさんの紙が展示されているコーナー。
いや、紙じゃなくて、どうやら手紙の展示らしい。
もっと派手な展示品がいくらでもあるのに、ぼくの目は、なぜかそこに吸い寄せられたんだ。
【御レイ状】
あの世にいる霊にお礼のメッセージを送ることができるハガキ。
ただし返事は来ない。
【滅入るメール】
送った相手に呪いをかける便箋。
あくまでも便箋それ自体が呪いの正体であり、書かれている内容は関係ない。
そのため、呪いをかけたとバレにくい。
【連絡蝶】
羽にメッセージを書くと、相手のもとまでヒラヒラ飛んで行く、紙でできた蝶。
目立たないように隠れながら飛んでくれるが、雨に弱い。
やがて、ぼくはその展示品に気づく。
【変身手紙】
手紙に、自分がなりたいものを書くと、少しの間、そのなりたいものに変身できる手紙。
「変身……返信、じゃなくて?」
この、なんの変哲(へんてつ)もない白い便箋と、タヌキの絵がちょこんと描かれただけの白い封筒に、そんな力が?
まさか。そんなバカな。
ありえないと頭ではわかっているのに、ぼくは変身手紙から目がはなせない。
頭ではわかってる。でも、心は、ぼくの心は、変身手紙にどうしようもなく惹かれていた。
これが、ほしい。
変身手紙が展示されたガラスケースに向けて、ぼくは、ゆっくり、手を伸ばし――
「ガラスに指紋がついちゃうよ」
あわてて、手を引っこめる。
ふり向くと、人が立っていた。ぼくと同い年ぐらいの、ボブヘアーの女の子。
「ご、ごめんっ」
反射的に、あやまった。この子にあやまってもしかたないのに。
「うん。わかってくれたらいいよー」
でも、その子はそう言った。いかにも人当たりの良さそうな笑みを浮かべながら。
「まあ、べつに触ってもいいんだけどね。ただ、あとで掃除するのもメンドウだから」
そ、掃除?
「あ、そっか。まずはこれを言わなきゃ」
その子は姿勢をピッと正して、やがてこう言った。
「ようこそ、ふしぎアイテム博物館(ミュージアム)へ」
……ふしぎアイテム、博物館。
そうか、この変な手紙たちは、たしかにフシギなアイテムだ。
「わたしはメイ。この博物館の館長――の助手をしているよ」
「その、ぼくは、春崎冬馬。小学五年生」
流れで自己紹介してしまったけど、助手ってなんだ? いや、そもそも、この博物館自体が謎すぎる。
「ねえ冬馬くん、変身手紙かな?」
「えっ?」
「見ていたのは、変身手紙?」
「……そう、だけど」
恥ずかしくて、ぼくの声は小さくなった。
変身手紙を見ていたなんて、変身したいですって言っているのと同じだ。
「そっかそっかー。うん、ちょうどいいね」
ちょうどいい?
メイさんはこちらに近づくと、ガラスケースを外して、中の変身手紙を取り出した。
メイさんの動作は、とても堂々として見えた。しかもその手には、白い手袋がはめられている。
じゃあ、ほんとうに、この子は博物館の人なのか?
「ねえ冬馬くん、いま、時間ある?」
あるかないかで言えば、ない。
ほんとうだったら、いまは塾の予習をしてるはずなんだ。
「時間は……あるよ」
でも、ぼくはそう答えていた。それくらい、変身手紙に心を奪われていた。
「よかった! うちの館長が、冬馬くんに会いたがっててさ。連れてくるようにって言われてるんだ。この変身手紙が気になるんなら、うん、会ったほうがいいよ」
「どうして?」
「だってここにあるアイテムは、みーんな館長が集めたんだもん。きっと、おもしろい話が聞けるよ」
たぶん、その館長はただ者じゃない。もしかしたら、危険かもしれない。
そう思いつつ、でも、やっぱり、ここで帰る気にはなれない。
「さあ、こっちこっち」
メイさんに連れられ、ぼくは歩きだす。博物館の、奥へ奥へと。

* * * * * * *
やがてたどり着いたのは、金色の飾りで彩られた、それはそれは豪華な扉の前だった。
「ごきげんよう」
扉を開けたとたん、声をかけられる。
「ひさしぶりのお客さまだわ。さあ、座って」
サラッサラの黒髪に、スッと通った鼻筋、キラキラ輝く大きな目。
声の主は、女の人だ。それも、とんでもなくきれいな。
黒いドレスを着て、優雅にソファーに座る姿は、どこかつくりものめいてすらいた。
動かずじっとしていれば、博物館に展示された美術品だと思ってしまうかも。
「ふしぎアイテム博物館の館長、宝野(たからの)ヤカタよ」
館長さんは、中学生くらいに見えた。
ふつうなら、中学生で館長はおかしい。でも、そもそも、この博物館はふつうじゃない。
「その、ぼくは、春崎冬馬です」
「お礼を言うわ冬馬くん。いそがしいのに、私に会ってくれてありがとう」
「え? あの、どうしてぼくがいそがしいって、わかったんですか?」
「なんとなくそう思ったの。私のカンはね、当たるときは当たるわ」
当たるときは当たる。
当たり前のことなのに、館長さんが言うと、なにか深いセリフのように聞こえた。
たぶん、ぼくは、この人のオーラにのまれてる……。
「……あの、館長さん」
「なにかしら?」
それでも、ぼくは聞くべきことを聞いた。
「この博物館はいったいなんなんですか? ぼくは塾の自習室に入ろうとして、ここにつながる通路を見つけたんです」
「うふふふふふっ」
館長さんは上品に口元をおさえて笑う。
上品で、楽しげで、でもそれだけじゃない〝なにか〟がふくまれた笑み。
「ねえ冬馬くん、そんなことはどうでもいいと思わない?」
「ど、どうでもいいって……」
「冬馬くんはいそがしいのでしょう? だったら、もっとほかにするべき質問があるのではなくて? たとえば、気になっているアイテムのこととか」
頭に、変身手紙のことが浮かぶ。
……いや、ちょっとまった。ぼくがアイテムを気にしているって、どうして館長さんはわかったんだ?
これも、なんとなく?
「ヤカタさま、これこれっ」
メイさんが変身手紙を館長さんに渡した。
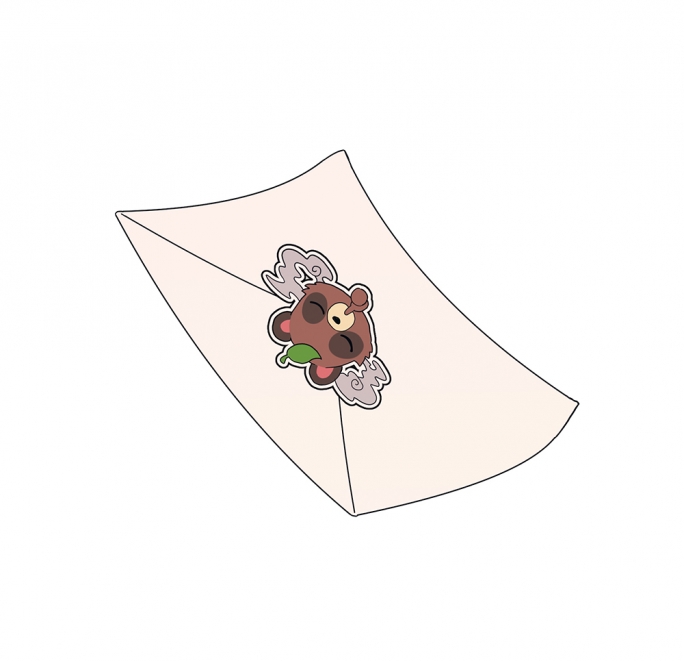
「ああ、変身手紙じゃない。なるほど、冬馬くんは変身したいのね? いまの自分に、なにか不満があるのね?」
「えっと、それは……」
「どうなのかしら? 冬馬くん、あなたはほんとうに、変身手紙を望んでいるの?」
正直、話したくなかった。だって、自分の弱みをさらすのは、とても恥ずかしいことだから。
「ねえ、冬馬くん」
館長さんが少しだけ、ソファーから身を乗り出した。
大きな目が、ぼくをとらえる。
その瞬間、体がゾクッと震えた。全身に電流のようなものが走った。
「さあ、正直に、言ってみて?」
「……変身手紙を見た瞬間、どうしてもこれがほしいって、ぼく、そう思ったんです」
なぜだろう。ぼくはいつの間にか、正直な気持ちを口にしていた。
「……だって、明日、球技大会があるから」
「球技大会?」
館長さんは首をかしげた。
「学校中が、バレーやバスケやドッジボールなどの球技で、一日競い合うんです」
「へえ? なんのためかしら?」
なんのため? そんなこと、考えたこともなかった。
「な、なんのためって言われると、わからないんですが、とにかく、そういうのがあるんです。ぼくは運動が苦手で、だから、変身手紙がほしくて。勉強はできるけど運動はダメ。クラスメイトから、何度もそんな風に言われて……」
笑われると思った。
でも、館長さんは静かにぼくを見つめていた。
「ふうん。なるほど。そういう悩みもあるのね。運動なんてしたことないから、私にはよくわからないけど。まあ、でも、ふさわしいわ」
ん? ふさわしい?
「ねえ冬馬くん、変身手紙を使ってみない? 私、あなたに変身手紙を貸したいの」
「か、貸すって、いいんですか……!? でも、どうして……?」
「私はただ、愛するアイテムを使ってほしいの。だって、アイテムは人が使ってこそでしょう? 人に使われてはじめて、アイテムは真の価値を発揮するわ。だから、変身手紙を強く望む冬馬くんに、ぜひとも使ってほしいの」
「でも、館長さん、ぼく、お金は持ってなくて……」
「いいのよ」
「でも、貴重なものなんじゃ?」
「いいのよ。冬馬くんは変身手紙を、大事に使ってくれるのでしょう?」
「それは……はい」
「なら、いいの。それが、お金の代わりになるわ」
いくら使ってほしいからって、それが代わりに?
なにかをはぐらかされている気もするけど……まあ、いいか。
じゃあやっぱり、金を払えと言われてもこまる。
「それじゃあ、話もついたことだし、冬馬くん紅茶でも飲む? ねえメイ、持って来てくれるかしら、ほら、この間飲んだ――」
「あ、いや、おかまいなく」と、ぼくはあわてて言った。
思ったより、ずいぶん長居してしまっている。
「ぼく、そろそろ帰らないと。塾とか、宿題とか、習い事とかあって。だから、そろそろ失礼します」
「そう? わかったわ。メイ、出口まで送ってあげて……ああ、まって」
立ち上がったぼくを、館長さんは引き止めた。
「これだけは言っておくわ。変身手紙を使うのは、なるべく一人きりのとき、できれば自宅にいるときがいいでしょうね」
え? なんでだろう。
「変身手紙は魅力的な、そして強力なアイテムよ。もし、変身手紙の存在が知られたら、みんなほしがるに決まってる。冬馬くん以外の人が、変身手紙になりたいものを書いても、もちろんその人が変身するわ。だから変身手紙を使っているところを、だれにも見られようにね」
ぼくは「わかりました」と返事をして、お礼を言ってから、館長室を出た。
「冬馬くん、今日は、ヤカタさまのワガママに付き合ってくれて、ありがとう」
入ってきた扉のところまで来たとき、メイさんが言った。
「いや、ぼくも、アイテムを貸してもらったから……」
「貸し出し期間は、そうだなぁ、球技大会が終わるまででいい?」
ぼくはうなずいた。
「変身手紙の効果が出るのは、変身手紙を使ってから十分後。そして効果が切れるのは十時間後だから、よく覚えておいてね。それと……」
メイさんは少しタメを作ってから言う。
「ヤカタさまの言うとおり、変身手紙は強力なアイテムだよ。でもね冬馬くん、なにに変身しようと、きみはきみだよ。どうか、それを忘れないでね」
きみはきみ? よくわからなかったけど、いちおう「うん」と返事をして、メイさんにも別れを告げる。
扉を開けた瞬間、周りの景色が、一瞬で変わったのがわかった。
絨毯もシャンデリアもない、見慣れた塾の自習室に、ぼくは立っていたんだ。
<第4回へつづく> 4月23日公開予定
『ふしぎアイテム博物館』は好評発売中!
つばさ文庫の連載はこちらからチェック!▼

















