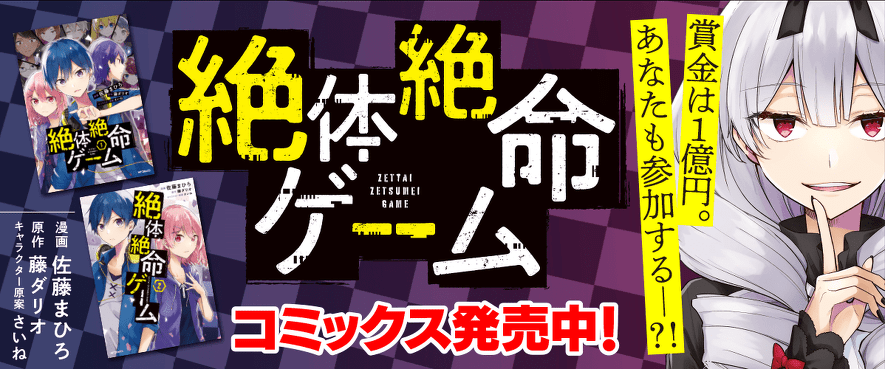◆3 脱落者には死を
ド────ン!
春馬は大きなクッションの上に落ちた。
煙を吸ったせいか、頭が少し痛い。
春馬はおきあがって、まわりを見た。
教室の半分くらいの広さの、殺風景な部屋だ。
未奈、理子、亜久斗、ほかのゲーム参加者、タツと大男もいる。
「火事たァ、驚いたね。けが人はいないようだね」
タツが、まったくなにごともなかったかのような、やけに冷静な口調で言った。
……なにかが、おかしい。
「アクシデントはあったけど、ゲームを再開しようかね」
平然としているタツに、春馬は違和感をおぼえる。
「ちょっと待ってください、火事はどうなったんですか!?」
「あぁ、そのことなら心配無用だ」
「早く避難したほうがいいんじゃないですか!?」
「春馬、聞こえなかったのかい。心 配 無 用 と言ったんだ」
タツの迫力におされて、春馬は口を閉ざす。
……あれ?
なにげなくポケットをさわると、携帯電話がなくなっている。
逃げるときに落としたのかな?
「すみません、携帯電話を落としたみたいです」
春馬が言うと、ほかの参加者もポケットを探しはじめる。
「あれ、わたしもだ」「おれのもなか」「ぼくのもないぞ」「どうしたんだ?」
タツは知らんぷりをしている。
「あの、それよりも、参加者が、1人少ないんですけど……」
理子が、不安そうにまわりを見て言った。
参加者を確認する。
未奈、亜久斗、竜也、奏、理子、大樹、慎太郎、サオリ……。
幸一がいない。
「おや、おかしいねェ。脱出口のどこかで引っかかっちまったかな?」
タツは、みんなが落ちてきた天井の穴を見あげる。
「園田幸一、まだ中にいるのかィ!?」
そのとたん、穴から園田幸一が落ちてきた。
「うわっ!」「きゃぁぁぁぁぁぁぁぁ!」
落ちてきたのは、真っ黒に焼けこげた死体だ。
「どうやら幸一は、逃げ遅れちまったようだねェ」
タツが冷たく言いはなつ。
「そ、それ、ほんとうに幸一ですか!?」
「真っ黒こげで死んでいるから、断言はできないけどねェ」
「幸一は、ぼくより先に非常口に入った。もし中で引っかかってたら、ぶつかってたはずだ!」
「おや、それは不思議だねェ。それじゃ、この死体は、だれだっていうんだい?」
そう言われたら、こまる。
春馬は1歩、死体に近づいた。
焼けこげた、強烈な悪臭がする。
これが幸一の死体かはわからないが、かたちから、人間の死体なのは、まちがいないようだ。
春馬がほかの参加者を見ると、みんな、青い顔をして死体から目をそらしている。
「どうするんだい、この死体を調べるかい?」
小学生が、死体の検視なんてできない。
でも、これには、からくりがあるはずだ。
「タツさん、なにか隠してますよね。ほんとうのことを話してください」
春馬が言うと、タツは袖から大きな扇子を出して、ぱたぱたと顔をあおいだ。
「あーァ、もうばれちまったようだね。しかたねェ、ネタばらしをしてあげるよ。さっきの火事騒ぎはすべて、あたしらが仕組んだものさ」
それじゃ、幸一は火事で死んだんじゃない。殺されたのか?
「今回の『絶体絶命ゲーム』はね、東京の街中でおこなうんだよ。それで、一般人に迷惑をかけないように、アンタたちの人間性を、チェックさせてもらったってわけさ」
渋谷の地下で火災報知器まで鳴らして、一番、ひとに迷惑をかけているのはだれなんだ!
「そうそう、火事騒ぎはゲーセンの中だけだから心配ないよ」
なるほど、あそこは防音室になっていたのか。そして、煙は外にもれないようにしていた。
それでドアがしっかり閉まっていたんだな。
あいかわらず、このゲームの仕掛け人は用意周到だ。
「人間は非常時に本性が出るんだよ。あたしャ、卑怯な輩が大嫌いなのさ」
もしかして、幸一のことを言ってるのか?
「園田幸一は、ふらふらしていた理子をつきとばし、春馬に暴言を吐いて、われ先に逃げだそうとした。そんなやつにはゲームの参加資格はないから、脱落……。いや、失格にしたんだよ」
「そ、それで、殺したんですか!?」
今まで震えていた理子が、怒っている。
「ゲームに参加したら命の保証はないと、招待状に書いてあったはずだ。みんな、それに承知して参加したんだろう?」
「園田くんは、わたしをつきとばした。それはひどいけど、だからって殺すなんて……」
「甘ったれるんじゃねェ!」
タツが一喝する。
「あれがほんとうの火事だったら、お前さんはいまごろ、お陀仏さ。これは遊びじゃねェ、命がけの『絶体絶命ゲーム』なんだ。弱肉強食、情けは無用。しっかり肝に銘じて、おくんンだァねェ!」
タツは、歌舞伎のような寄り目になると、両手を広げて、足を踏んばり、見得を切った。
「よっ、鳥肌屋っ!」と大男が声をかける。
「……!」
参加者たちが、顔を青ざめさせて、おしだまる。
「─あぁ、時間をムダにしちまったィ。まずは、アタシの助手の鬼吉を紹介するよ」
タツに言われて、大男がかるく頭を下げ、
「オレァ、鬼吉だ。よろしくなァ」と低い声で言った。
「鬼吉、さっそく仕事だよ。あれを持ってきておくれ」
タツが命令すると、鬼吉はすばやくアタッシュケースを持ってきた。
開けると、中には、スマートフォンが9台入っている。
型はどれも同じで、色は赤、青、黄、緑、オレンジ、白、黒、金、銀と9色ある。
「好きなのを選びな」
これにも仕掛けがあるのだろうか?
春馬が慎重になっているうちに、ほかの参加者がスマホを選んでしまった。
「残りものには、福があると言うからな」
春馬は、残った黄色のスマホを手にした。
黄色は好みの色じゃないけど、しょうがない。
「選んだスマホを、アームバンドで右の手首につけて」
タツに指示され、春馬はアームバンドを手首に装着する。
「うわぁ、すごいな!」
すぐに、ディスプレイに 武藤春馬 認証 と名前が表示された。
「ホーム画面に、アプリが表示されているね。タッチすれば使えるよ。アプリはマップ、乗り換え検索、メモ帳、コンパス、時計だけだ、追加はできないよ。メールは受信のみ。
あとは、ICカードが内蔵されてるよ。改札の読み取り機に、ディスプレイをタッチすれば、都内のバス、地下鉄、電車は乗り放題さ。お得だろ?」
ディスプレイに時間が表示されている。
9時45分
なんだって!?
そのとき、サッと未奈が手をあげた。
「このスマホ、時間がおかしいです! 9時45分になってます」
「おかしくないよ。今は9時45分……46分になったね。時間は正確サ。それじゃゲームの説明をはじめるよ」
どういうことだ。
時刻が正しいとすると、今は、集合時間から1時間46分が経っていることになる……。
「今回のゲームは、アンタたちのスマホに、直接、問題のメールが送られる。メールにはヒントが添付されてるから、それをもとに、都内のどこかにある、『チェックポイント』を推理して、制限時間までにそこに到着するってェゲームだ。間にあわなかったやつァ、そこで脱落。最終問題のチェックポイントに一番早く到着した者が優勝さ」
「そりゃ不公平や! そいじゃ、東京に住んでいる人が有利ばい!」
九州から参加した大樹が、口をとがらせて言った。
「あぁ、そうサ不公平だよ。でもね、どの世界にも運・不運ってェのがあるんだ。まったくの公平なんてのァ、この世には存在しないよ。お前さんたちはもともと、不公平な世界で生きてるんだ。そんなこと、小学5年にもなればわかるだろ!?」
タツの言葉に、だれも言いかえせない。
このゲームの参加者のほとんどが、この世界が不平等だってことに不満を持っているんだから。
「自分が、人より不利な状況にあると思うンなら、それをカバーするために、頭を使うんだね。東京に住んでないやつでも、このゲームには勝てるはずサ」
大樹はまだ不満そうな顔をしているが、タツは気にもしていないようだ。
「ゲームの説明が途中だったね。─ゲーム中の暴力、暴言、差別発言、交通ルール違反、マナー違反などの、非道徳な行為はすべて禁止だよ。それと、ゲーム参加者以外の一般人と会話することも禁止。もし違反すると、イエローカードで、いたーいお仕置きがあるからねェ」
ピーッ
そのとき、全員のスマホからホイッスルの音がひびき、ディスプレイに、サッカーの審判が胸ポケットからイエローカードを出す動画が表示された。
その瞬間、体に電流が走った。
「うわぁ!」
春馬も、ほかの参加者も、いっせいに叫んだ。
冬にドアノブをつかんだときにビリッとなる静電気が、全身でおきた感じだ。
体中に、無数の針を刺されたようで、耐えられないくらい痛い。
「イエローカードをもらうと、今の3倍の電気ショックが、きっかり1分間つづくからね。死にはしないが、死にたいくらい痛いよ。あとイエローカードのペナルティーとして罰則や、特典がうけられないことがあるからね。イエローカード2枚で、ゲーム脱落。悪質でひどい違反があれば、レッドカードで一発アウト、即・脱落だからね。そのときは……、これは言わないほうがいいね。フフフ」
「レッドカードの場合は……感電死ですか?」
春馬が聞くと、タツはにやりと笑った。
「違反しなければいいのサ」
そのとき、亜久斗がはじめて口を開いた。
「『優勝者を決める』ということは、勝者は1人ということだな」
「ああ、そうサ。チャンピオンは、たった1人だ。ゲームの途中でも、もし参加者が1人だけになったら、そこでゲームオーバー。残った者が優勝だ」
ブルブルブル
そのとき、9人のスマホが振動した。みんな、いっせいにメールを開く。
第1チェックポイント 制限時間は、午前11時00分
時間オーバーは─脱落
メールには、『ヒント』というタイトルの添付ファイルがついている。
チェックポイントの場所を見つける手がかりか?
春馬はファイルを開いた。
画面に、鬼のうしろすがたのイラストが表示される。
どういう意味だろう……。
「なんや、かんたんや。ここなら、オレでも知っとる」
ヒントを見てそう言った竜也に、奏が「声が大きいわ」と注意している。
「アタシのヒントは、はずれ。ぜんぜん意味わかんない!」
サオリが吐き捨てるように言った。
「ぼくのヒントもはずれだ。でも……」
そこまで言って、慎太郎はあわてて口を閉ざす。
「でも、なに?」
サオリが聞くが、慎太郎は話そうとしない。
「自分で考えろよ」
「ねえ、スノボ教えてやるからさぁ、協力しよ。スノボが上手だとクラスで人気者になれるよ」
「ぼくは今でも人気者だよ」
「もっとだよ。女子にモテモテだよ」
「女子に……モテモテ……」
サオリと慎太郎は、なかよくなったようだ。
タツがおもしろそうに、みんなを見まわして言う。
「もうわかっただろうけど、添付されてるヒントは、1人ずつちがうよ。アタリもあれば、大ハズレもあるのサ。人と協力してチェックポイントにむかうのもいいし、1人でいってもいい」
春馬は、まだ自分のヒントを見つめて、頭を悩ませていた。
これだけじゃ、まったくわからないぞ。
どうすればいいんだ……。
「あたしャこれでも人情家なんだ。悩んでいるやつもいるようだから、特別に、追加のヒントをあげよう。
─第1チェックポイントは、有名な観光スポットさ。ホラ、かんたんだろ。タイムリミット内に着かなかったら脱落。そのときは命の保証はないからね」
タツは両手を高く持ちあげ、野球のピッチャーのように右手をふりおろした。
「大舞台の、幕開けさァ─!」
バ────ン!
爆音がとどろき、天井が吹っ飛び、壁がくずれ落ちた。
一瞬にして部屋がなくなり─春馬たち9人は、屋外に立っていた。
◆4 ここはどこだ!?
どういうことなんだ!?
そこは、うっそうとした森の中だ。
ごつごつした岩はコケにおおわれ、石だたみの道の横に、小川が流れている。
鳥の鳴き声が、のどかに聞こえてくる。
春馬、未奈、亜久斗、理子、大樹、慎太郎、サオリ、奏と竜也は渋谷にいたはずなのに……!?
ふりむくと、タツと鬼吉、そして幸一の死体は、すがたを消していた。
「……あたしたち、瞬間移動でもしたのかな?」
未奈に聞かれて、春馬は首を横にふる。
「いくら『絶体絶命ゲーム』でも、そんなことはできない。ぼくたちがいた部屋が、この森の中にあったんだ」
その証拠に床はそのままだし、くずれ落ちた壁や天井の残骸もある。
「でも、渋谷の地下にいたはずでしょう!?」
「たしかに不思議だけど、なにか仕掛けがあるはずだ」
春馬は、今までおきたことを、頭の中で整理する。
渋谷の地下に集合したあと、火事騒ぎがあった。煙を吸ってふらふらして、非常口から出たけど、床の穴から下に落ちた。あのとき、タツは防護マスクのようなものをつけていた。
ぼくたちは、気がつくとここにいて、そして、1時間45分が経過していた……。
「……そうか。ぼくたちがここにいることは、大して不思議じゃない」
「どういうこと?」
ほかの参加者も、興味しんしんの顔で、春馬と未奈の話に耳をかたむけている。
「渋谷の地下で吸った煙に、催眠ガスが入っていたんだ。穴から落ちている間に、眠らされた」
「そんなの数秒でしょう」
「いや、ちがう。落ちた先にクッションかなにかがあり、ぼくたちはそこで完全に眠ってしまったんだ。その間に、携帯電話やスマホをぬきとって、ここに運び、ぼくたちの目がさめるタイミングで、ここのクッションの上に落としたんだ」
春馬の謎解きを聞いて、慎太郎とサオリは、こそこそ小声でなにか話をしている。
「そげなこつがわかったところで、どうにもならん。問題は、ここがどこかばい!?」
いらいらしたように言ったのは、大樹だ。
「ここの場所なら、スマホのGPSでわかるんじゃないでしょうか」
理子に言われて、春馬はスマホの操作をする。
マップを開いて、現在地を示す矢印をタッチする。
設定されていません
「GPS機能は使えないみたいだ」
そのとき、亜久斗が黙って、1人で小道を歩きだした。
「亜久斗、どこにいくんだ?」
春馬が声をかけると、亜久斗がふりかえる。
「決まってるだろう。第1チェックポイントだ」
「チェックポイントがどこか、わかったのか!?」
おもわず聞くと、亜久斗はフッと笑った。
「教えないよ」
「……わかってるよ。それを見つけるゲームだろう」
「春馬のお人好しは、直っていないようだな」
冷たい笑みで、亜久斗が言った。
「人の性格は、かんたんに変わらないだろう。亜久斗だって、あいかわらず偏屈じゃないか」
「偏屈じゃない。おれは、合理的で素直なんだ」
「それ、冗談のつもりか?」
「おれは冗談は言わない」
これまで、『絶体絶命ゲーム』で、二度も亜久斗と戦った。
彼は頭がよくて、運動もできる。そして、憎らしいほど沈着冷静で異常なほど執念深い。
春馬に負けたのを、ずっと根に持っている。
「みんなの前で、謎解きをしてみせるなんてな。おまえには危機意識はないのか」
「一番危険な亜久斗に言われたくないよ」
「まぁ、いい。おかげで、ここがどこかわかった。それじゃあ、チェックポイントで会おう」
亜久斗は迷いのない足どりで、石畳の道を歩いていく。
「……彼についていこうよ」
慎太郎がサオリを連れて、亜久斗のうしろをついていく。
なるほど、その手があったな。
自分のヒントから推理できなくても、行き先のわかった人についていけばいいんだ。
でも、亜久斗と行動をともにするのは、危険すぎる。
慎太郎とサオリに忠告しようと、春馬が口をひらこうとしたとき、大樹がタッと動いた。
大樹は、とおりかかった犬の散歩中の女性に駆けよる。
「すみません、ここって、どこと?」
「話しかけたら、ダメだ!」
おもわず、春馬が大きな声を出すと、女性がこっちを見た。
「あなたたち、なんですか?」
女性が口をひらいた瞬間、大樹のスマホから、ピーッとホイッスルの音が鳴った。
「うわぁぁぁぁぁぁ!」
大樹が大声をあげて、地面をのたうちまわる。電気ショックだ。
声をかけられた女性は、焦ったように、足ばやに去っていく。
「大丈夫か? 大樹」
春馬が話しかけようとしたとき、春馬のスマホからも、ピーッとホイッスルの音が鳴る。
「えっ、どうして!?」
スマホの画面に目をむけるより先に、春馬の全身にも電気ショックが襲ってくる。
「どどどどどどうして……、ぼぼぼ……ぼくが……!?」
まるで針の山を転がされているように、体中に激痛が走る。
頭がおかしくなりそうだ。
「た……助けてくれ!」
大樹は苦しがりながら、そばにいた未奈に歩みよる。
「み、み、未奈……あ、あ、あ……危ない!」
春馬が叫んだが、遅かった。大樹が未奈の腕をつかんだとたん、
「きゃあっ!」
大樹の体に流れる電気ショックが、未奈にも伝達する。
それを見て、奏や竜也たちが、じりじりと距離をとった。
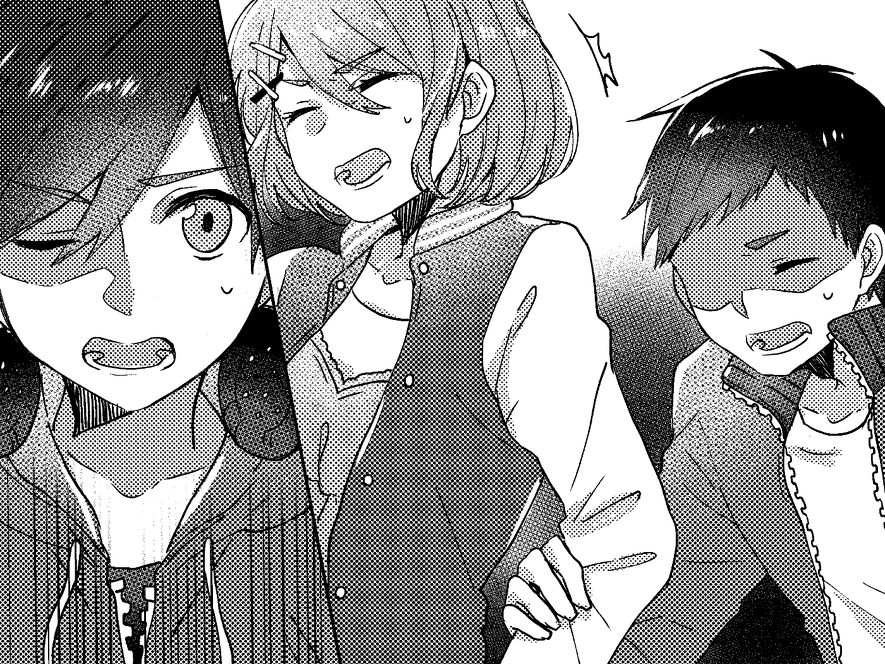
永遠のような1分間のあと、電気ショックはおさまったが、3人は、すぐには動けなかった。
スマホの画面を見ると、ホーム画面に、アプリと交ざって、1枚の黄色い四角が表示されている。
「……どうしてだ。ぼくは違反はしてないぞ」
つぶやいた春馬に、理子が話しかけてくる。
「あの、おそらく、春馬くんの声に、あの女性が反応したからかと思います……」
たしかに女の人は、大樹と春馬にむかって「あなたたち、なんですか?」と言ったのだ。
これが「会話した」ことになったのだ。うかつだった。
春馬と大樹は、イエローカードをもらったが、未奈のスマホにイエローカードの表示はない。
彼女は電気ショックに巻きこまれただけらしい。
スマホを確認している春馬に、理子が進みでた。
「あの……火事のときは、助けてくれて、ありがとうございました」
「いいよ、あれくらい。あたりまえのことをしただけだ」
「春馬くんは、このゲームの経験者なんですよね」
「うん。そうだけど……」
「わたし、お金がほしいと思って参加したんです。こんなにすごいゲームだとは知らなくて…」
「ぼくも、最初はかるい気持ちで参加したんだ」
「そうなんですか」
理子と目があって、春馬は少しドキリとした。
以前にも、金持ちのお嬢さまで美人の桐島麗華に見つめられたことがある。
理子は、美人というよりは、かわいいタイプだ。瞳が大きくてアイドルのようだ。
春馬が理子と話をしている間に、ほかの参加者は亜久斗がむかっていったほうに歩いていく。
「ぼくたちも移動しよう」
春馬は理子といっしょに、みんなのうしろについていく。
奏と竜也は話をしているが、大樹、未奈の間には距離がある。そのうしろを春馬と理子が歩く。
5分ほど歩くと、案内板があった。
『等々力渓谷と周辺のご案内』と書かれている。
「なるほど、ここは等々力渓谷か。渋谷からも近いな」
亜久斗は、ここにきたことがあるのかもしれない。
春馬の謎解きを聞いて、ここがどこかを、思いだしたにちがいない。
「等々力渓谷って、東京のどこばい?」
「東京の世田谷区にある、1キロくらいの渓谷だ。渋谷まで、電車で20分くらいだろう」
「渋谷から電車で20分のところに、こぎゃんと自然豊かな場所があるんか」
大樹が驚いている。
案内板には、最寄りの駅も描かれていた。
「徒歩5分ほどで、東急大井町線の等々力駅があるな」
「駅がわかれば楽勝や。奏、急ごうぜ」
竜也と奏が駆けていく。
「おれも急がんと。脱落はごめんばい」と大樹も走る。
「春馬、あたしたちも急ごう」
未奈のあとを、春馬も駆けだすと、理子もついてきた。
【新刊発売!リプレイ連載】『絶体絶命ゲーム3 東京迷路を駆けぬけろ!』第2回につづく(10月24日更新予定)
『絶体絶命ゲーム』コミカライズ版のためし読みを公開中!