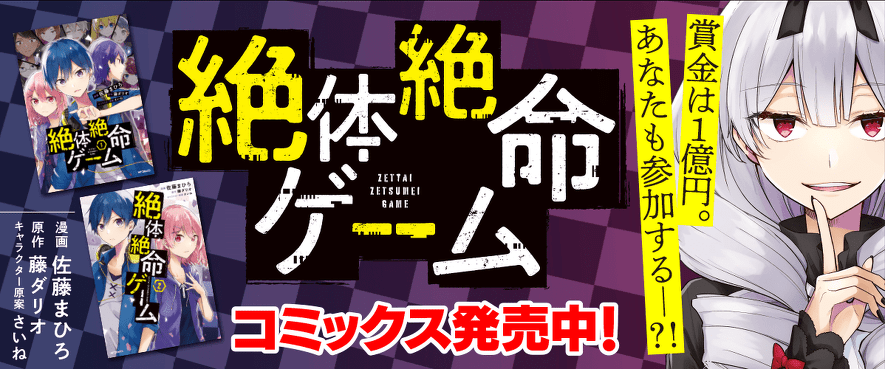◆9 確率は1/2
バスは高速道路を出て、一般道を走っていた。
「あと数分で荻窪駅だけど、春馬はどちらにいくか、決めたのか?」
亜久斗が、とうとつに話しかけてきた。
なにか企んでいるのだろうか?
警戒する春馬を見て、亜久斗はとってつけたように微笑んだ。
「怖い顔をするな。行き先を決めたか聞いただけだ」
「……人に意見を聞くときは、まず自分の意見から言うんじゃないのか?」
「あぁ、そうだったな。それなら、おれから言おう」
「だますつもりじゃないだろうな」
「人聞きの悪いことを言うな。おれはそんなに意地悪じゃない」
「亜久斗がほんとうにラッキーカードを持っているのなら、ぼくたちをチェックポイントとは逆に誘導するだろう」
「それなら、おれの意見とは、反対にいけばいいだろう」
しかし、それも考えているとしたら、その反対……。
いや、それも考えているとしたら……。
「さっきの話をきいて、鬼太郎茶屋か哲学堂公園、どちらにいくか、決めた人はいるか?」
亜久斗が聞くが、答える者はいない。
「どうやら、おれは嫌われているようだな。……まぁ、いいか。憎まれっ子、世にはばかるっていうからな。それじゃ、おれの考えを言おう。チェックポイントの場所は……」
そこで、亜久斗はじらすように深呼吸する。
「……哲学堂公園だ」
「根拠はあるのか?」
春馬が聞く。
「第2チェックポイントが鬼太郎茶屋だとしたら、8人のヒントの中に、水木しげるの代表的キャラクターである、目玉おやじ、砂かけばばあ、子泣きじじい、このあたりがないのはおかしい。つまり、消去法で哲学堂公園だ」
春馬の考えも同じだった。
哲学堂公園にはいったことがないのでよく知らない。でも、『ゲゲゲの鬼太郎』ならアニメを観ていた。ヒントの中に『ゲゲゲの鬼太郎』だという決め手がない。ということは、哲学堂公園になる。しかし、亜久斗と同じ場所にむかうのは危険な気がする。
「それで、春馬はどこにいくつもりなんだ?」
「ぼくも、哲学堂公園だと思っていたけど……」
春馬は自信なさそうに答えた。
「その顔は、おれと同じ場所にむかうのに不安を感じているんだな」
当たっているけど、春馬はこたえなかった。
「未奈はどう思う?」
これまでの経験上、勘のするどい未奈の意見を聞きたい。
「妖怪のことはよく知らないけど、あたしも哲学堂公園だと思う。勘だけど……」
亜久斗、春馬、未奈が哲学堂公園を選んだ。
「わたしは、未奈さんと春馬くんと同じところにいきます」
理子が言うと、大樹、奏、竜也も哲学堂公園を選ぶと言う。
残りは、サオリだけだ。
彼女はいっしょに行動していた慎太郎の死がショックだったのか、バスに乗ってから、ほとんど口をきいていない。
「サオリはどうする?」
春馬が聞くと、彼女は肩をビクッと震わせた。
「え、ええ。……みんなが哲学堂公園なら、アタシも……」
命がけのゲームなのに、ぼうっとしているんだろうか。
「全員が哲学堂公園を選んだわけだな。もし、まちがえていたら7人が死んで、ラッキーカードを持っている1人が優勝だ」
亜久斗は、他人ごとのように、かるい口調で言った。
もしかして亜久斗は、全員が哲学堂公園を選ぶように誘導したのか?
「それじゃ、本題に入ろう」
いつもの冷静な口調で亜久斗は、静かに参加者の顔を見た。
「─この中に、ウソをついている者がいる」
「ウソだって? どういうことだ?」
「おや、春馬は気づいてないのか?」
「それは……」
口ごもった春馬に、亜久斗はさらに嫌味をつづける。
「今日は調子が悪いようだな。これは『絶体絶命ゲーム』なんだぞ。東京観光かなにかと、かんちがいしてるんじゃないのか」
「そんなことはない」
むきになって否定した春馬だったが、亜久斗の指摘は、はずれてもいなかった。
3回目の『絶体絶命ゲーム』で、恐怖に麻痺してしまったのかもしれない。
「しっかりしろよ。今回はほんとうに殺されるんだぞ」
たしかに、そのとおりだ。
最初に参加したときは、こんなに恐ろしいゲームだと思わなかった。
2回目は強制参加だった。
今回は、勢いで参加したことを後悔している。逃げたい気持ちでいっぱいで、現実逃避しようとしているのかもしれない。こんなことだとほんとうに殺されてしまう。しっかりしないと……。
「おまえ、東京タワーで、なにを見てたんだ」
亜久斗に言われて、春馬の記憶の一部が、ゆっくりよみがえる。
東京タワーで見たもの……? 展望台からの東京の景色、モンスターの蝋人形、ガラス張りのエレベーター、1階の人ごみ、売店のおみやげに……。
ああ。あれか。……そういうことか。
「思いだしたみたいだな」
春馬は、うなずいた。
「でも、どうして彼女は、ウソをついたんだ?」
「彼女?」と未奈が眉をひそめて聞いた。
「この中に、1人だけ、第2チェックポイントのヒントを、見せなかった者がいるんだ」
春馬が言うと、大樹が首をかしげる。
「みんなのヒントば、見たけど……」
「いいや、スマホのディスプレイで、ヒント画像を見せあっただけだ。ぼくたちは、それを第2チェックポイントのヒントだと思いこんだ」
「どういうことですか?」
理子もわかってないようだ。
「その人だけ、第1チェックポイントのヒント画像を見せたんだ」
「その者に、ほんとうの第2チェックポイントのヒントを見せてもらおうじゃないか。それで、目玉おやじでも出てきたら、どんでん返しだ。行き先が変更になる。……どうかな、土屋サオリ」
サオリの顔色が変わった。
「な、な、なによ。アタシはちゃんと、第2チェックポイントのヒントを見せたわよ」
「往生際が悪いぞ。あれは東京タワーのヒントだ。みんなは見過ごしただけで記憶に留めなかった。おれと春馬は、見ただけじゃなく、記憶にしまったんだ。そうだろう、春馬」
「そんなにおおげさなことじゃないけど、ぼくもおぼえていた。売店にグッズが売られていたよ。サオリが見せたのは、東京タワーの公式キャラクターのノッポン兄弟だ」
「そ、それは……」
サオリが口ごもる。
「ほんとうのことを話してくれ」
春馬がやさしく声をかけた。
「……わかった、そのとおりよ。でも、『絶体絶命ゲーム』ってだましあいもありでしょう。それなら、少しでも自分に有利なほうがいいと思って……。でも、それだけよ」
「そんなことより、ほんとうの第2チェックポイントのヒントを見せろ」
亜久斗が強い口調で言った。
「これよ」
サオリはスマホのディスプレイを見せた。
地面に尻をついた子どもの石像の写真だ。これはなんだろう?
「あやうく、だまされるところだったな」
「この石像がなにか亜久斗はわかるのか?」
「あたりまえだ。『ゲゲゲの鬼太郎』に出てくる、子泣きじじいじゃないか」
「えっ?」
「子泣きじじいは見た目はおじいさんで、赤ちゃんのような泣き声を出すんだろ。これは、ただの子どもの石像だ」
「妖怪は、地方によって多少のちがいがあるんだ。赤ちゃんに化けていて、背負ったら石のように重くなるという話もある。この写真の子どもは、子泣きじじいだ」
亜久斗の言うことが正しいのだろうか……。
ほんとうに、これが子泣きじじいだとしたら、行き先は鬼太郎茶屋になる。
「サオリはこの写真を見て、第2チェックポイントが鬼太郎茶屋だと気づいたんだ。それで、おれたちに見せなかった」
自信満々で、亜久斗が言った。
「そうじゃないわ! アタシは写真をまちがえて見せただけで……」
「おかしいな。さっきは少しでも有利なほうがいいと思って、かくしたと言ってただろう」
亜久斗はまるで刑事のように、話の矛盾点を指摘する。
サオリは、ヒントを見せたくなかったようだ。でも、どうして?
「……もしかして。サオリがラッキーカードを持っているのか?」
春馬がたずねると、サオリはサッと視線をそらした。
「気づくのが遅いぞ。やっぱり、今日の春馬は調子が悪いな。でも、おまえの調子がどうだろうと、おれは容赦しない」
「ぼくの調子は関係ない。それよりも、サオリの話だろう」
「そうだったな。サオリ、ラッキーカードを持っているだろう?」
サオリは口を閉ざした。
「黙秘権か。それなら、おれが代わりに解説しよう。彼女はおれたちの話を聞いて、ある計画を思いついたんだ」
「どういうこと?」と未奈が聞いた。
「おれたちは哲学堂公園にいこうとしていた。全員がまちがえた場所にいけば、30分の延長のあるラッキーカードを持っている者が優勝になる。棚からぼたもちというやつだ。それで、サオリはこのまま本物のヒントを見せずに、みんなをまちがえた場所にむかわせようとしたんだ」
ふだんは無口な亜久斗だが、しゃべりは下手じゃない。
むしろ上手だ。引きこまれる。
「このゲームで、だます行為はあたりまえだ。だから、ほんとうのことを言う必要はない。ただ、そうなると、サオリは孤立するぞ」
亜久斗はそこまで言うと、じらすように間をとってから、
「ここで、だれも脱落しなかったら、サオリはおれたち7人を敵に回すことになる。このあとのゲームで、だれかと協力しなければならないかもしれない。そうなると孤立している者は不利だ。この世界で、集団ほどおそろしいものはないんだ。なあ、サオリ。今ここでラッキーカードを見せてくれたら、第2チェックポイントのヒントを隠したことは根に持たない。むしろラッキーカードを持っていると名乗り出てくれたことに感謝するはずだ。……見せてくれ」
ここまで言われたら、見せないわけにはいかない。
「わかったわ」
サオリは力なく言った。
「……たしかにアタシは、ラッキーカードをもらったわ。アタシ、このゲームをあまく考えていた。運動神経には自信があったけど、こういうのは苦手なの。でも、もうやめられないし。そんなとき、ラッキーカードが届いた。これを使えば、なんとかなるんじゃないかと……でも……」
サオリがなにかを言おうとしたが、すかさず亜久斗がさえぎった。
「言い訳は聞きたくない。ラッキーカードを見せてもらおう。おれは疑りぶかい性格なんだ」
亜久斗の独擅場で、ほかの者は口をはさむすきがない。
サオリがこまっていると、タツが口をはさんできた。
「ラッキーカードの入ってる、隠しフォルダの開け方かい? スマホ所有者本人の操作なら、受信メールの添付フォルダをタッチすりゃ開けられるよ」
タツの説明に従い、サオリがフォルダを開く。
ディスプレイに、『ラッキー』と書かれた黄金のカードが映った。
まちがいない。ラッキーカードはサオリが持っていた。
「ここでの脱落者はなしになったな。第2チェックポイントは、鬼太郎茶屋で決まりだ」
亜久斗はそう言うと、すべてが終わったように深く席に座った。
「…………春馬、いいかな」
小声で話しかけてきたのは、未奈だ。
「あたし、なにか納得できないの」
勘の鋭い未奈は、亜久斗の言動に、違和感をおぼえているようだ。
「ぼくも同じだ。なにか引っかかる」
「タツさんが『実力も運のうち』って言ったの、おぼえてる?」
春馬はうなずいた。
「自慢じゃないけど『絶体絶命ゲーム』で実力があるって言うなら、一番はあたしでしょう?」
春馬が苦笑いするが、未奈の言っていることは、まちがいとはいえない。
彼女は、このゲームで一度、1億円を手にしているのだ。
「それで?」
「実力も運のうちなら、実力のあるあたしが、ラッキーカードをもらわないとおかしくない?」
「そういえなくもないけど……。『実力』の定義がはっきりしないよ。今までの大会の勝者が、実力があるとは限らないし」
「じゃあ、どうしてサオリが実力があるのよ」
たしかに、それは疑問だ。
「今回のゲームは始まったばかりで、まだ横一線でしょう」
「そうだな。まだゲームは1つしか……。あっ、そういうことか!」
春馬のもやもやが晴れた。
危ないところだった。これはワナだったんだ。
なんとかしてこの状況からぬけ出さないと……。
春馬はいそいでスマホのディスプレイを開き、使えそうなアプリを探す。
あったぞ。メモ帳が使える。
◆10 意外な脱落者
春馬と未奈と理子は、路線バスに乗っていた。
荻窪駅でリムジンバスを降りたあと、JRに乗り換えて3人がむかったのは─中野駅。
大樹、奏と竜也が、ついてきていた。
「……ほんとうに、こっちで大丈夫なの、春馬?」
未奈が心ぼそそうな声で言った。
車内はすいていたので、春馬たち6人は、一番うしろの座席にまとまって座っている。
「わたしは春馬くんを信じています。……けど、どうしてこっちにしたんですか?」
理子が念を押すように聞いた。
「おそらく、哲学堂公園が、正解だ」
「おそらくって……たよりなかね。亜久斗とサオリは、鬼太郎茶屋にむかったぞ。どっちが正解なんや! おれは、負けられんばい!」
「それは、大樹くんだけじゃありません。全員が同じです!」
理子が怒るが、大樹の耳には入らない。
「おれの家は大雨で流された。そげな経験したやつが、ここにおるか?」
「大樹だけが特別だと思わないで! ここにいるほとんどの人はつらい経験をしているわ」
未奈がめだたないように、おさえた口調で言うと、みんなが黙る。
「……おれは、こんゲームに勝って、家族が安全に暮らせる家ば手に入れるーったい」
「そういうのって、ほんとは、国の仕事ですよね?」
つぶやくように言ったのは理子だ。
「国も政治家も、なんちゃしてくれん。ちっぽけな仮設住宅に押しこめて、あとは知らんぷりばい。世間が同情してくれるんも、災害後のせいぜい1カ月や」
大樹の話を聞いて、春馬は暗い気持ちになった。
子どもの暮らしは、親の能力で大きく左右される。
大人なら自分のがんばりで生活を変えられるかもしれない。でも、子どもはそうはいかない。
今の生活からぬけだすには、『絶体絶命ゲーム』のような危険を冒さなければならない。でも、そんな世界、正しいのか? 今は、考えてもしかたがないけれど。
「春馬が、メモ帳アプリに書いてたことは、ほんとうなんか?」
たしかめてきたのは竜也だ。
リムジンバスの中で、春馬は、スマホのメモ帳にあることを書いて、亜久斗以外の全員にそっと見せてまわった。
『亜久斗にだまされるな。ラッキーカードは、亜久斗も持っている』
「あれを見て、オレは春馬についてきたんやぞ」
「じゃあ、サオリの見せてくれたラッキーカードは、にせものだったってこと?」
未奈の質問に、春馬は首を横にふる。
「タツさんは、ラッキーカードが1枚だけだとは言わなかった」
「いいや、言ったぞ」
大樹が言うと、未奈たちは首をかしげて考える。
「『カードを持っているのが1人』と言ったのは、亜久斗だ。彼はみんなに、ラッキーカードは1枚しかないと思いこませたんだ」
「どうして、そんなことをしたの?」
「ゲームに勝つためだ。全員をまちがえた方向にいかせて、ラッキーカードを持っていない者を脱落させる計画だったんだ」
「どうして、あいつがカードば持ってるってわかるんと?」
「タツさんが言っただろう。『実力も運のうち』だって」
「ええ、おぼえています。運も実力のうちと言いまちがえたのだと思っていましたけど……」
理子が言った。
「ぼくもはじめはそう思ってた。でもタツさんそのあと『ラッキーは優秀な者にいく』と言ったんだ」
「優秀な人って……あたしだよね」
未奈は、まだ不満そうだ。春馬は苦笑いする。
「実力っていうのは、今日の成績のことなんだよ」
「今日って、まだ1つしかゲームをしてないでしょう」
「そうだ。1つめのゲームのあと、最初に東京タワーに到着した亜久斗とサオリを、タツさんは『優秀だ』と言ってた。『ラッキーは優秀な者にいく』というのは、ラッキーカードは亜久斗とサオリにいくという意味だよ」
「ああ、そういうこと」と未奈は納得する。
「人間観察が得意な亜久斗は、サオリの変化を察して、彼女にもカードが届いたと気づいたんだ。サオリが第2チェックポイントのヒントを隠したことを利用して、ぼくたちを反対方向にいかせることを思いついた」
「春馬の話はわかったけど、問題なのは第2チェックポイントの場所やろう」
大樹に言われて、春馬は小さくうなずいた。
「第2チェックポイントは、哲学堂公園にまちがいないよ」
春馬は自信を持って、うなずいた。
亜久斗は小さなミスをおかした。彼は、春馬に哲学堂公園にいったことがあるか確認した。
春馬は、それが気になっていた。
つまり、哲学堂公園にいったことがあれば、さっき見た8つのヒントで、チェックポイントがはっきりとわかるってことだ。
「哲学堂公園が正解なら、なんで亜久斗は三鷹行きの電車に乗っていったの?」
首をかしげながら未奈が聞いた。
「ぼくたちを、疑心暗鬼にさせるためだ。自信満々に行動していれば、1人くらい亜久斗についていくかもしれないだろう」
「サオリはついていった……」
「サオリは、亜久斗といっしょにいれば脱落しないと考えたんだろう。あの2人はラッキーカードを持っているからな。三鷹ですぐ引きかえしてくれば、制限時間に間にあうはずだ」
春馬たちは、『哲学堂公園入口』の停留所でバスを降りた。
住宅街のまんなかに、広大な敷地の公園がある。
園内は豊かな緑があり、グラウンドやテニスコート、ユニークな建物と奇妙な石像がある。
グラウンドでは草野球の試合がおこなわれ、遊歩道を親子づれや老人がのんびり散策している。
「公園のどこへいけばいいのかわからないけど、とりあえず入ってみよう」
正面口から公園に入っていくと、『哲理門』と書かれた、お堂のような正門がある。
「春馬くん、これ見てください!」
理子が興奮した声を出す。
哲理門の建物内に、大人くらいの大きさの不気味な彫刻がある。
右は天狗で、左はホラー映画に出てきそうな女の幽霊だ。
天狗は亜久斗のヒント、女の幽霊は理子のヒントと一致する。
正門をくぐったとたん、ブルブルブル……とスマホが振動した。
第2チェックポイント到着
時間は12時52分。
「第2関門クリアだ!」
未奈、理子、大樹、竜也と奏にも、到着を知らせるメールが届く。
春馬はほっと胸をなでおろす。
到着メールは届いたが、第1チェックポイントのようにタツや鬼吉はあらわれない。
春馬が考えていると、理子が案内板の前で手まねきしている。
「これを見てください」
案内板の地図に、園内の建物や石像の場所がイラスト入りで描かれている。
春馬たちが受け取った8つのヒントは、すべて公園内にあるようだ。
「ここにきたことがあったら、すぐにわかったんだ。それにしても奇妙な公園だな」
春馬はあたりを見まわした。
春馬たちが到着してから20分ほどがすぎたころ、悠々とした足取りで、亜久斗とサオリがやってきた。
時間は1時18分。
「……ふん。かんたんに引っかかるとは思わなかったが、企みを見やぶられるのはくやしいね」
哲理門をくぐった亜久斗は、悪びれない態度で言った。
「亜久斗も、ラッキーカードを持ってるんだな」
「その質問に答える必要はないだろう。春馬の推理したとおりだよ」
「ぼくがどう推理したか、亜久斗は知らないだろう?」
亜久斗はふっと鼻で笑っただけで、それ以上は話そうとしない。
そのとき、
「えっ、どうして?」
サオリが、スマホのディスプレイを見て蒼白な顔をしている。
「どうしたんだ?」
サオリがスマホを見せてくる。
第2チェックポイント─土屋サオリ、脱落
電気ショックまで、残り3分
どういうことだ?
ラッキーカードを持っているサオリは、リミットが30分延長されるから、1時30分までに到着すればいいはずだ。それが、どうして脱落なんだ!?
春馬が考えていると、公園の奥から笛と太鼓の音色が聞こえてくる。
「タツさんだ。いってみよう!」
春馬たちが駆けていく。
中央の広場にある、『四聖堂』という正方形の建物から、笛や太鼓の音色が聞こえてくる。
四聖堂をのぞくと、雅楽の演奏者をバックに、タツが優雅に日本舞踊を舞っている。
「タツさん、教えてください!」
春馬が声をかけると、タツがじろりとにらんだ。
「邪魔をするんじゃないよ、無粋者!」
タツが怒るが、春馬はひるまない。
このままだと、サオリが電気ショックで死ぬ。
「タツさん、お願いです。話を聞いてください」
「しょうがないね」
タツが舞をやめると、笛や太鼓の演奏も止まる。
「タツさん! アタシ、制限時間内に第2チェックポイントに到着しました! これはなにかのまちがいです!」
泣き出しそうな声でサオリが言った。
「知ってるよ。あたしゃゲーム案内人だからねェ」
「どうしてアタシが脱落なんですか?」
「決まってるだろう、制限時間内に到着しなかったからさ」
「遅れてないわ!」
「お前さんが哲理門をとおったのは、1時18分。制限時間を18分オーバーしてるじゃないか」
「アタシ、ラッキーカードがあります!」
サオリは、スマホをタツに見せようとするが、
「おッとざんねん、そのカードは使えないよ」
「えっ、どうして!?」
「お前さん、イエローカードをもらっただろ」
春馬は、はっとなった。
ゲームの説明のとき、イエローカードをもらうとペナルティーとして特典が受けられないことがあると言っていた。それじゃサオリは……。
「─土屋サオリ、お前さんはここで脱落だよ」
タツが冷たく言いはなった。
「いや、そんなの……チャンスをちょうだい、チャンスを……」
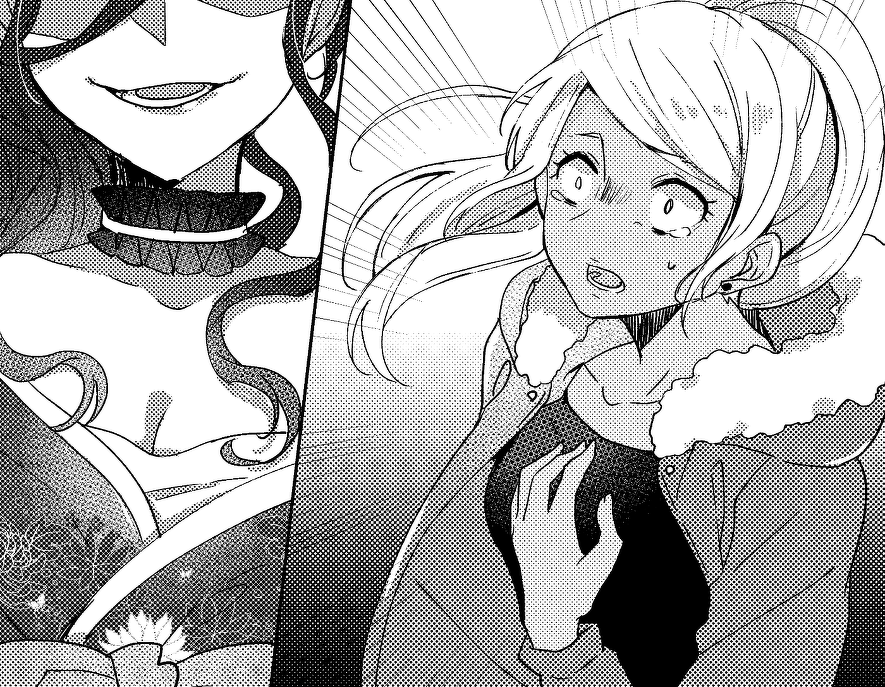
そのとき、サオリのスマホがブルブルブル……と振動する。
「3分経ったようだね。さようなら、土屋サオリ」
「ギャ─ッ!」
叫んだサオリは、激しく体を震わせる。
「サオリ……!」
思わず駆けよろうとした春馬を、未奈がおさえる。
「彼女に触れたら、春馬も死んじゃう」
サオリは、口から泡を吹いてけいれんし、やがて動かなくなった。
「こんなの、ひどすぎる……」
みんな、サオリから目をそらす。
「鬼吉、処理しておいて」
タツに言われて、鬼吉はサオリの死体に黒い布をかける。
「お前さんたちは、あたしについてきな!」
タツは、春馬たちを、公園の奥に連れていく。
木々にかこまれた小道を3分ほど歩くと、木造平屋の古い建物がある。
看板に『髑髏庵』と書かれている。
名前は不気味だが、この建物は、ただの休憩所だ。
春馬たちは、8畳ほどのがらんとした部屋に連れてこられた。
─幸一、慎太郎につづいて、サオリも死んだ。
今回のゲームは脱落したら、すぐに殺される。
どうして、こんなゲームに参加してしまったんだ……。
ブルブルブル
スマホが振動して、春馬は驚いて飛びあがりそうになった。
全員に、同時にメールが届いたようだ。
第3チェックポイント 制限時間は、午後3時00分
時間オーバーは─脱落
『ヒント』のファイルを開いた春馬は、目が点になった。
【新刊発売!リプレイ連載】『絶体絶命ゲーム3 東京迷路を駆けぬけろ!』第3回につづく(10月31日更新予定)
『絶体絶命ゲーム』コミカライズ版のためし読みを公開中!