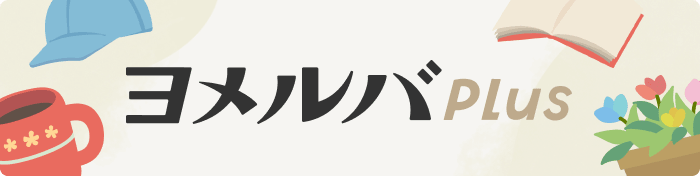3 オレンジと悪党と
おれは、マサキといっしょに屋敷を出て、街にむかってぷらぷらと歩いていった。
季節は夏だ。
気温は40度に迫るいきおいだが、カラッとした気候のせいか、そんなに不快感はない。
この暑さでも、街は人であふれていた。
ところどころ削れた石畳と、古いレンガの建物が歴史を感じさせる。
建物は低いものが多く、高くてもせいぜい3階ぐらいだ。
街中にいる人たちは、髪の色も目の色も肌の色もさまざま。この国の人間には「こういう顔だちが標準的」というような特徴がない。
それというのも、移民が多く、よその国から流れ着き、さらにここで結びついて住むようになったという歴史があるかららしい。
いまでも他国から移り住んでくる人がいる。
そのおかげもあって、日本出身のおれも、容姿で目立つことはない。
だからこそ、師匠はこの国に拠点をおいたのかもな。
そんなふうに、ふと思う。
おれとマサキは、街中を歩きながら、ひときわ活気のある通りに出る。
道の片側には、ずらりと屋台がならんでいる。
このあたりで、一番大きな市場だ。
野菜や果物、肉なども、ここで買える。
飲みものや軽食などの屋台もある。
おれの日本での記憶は、おぼろげなところもあるが、「お祭りの屋台」というのが、こんな雰囲気だった気がする。
「おや。坊ちゃんじゃないか。買ってかないかい?」
顔見知りの果物屋のおばちゃんが、声をかけてくる。
「じゃあ、オレンジを2つもらおうかな」
「ありがとう! 1つおまけしとくよ」
おばちゃんが、オレンジを3つ手わたしてくる。
おれは受けとると、1つ、マサキにわたす。
「『坊ちゃん』という呼ばれかたにも、すっかりなじみましたね」
マサキは、オレンジの皮をむきながら言う。
「金持ちそうな豪華な屋敷に住んでいるから坊ちゃんっていうのは、安直だと思うんだがな。もう訂正するのもあきらめた」
幼いころから住んでいるため、この街の住人からすれば、おれは親戚の子どもみたいなものなんだろう。
何度か『坊ちゃん』呼びはやめてくれと言ったのだが、きいてくれたためしがない。
「同じ屋敷に住んでいるのに、マサキは、なぜ坊ちゃんと呼ばれないんだ?」
おれは、オレンジをかじると、不満げにマサキをにらむ。
「それは、おれが従者だからです」
マサキが、すまし顔でこたえる。
街中で、マサキに従者らしいそぶりをさせたことは、あまりない。
なるべく友人としてふる舞うように、言ってある。
それでも、マサキが『坊ちゃん』と扱われないのは、それすらも見透かされているからなのか。
店頭に立ち、日々、人を観察している者の目は、侮れない、ということなのかもな。
「それにしても、このオレンジうまいな」
おれは、2つ目のオレンジもペロリとたいらげる。
甘くてジューシーで、のどもうるおう。
「あの店で買うものは、外れがありませんから」
マサキが言う。
ときどきこの市場で買い出しをしているマサキの言葉なら、実際そうなのだろう。
そのまま2人で歩いていくと、
「坊ちゃん。散歩かい?」
「ああ。気分転換だ」
「いい牛肉が手に入ったんだ。坊ちゃんの口に合うんじゃないかな」
「いいね。家の者に伝えておくよ」
「こないだは、質のわるい客を追いはらってくれて、ありがとうな」
「ちょうど、通りかかっただけだよ。また、なにかあったら、言ってくれ」
次々と、顔見知りが声をかけてくる。
「坊ちゃん。いいリンゴが手に入ったから、シャーベットにしたんだ。どうだい?」
屋台の顔見知りのおじさんからも、声がかかる。
前はフルーツジュースの屋台をしていたはずだが、商品を変えたようだ。
さっきオレンジを食べたばかりだが、この暑さで汗が噴きだしている。
冷たいものは大歓迎だ。
「2ついただくよ」
おじさんから、シャーベットを2つ買って、マサキに1つわたす。
「ありがとよ!」
おじさんの声を背に、シャーベットを舐めながら、通りを進む。
シャーベットのおかげで、体の内側から暑さがやわらぐ気がする。
そのまま、市場のある通りのはしまで、やってくる。
この先は、住宅街が広がっている。
おれは迷わずに、住宅街へと進む。
この周辺なら、幼いころから歩きまわっていて、地図どころか景色まですべて頭の中に入っている。
住宅街は、歴史のある家と、ごく新しい家が混在している。
庶民の住むこぢんまりとした家が多く、大きな家や屋敷などは、郊外にあることがほとんどだ。
それはこの街のつくりであって、となりの街にいけば、高級住宅街があったりするから、この街特有のルールのようなものだ。
住宅街の通りはせまく、玄関前に住人が出てはのんびりとおしゃべりをしている。
市場とはちがったにぎやかさがある。
「坊ちゃん。お散歩かい?」
「この間負けた、チェスのリベンジさせてくれよ」
前に家の前でチェスの勝負をしたおじいさんが、声をかけてくる。
「ああ、今度また、スナックでも持って家を訪ねるよ」
「マサキ君。この前は、息子にサッカーを教えてくれてありがとう」
「いえ。時間が空いていたので」
30代ぐらいの男から、マサキも声をかけられて、話をしている。
「なんだ、マサキ。そんなことしていたのか?」
初耳だ。
そもそも、ボールを蹴っているところも、見たことがない。
「たのまれたときに、時間があったので」
「おれとは、サッカーしたことなんてないだろ」
「さそわれたことがなかったので」
マサキは、しれっとした顔で言う。
「じゃあ、今度さそうとしよう」
「サッカーにですか?」
おれが言うと、マサキがいやそうな顔をする。
そんな会話をしながら、住宅街を歩いていく。
このあたりの人たちは、あまり裕福ではない。
屋敷からやってくるおれたちに対して好意的なのは、ちゃんと理由がある。
ちょっとした仕事をまわすことがあるからだ。
届けものであったり、調べものや街のうわさ調査、なんてものもある。
それが彼らの小遣い稼ぎになっている。
それでいて、師匠やおれがいったい何者なのか――といったことを詮索しないでいてくれる。
これが、おれたちの暗黙の了解なのだ。
それをはじめたのは師匠で、幼いころからこの街で暮らすおれと彼らの間に、上下関係があるわけじゃない。
おたがいに、気安い話のできる間柄だ。
住宅街をぬけて、さらに横道に進んでいく……と、とつぜん街の雰囲気が変わる。
道ばたにただすわりこんでいるだけの人が多く、にらむような、するどい目で見てくる者もいる。
――ここはスラム街。
いわゆる、貧困層が暮らす区域だ。
家も、かろうじて雨風がふせげるようなものだったり、元はなにかわからないものがゴチャゴチャと積み重なったままだったりする。
服装もボロボロに汚れていたり、着古したものを着ている。
街の中心からわずかの距離しか離れていないが、このあたりでは犯罪があっても黙認されることもある。
自衛できなければ金品を奪われたり、最悪、命を失うこともあるかもしれない場所だ。
それでも彼らがおれたちを狙ってこないのは、以前、スラム街で強盗に襲われたときに、何度か叩きのめしたからだろう。
おかげで、このあたりのチンピラには、顔を知られている。
下手に手を出さないほうがいい相手。
ただし、我がもの顔でここを歩かれるのは気に入らない――そういう視線がむけられているのがわかる。
じつは、ここにも、おれの知り合いがいないこともない。
だが、こういう表立った場所では、話したりはしない。
おれたちと関わっているとわかるだけで、スラム街の住人にとってはリスクだからだ。
7~8歳ぐらいの子どもたちが、細い通りを笑いながら走りぬけていく。
子どもたちの顔に、明るさがあるのが、このスラム街がまだ「最悪ではない」という証かもしれない。
もっとひどい場所は、ほかにもあった。
そう、たとえば……。
「マサキと出会ったのも、こういうところだったな」
おれは、昔のことを思いだしながら言う。
マサキとはじめて出会ったのは、おれがさっきの子どもたちと変わらない7歳ぐらいのころ、こことは別の国だった。
その街で、守ってくれるおとなもいない存在だったマサキは、裕福そうな身なりだったおれを狙って、持ちものをすろうとした。
「あのときは……恭也様を狙うなんて、おそれ多いことを……」
マサキは、申しわけなさそうにうつむく。
「あの国では、それが生きていく手段だったんだ。しかたがないさ」
幼かろうと年老いていようと、スラム街の住人が犯罪に手を染めるのは、めずらしいことじゃない。
法に触れるやりかたで、わずかながらの金を手に入れて生きていることもある。
結局、なにも奪われることなくマサキを捕まえたおれは、どうしてかマサキを連れていくことにした。
そうしたくなったから。
最初、マサキは殺されるとでも思ったのか、必死で逃げだそうとして、連れていくのには苦労したけどな。
「狙った相手が恭也様でなかったら、おれがいま生きてこうしていることはなかったでしょう。まさか、拾っていただけるとは」
「なにかの縁だと思ったからな」
おれの勘は、あたっていたわけだ。
これほど優秀で忠実な従者として、いまだにおれのそばについていてくれるわけだからな。
本人には話していないが、幼いマサキを連れ帰ったあとも大変だった。
師匠の配下の者たちからは、マサキを引き入れることを反対された。見られたことも問題だと、いっそ消してしまおうという過激な意見すらあった。
その中で、師匠だけがひと言、
「そうか。おまえが責任を持て」と、認めてくれたのだ。
師匠の決定に、配下が逆らえるはずはない。
それからは、なにも言われることなく、マサキにおれの「従者」という役目を与え、師匠やアランなどに手を貸してもらいながら、鍛えてきた――おれから片時も離れない者となってもらうために。
そんな昔話を思いだしていると、いつの間にかスラム街の中でもさらに人気の少ない路地にきていた。
もどるか。
そう思って、きびすをかえそうとしたときだ。
「あんたたちなんかに、わたすもんか!」
「うるせえ! 命が惜しければわたせ!」
争う声がきこえてきた。
4 おせっかいな通りすがり
「いこう」
ひと言だけマサキにむかって告げると、おれは声がきこえたほうにむかって走った。
マサキも当然のようについてくる。
路地を右に曲がり、まっすぐに進む。
たしか、こちらのほうからきこえたはずだが……。
おれが足を止めて、まわりを見ると、左の路地に人の気配があった。
迷わずに路地に入ると、その行き止まりで、褐色の肌と気の強そうな瞳をした少女が、チンピラらしき男たち4人に追い詰められていた。
少女の手には、大きめなアタッシェケースがあったが、旅行者のようには見えない。
どういう事情か知らないが、おれが気づいた以上は首をつっこまないという選択肢はない。
おれは、男たちのほうへスタスタと近づいていく。
「おれの視界で、子猫ちゃんに手をあげようとは……見のがすわけにはいかないな」
おれは、チンピラらしき男たちにむけて言う。
となりでマサキが、「はあぁ……」と、おおげさにため息をついている。
「なんだ、てめえら!」
チンピラが、おれたちをふりかえってどなる。
……ん?
どうやら、チンピラたちは、おれたちの顔を知らないらしい。
スラム街のチンピラなら、おれたちを見てなにか反応するはずだ。
「……どうやら、このあたりの人間じゃないな」
「なにを言ってやがる!」
おれたちが動じる様子がないとわかったのか、チンピラの1人が、殴りかかってくる。
楽勝だな。
おれは、チンピラの拳をかわして、左足をかるく前に出す。
「う、うおっ!」
ドスンと音を立てて、チンピラが前のめりに地面にころぶ。
「や、やる気か!」
「なめるなよ!」
いや、おれはなにもしていないが?
残りのチンピラ3人が、おれたちのほうをむくと、懐からナイフを取りだしてかまえる。
殴りかかってくる男を、ふたたびかわし、足をかけてころばせる。
顔面から倒れこんだ1人も、鼻血を出しながら立ちあがると、まだめげずに血走った目でナイフをむけてくる。
まったく。おだやかじゃないな。
このあたりのチンピラなら、引きぎわもわきまえているというのに。
いくら人気が少ない場所とはいえ、ナイフを振りまわして争っていたら、スラム街でも人目につく。
……引きぎわがわからないか。それとも――――引けない理由があるか。
おれは、チンピラに追い詰められていた少女をちらりと見る。
状況を見さだめようとしているのか、身動きはせず、こちらをうかがっている。
彼女のほうが、よほどチンピラより優秀そうだね。
「おらっ!」
かけ声だけは一人前のチンピラが、ナイフをつきだしてくる。
丸見えのナイフの軌道を、おれは小さくステップを踏んでかわすと、そのままそいつの腕をとる。
「いてててててっ!」
チンピラの腕をかるく決めてやると、すぐにナイフを取り落とした。
そのまま、チンピラの背中方向に腕を押さえこんで制圧する。
「いてえ! はなせ!」
チンピラは、地面に押さえつけられたまま、叫んでいる。
「さわがしい」
おれは、身動きのとれないチンピラに、一撃を加えて意識を失わせる。
「なめやがって!」
背中をむけたおれが無防備だと思ったのか、残ったチンピラ3人が、まとめてむかってくる。
「なめているのは、おまえたちだ。この方をだれだと思っている」
マサキが割って入ると、1人のチンピラの顎を、パンチで打ちあげる。
「がはっ」
マサキは、もう1人の顔面を、回転しながらのバックハンドブローで強打した。
「ぎゃあっ!」
チンピラ2人はうめき声をあげて、よろよろとうしろに下がる。
それを見て、残った無傷のチンピラが、あとずさりする。
「ひ、引きあげるぞ!」
無傷のチンピラの言葉に、あっという間に、動ける仲間が気絶しているチンピラをかつぎあげる。
「覚えてろよ!」
決まりの捨て台詞を言って、チンピラたちが路地から、逃げだしていく。
あざやかな逃げとは言い難いが、こちらも追いかけるつもりはない。
自分たちの足で逃げだせるように、わざわざ加減してあげたんだからね。
「きみたちみたいなやつらのことを、おれが覚えてるわけないだろ」
おれは、チンピラたちの背中にむけて言う。
むさくるしい男の顔を、脳におさめておく趣味はない。
それよりも、だ。
「さて。もうだいじょうぶだよ、子猫ちゃん」
おれは、笑顔になって少女のほうへとむきなおった。
が、そこには少女のすがたはない。
「……マサキ? ここにいた子猫ちゃんは?」
おれは、きょとんとした顔で、マサキにたずねる。
「さっき、その壁をよじのぼって、逃げていきましたよ」
マサキが、目の前の3メートルはある壁を指さす。
「なんで、言ってくれないんだ!」
「まさか、あんな逃げかたをするとは思いませんでしたし。これ以上、あの者と関わり合いにならないほうがよいのでは?」
あきらかに面倒ごとだ、とマサキは言いたげだ。
「マサキ、まだおれをわかっていないな。子猫ちゃんが困っているなら、それを助けないという選択肢があると思うか?」
「……恭也様には、ないんでしょうね」
マサキは、あきれ顔をしている。
おれは、3メートルの高さの壁に近づくと、その場で飛びあがって、ひらりと壁の上に乗る。
壁の上で見まわすと、家々の屋根を飛びうつりながら走り去る少女のすがたが見えた。
「なかなか機敏な子猫ちゃんだね。さあ、マサキ。おせっかいを焼きにいこうか」
言いながらおれは、少女のあとを追って動きだした。
第2回へ続く(5月30日公開予定)
【6月14日発売!】つばさ発の単行本「角川つばさBOOKS」、『怪盗ファンタジスタ』、乞うご期待!